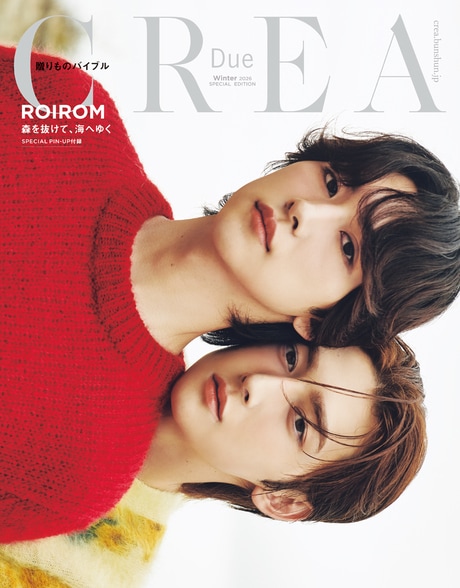親の所有意識が子どもを縛る

共同体の縮小は親離れ・子離れができない親子の増加にも影響している。
「親が子どもに対していつまでも支配的な態度で接するのは、子どもを自分の所有物のように考えてしまうから。共同体で育てていれば、他人に懐いたり、叱られたりと母親の手を離れる瞬間が多くなるため、所有意識は薄れていくものなんです。
それが特に都市部で暮らす現代の子どもはいろいろな制限があり、家と学校、塾の往復ばかりで付き合う年齢の範囲も限られています。重要なのは小さい頃からいろんな人と触れ合うこと。社会に出れば年齢、経歴、性別、知識、技術、価値観などが異なる様々な人たちと職場で渡り合っていかないといけないからです。経験しておかなければ、突然の出来事に対応できないですからね」
“不測”に対応できない子ども
地震や山火事など天災のニュースも後を絶たない。山極さんは、現代の人の在り方にも警鐘を鳴らしている。
「子どもの頃から答えのない現象に対処する能力を育てる必要があります。“遊び”というのは明確なルールがあるわけではなく、状況や相手、雰囲気によって変わっていくもの。だからこそ材料がなくても、想像力を培っていけるんです。詩人のジョン・キーツによる“ネガティブ・ケイパビリティ”とは、答えのわからないものをそのまま受け止める能力のこと。迷いながら答えに到達するプロセスこそが大事です。
また、問いを立てる能力を培うことも重要。現代教育は答えのわかっている問いを与えて、答えに早く到達することばかりを教えていますが、人にとって大事なのは出会いと気づきです。影響を与えるのは、人間ばかりではありません。虫や鳥、動物、川、山……様々な出会いによって新鮮な気づきを得ることこそが学びの本質なのです」
山極寿一(やまぎわ・じゅいち)
1952年、東京都生まれ。霊長類学者、人類学者、総合地球環学研究所所長。2020年まで京都大学総長を務める。ゴリラ研究の世界的第一人者。サルや類人猿との比較から、人間の社会や文化、未来を探究する。

老いの思考法
定価 1,650円(税込)
文藝春秋
年齢を重ねるごとに美しくなるゴリラは“老い″をめぐる学びの宝庫。人間に重ねてみると、読むだけで老いることが怖くなくなるどころか楽しみになる。コミュニケーションの本質や共同体についてもためになる。
続きは「CREA」2025年夏号でお読みいただけます。
- date
- writer
- staff
- 文=高本亜紀
写真提供=山極寿一 - category
CREA 2025年夏号
※この記事のデータは雑誌発売時のものであり、現在では異なる場合があります。