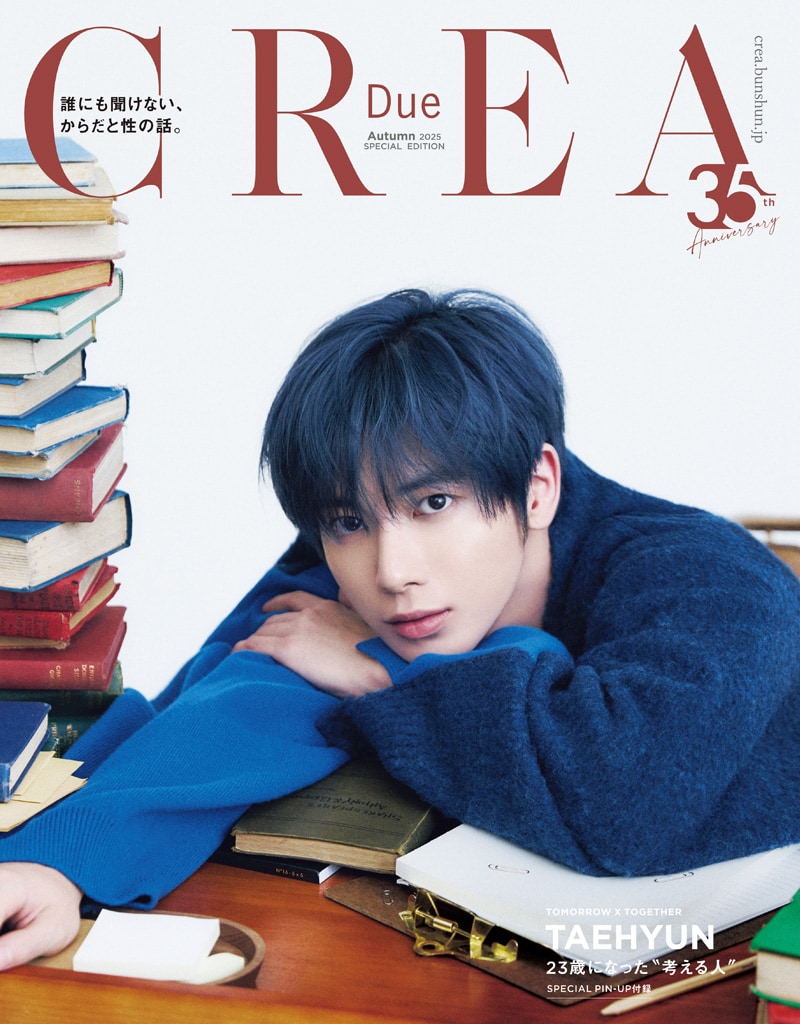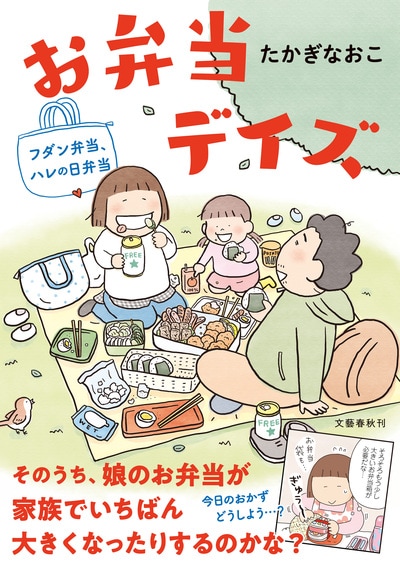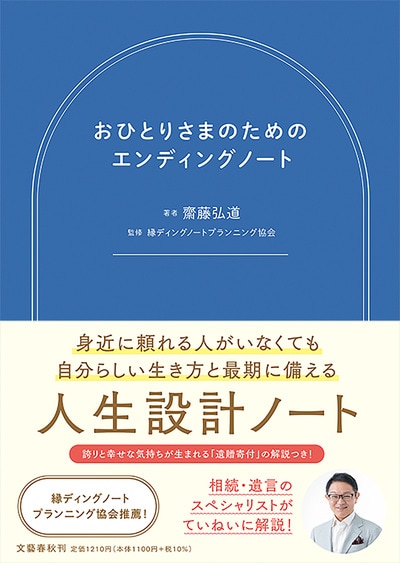「雨と川の音」 1958年(有栖川有栖・選)
有栖川 今回私は、捕物帳や推理小説を軸に選びました。史伝は、どれも面白すぎて選べなくなってしまって……。
宮部 この作品、未読でしたがとても面白かったです。
有栖川 清張さんの時代ものは、えてして2部構成になっていると思いませんか? 実は、この作品はもともと「オール讀物」で2回に分けて掲載された作品が一つに合体したものなんです。前半に来る脱獄パートは「なかま」、後半の推理小説らしいパートは「雨と川の音」という題でした。それぞれ何となく完結していますが、合わさっても楽しめる。前半と後半とで、二つの味を提供する清張さんのサービス精神を感じますし、物語の変幻自在さを存分に味わえます。

北村 主人公の与太郎は牢から溜(たまり)(病人や年少者を収容する牢)へ移るのに、医者とうまく折り合いをつけて仮病を使ったことを、先に溜にいた男に嗅ぎつけられる。二人は共に島送りから逃れるため、結託して脱獄を目指す――というところから、物語が動き出します。小説のきっかけにあるのは、上の差配ひとつで人生が決まってしまうという、清張先生の作品によく見られる運命の恐ろしさ。例えば戦争の赤紙についてもそうです。非常にずさんなやり方で徴兵されたり、事務方のちょっとした処置で人生を狂わされかねない。赤紙について各所で書かれていることからも、その恐怖に対する思い入れが強かったことが窺えますね。
有栖川 おっしゃる通りです。自分の生き死には、他の誰かにとっては単なる事務処理に過ぎない、という場面は清張作品によく出て来ます。
宮部 牢内の生活もリアルで恐ろしい。島送りになる先が、三宅島か、もしくはさらに遠い八丈島か――。現地での生活は苦しくても生きる道はまだあります。でも、佐渡は……。
有栖川 清張作品を読めば読むほど、佐渡島が怖くなります。佐渡の金山見学へ行った際に再現展示を見たんですね。ある人形が「俺は品川無宿だ」と言っていて、さながら『無宿人別帳』のようで。「清張作品の読者がこの展示を作ったんじゃないの?」と思いました(笑)。
- date
- writer
- staff
- 文=有栖川有栖、北村 薫、宮部みゆき
- category