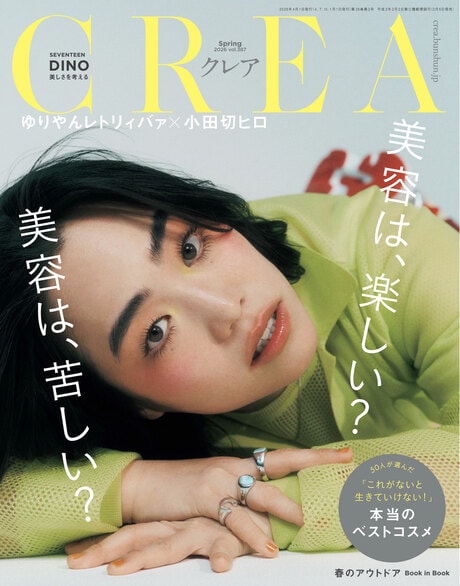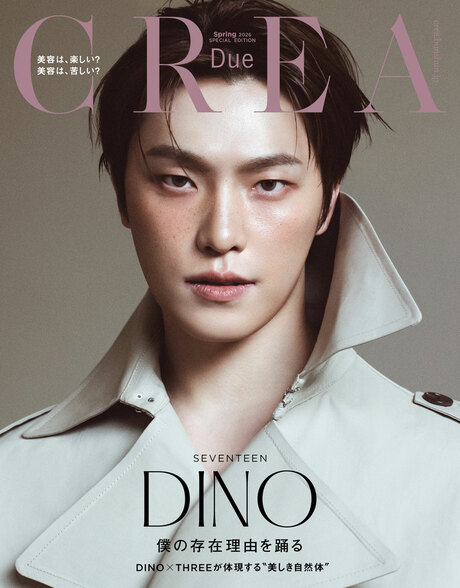古の時代から神湯と呼ばれ親しまれてきた島根県・玉造温泉の湯宿「界 玉造」。後篇では、滞在中に参加できる文化体験プログラム「手業のひととき~蔵元が伝える酒造りの世界と日本酒の美味しい飲み方」をメインにご紹介します。と、その前に、郷土色豊かな朝ごはんでパワーチャージ!
お腹の底から温まる“杜氏鍋”の朝食
地域色を感じる食材や調理法を取り入れた「界」のご当地朝食。ここでは、酒粕を使った「鶏つくねの杜氏鍋」や、のどぐろの干物などを取り入れた和食膳を用意しています。ほかにも地元の漬物や卵焼き、ゆばのあんかけなど、滋味深いおかずにご飯が進み、エネルギーチャージは万全!
食後は中庭を散歩したり、トラベルライブラリーでコーヒーなどを飲みながら、ゆっくり過ごしたり、もう一度温泉に浸かったり、思い思いのくつろぎタイムを。


蔵元が伝える酒造りの世界にどっぷりと浸る
2024年12月、日本の「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。酒造りは土地の気候や風土に応じた手法が伝承されており、また、酒は儀式や祭礼行事などといった文化や信仰にも深く関わっています。
そうした日本酒の奥深さを伝えたいという思いから、「界 玉造」では「蔵元が伝える酒造りの世界と日本酒の美味しい飲み方」と題した体験プログラムを展開(3月31日まで。参加費1人10,000円)。
酒造り最盛期の酒蔵を訪れ、代々継承してきた酒造りを蔵元から直接レクチャーしてもらえる貴重な機会です。訪れるのは、老舗酒蔵「酒持田(さけもちだ)本店」(出雲市)または「李白(りはく)酒造」(松江市)。今回は特別に、その両方を案内していただきました。


お酒の神様を祀る「佐香(さか)神社」のお膝元で明治10年に創業した「酒持田本店」。島根県産の酒米にこだわり、140年続く出雲杜氏としての技を継承している小さな酒蔵です。本プログラムでは、国の登録有形文化財に指定されている酒蔵を、蔵元の持田祐輔さんが案内。昔ながらの酒造りの工程を実際に見ることができます。
日によっては、麹や酒母(発酵の要となる酵母の培養液)、もろみなどが発酵している様子を直接見られるほか、お酒を混ぜる櫂入れ(かいいれ)などの体験ができることも。興味深かったのは、もろみを絞る装置「木槽(きぶね)」。一度に絞れる量が限られ時間もかかるため、現役で稼働しているものは全国的にも少なくなっているそう。
見学のあとの特別試飲は、同じ酒を温度違いや加水の有無で飲み比べ自分好みの味を探るなど、通常の試飲とはひと味違う面白さがありました。