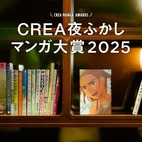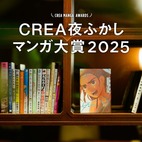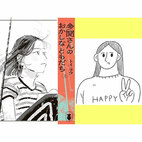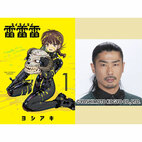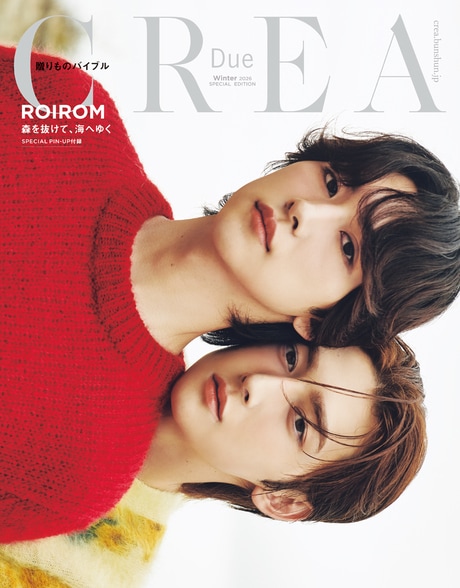手応えを感じた第4話
――「これを描きたかったんだ」という手応えを感じたのは?
藤見 第4話の日本人とフィリピン人のハーフの瑠詩愛(るしあ)の話ですね。これを描いている頃、移民の人への風当たりが強くなるのではないかと懸念される法律の改正案が通ってしまったりして、私も私と同じコミュニティの人たちも暗い気持ちになっていて。

そのときにネット上で善意の人たちが「外国人は生産性があって日本を支えてくれる」という擁護の仕方をしていることにモヤモヤしたんです。「役に立つ」じゃなくて「ただ幸せになる」みたいなことが描きたいと思ったんですよね。「だって私移民のガキじゃん そんなん人の100倍図々しくハッピーにならねえとじゃん」という瑠詩愛のセリフを当事者の方にすごく「よかった」と言ってもらうことは多いんです。みんなで絶対に幸せになろう、という気持ちでいます。
――作中にはハーフの仲間同士で本音を言い合う会のことも描かれています。藤見先生もこういう会をやっていますか?
藤見 そうですね。たまにこういうくだを巻く会をやってます(笑)。当事者同士だと話が早いこともあるけど、やっぱり個々に違うなと思うこともありますよ。
――取材をすることもありますか?
藤見 はい。身近な友達のほかに、SNSで知り合った人などにも。第5話は日本語を勉強する移民1.5世(外国で生まれ、幼少期に移住した人)の子どもたちの話ですが、実際に移民の子に日本語を教える教室に取材に行っています。先日は大阪の中学校にも行ってきました。そこは昔から中国出身の子を多く受け入れている学校で、常設の日本語教室があるんです。近隣の小学生も通ってくるからいろんな年齢の子がいて、親御さんも参加していたり。
ここの先生がカリスマみたいな方で……この人といっしょに活動したくてわざわざ他県から来ている先生もいるそうなんです。ハーフがテーマですけど、その周りの「関わりたい」という強い気持ちを持つ人のことも描きたくなるから、取材は本当にいい体験になります。担当さんも含めてですが、そういう人の気持ちに触れられるのはすごくありがたいです。取材させていただいて人の人生観に触れると、ちょっとした言葉の中にすごく本質的なことを発見できて、うれしい驚きがありますね。
- date
- writer
- staff
- 文=粟生こずえ
写真=平松市聖 - keyword