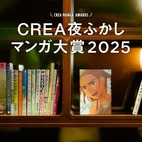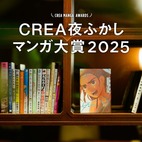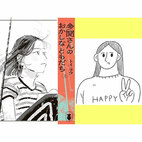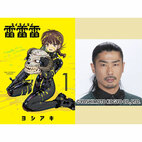――第2話で紗瑛子のルーツを知らずに中国人の悪口を言ってしまった女性・まりなが第3話では主人公になります。ハーフではない日本人が主人公の回を作ることは最初から構想にあったのでしょうか。
藤見 第2話を描いたあと、ひどいことを言ってしまった人を自然災害みたいな描き方をしてしまったなという反省があって。ただ加害して通り過ぎていく台風みたいにすませてはいけないなと。この話はすごく時間がかかりました。ネーム段階でセルフボツを重ねて。最初はまりなをもう少し傲慢で嫌な感じの人にしようと思ってたんですけど、結局「自分が人を傷つけていた」とあとで知ったらショックも受けるような、ふつうにいい人として描こうと。

――読む側としてはとても共感度が高いです。自分もこういうことを口走ってしまうかも、とドキッとします。
藤見 この話は感想を一番たくさんもらっているかもしれません。
「コーダ」の読者から共感の声が
――これに関連して違うマイノリティの話題が差し込まれていることで、より理解度が高まると思いました。感想の中で印象的だったことは?
藤見 コーダの方が「すごく共感した」と言ってくれたことです。「コーダ(CODA)」とは、「聞こえない/聞こえにくい親」のもとに生まれた「聞こえる子ども」です。その方も親の「通訳」を務めながら育っていて……ですが、親とは違う世界に住んでいる。この構造はハーフと似ているんですね。
『私だけ聴こえる』というコーダの若者たちを追ったドキュメンタリー映画があります。その中では、ろう者の世界にも、聴者の世界にも居場所を感じられない彼らの揺らぎが描かれていて、特に「自分はろう者でも聴者でもなくコーダなんだ」という台詞には、立場は違えど強く共感しました。
あとはアルビノや、クィアの方からも「共感した」と言ってもらえる機会がありました。マイノリティたちが同じ体験をしていると言うよりは、「普通」という強固な規範があって、その周縁にいる人たちには何か重なる部分があるのかもしれません。
――描きながら新たに知ることも多いのでしょうね。
藤見 そうなんです。時間をかけるほど考え方が変わったりふくらんだりして……。あとから読むと「もっとこうすればよかった」「これも描けばよかった」みたいな気持ちが無限にわいてくるから、早く続きを描かないとですね(笑)。
- date
- writer
- staff
- 文=粟生こずえ
写真=平松市聖 - keyword