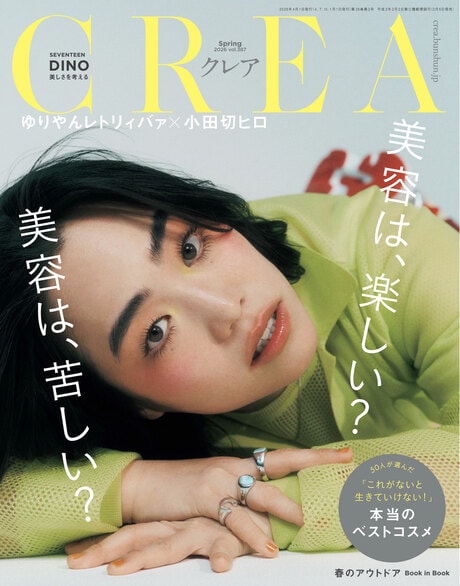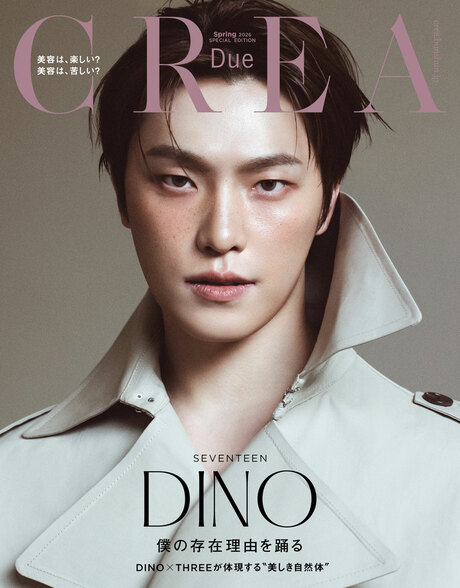灯台は今も、沖を行く船を照らしている

ここは、遠州灘に面していると同時に、天竜川の河口でもある。豊臣秀吉の時代から、山の上で伐り出された材木を筏にして川に流し、この掛塚湊から出荷していたという。
江戸に火事があれば、この土地の木挽きと廻船問屋が大いに儲かった……という話もあったらしい。
「丁度、江戸と大坂の中間の湊として、江戸時代には栄えていたそうですよ」
大正時代以降は、交易の港としての役割を終えているが、灯台は今も、沖を行く船を照らしているのだ。
灯室にあるレンズは、LEDのフレネルレンズ。動かずに、点滅して辺りを照らしている。

ふと灯室の天井を見上げてみる。
「あ、鉄板なんですね」
この灯台は、下部はコンクリートでできていて、上部は鉄製になっている。むき出しの鉄の天井が、何とも素朴な雰囲気を感じさせる。

「官営の灯台が出来たのは、一八九七年なんです」
明治三十年にこの灯台が完成。しかし、二〇〇二年になって海岸の浸食や、東海地震対策のため、現在の場所に移設されたのだという。
「ただ、この掛塚灯台は、官営ができる前に、私設の灯台があったんです」
その物語こそが、この掛塚灯台の面白さと言っても過言ではない。
「あの、改心灯台ですね」
そう。まずはその私設灯台のことを知るために、私たち一行はこの灯台に来る前に、磐田市歴史文書館を訪ねていた。