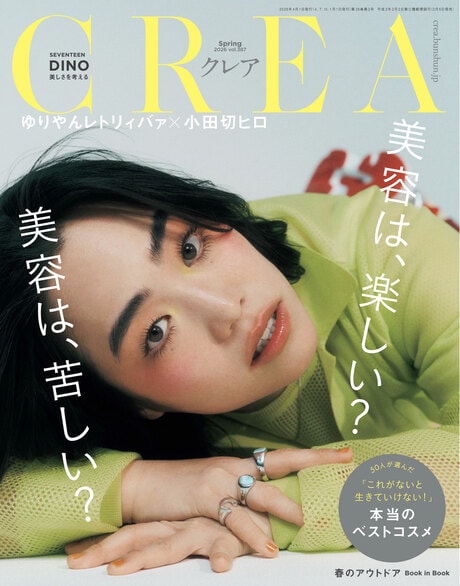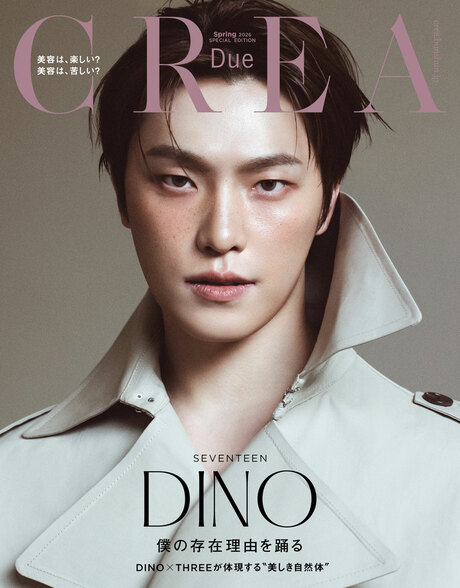興行収入21億円を突破、大ヒット中の映画『国宝』。任侠の一門に生まれた喜久雄(吉沢亮)の歌舞伎役者としての生き様を、歌舞伎界のプリンス・俊介(横浜流星)との関係を軸に描いた人間ドラマだ。上映時間が3時間近い大作にもかかわらず、公開とともに評判になり、ついに公開3週目にして週末映画動員ランキングでトップに立った。
なぜここまで『国宝』はヒットしているのか? その理由を映画に精通したライター西森路代さんが読み解きます(作品の一部ネタバレが含まれます)。

長崎で任侠の家に生まれた喜久雄
大ヒット公開中の『国宝』は、「視線」や「見る」「見られる」ということが印象に残る映画だと思った。主人公の喜久雄の背中に入っている入れ墨のミミズクが、ときおり観客をじっと凝視しているような目を向けることからしても、そのような視点で作られている部分はあるだろう。
喜久雄は、長崎の任侠の家に生まれ、上方歌舞伎の名門の当主・花井半二郎(渡辺謙)が家を訪れていた際に、父親(永瀬正敏)が抗争に巻き込まれ亡くなってしまう。
そのとき、父は戦う自分の背中を喜久雄にしっかり見届けるように告げる。喜久雄は、父の死の瞬間までを、瞬きもせずに見届けるのであった。もちろんそこに悲しみはあったのだろうが、その光景が強く心に焼き付いていたのではないだろうか。その日、長崎には珍しく雪が舞っていた。

父の死の直前、喜久雄が「積恋雪関扉」(通称「関の扉」)を演じていたのを見て魅了されていた半二郎は、身寄りのなくなった喜久雄を自分の元に呼び寄せ、同い年の息子・俊介と共に、歌舞伎役者になるための修行をさせることになる。「積恋雪関扉」は、雪景色にありながら桜が満開であるというシチュエーションの演目で、この映画を象徴するようであった。
文=西森路代