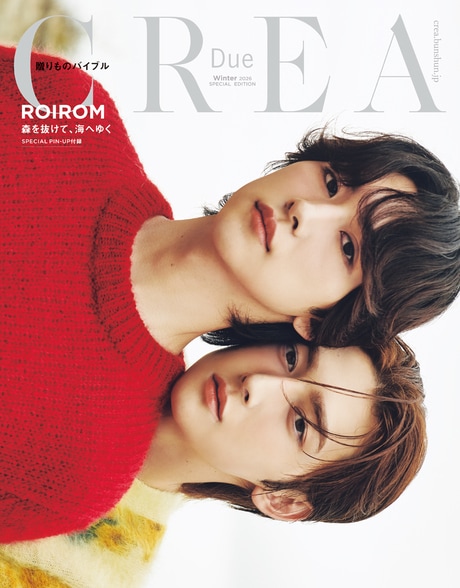第4章では、なぜ中国の不動産価格はこれまで長きにわたって上昇を続けてこられたのか、そのからくりを「合理的バブル」というキーワードによって解明する。その背景には社会保障全般、特に賦課方式の年金制度の不備がある。
後半となる第5章以降では、不動産価格の下落による社会の悲観ムードと、新興産業が台頭し、海外の市場を席巻するといういわばイケイケの状況が共存しているのはなぜか、という本書における核心的な「問い」に迫っていく。
まず第5章では、高口による中国現地取材、在日中国人へのヒヤリングを中心に、中国社会で高まる悲観論が個人と企業をどう変えたのかを見ていく。
第6章では、不動産危機と共に顕在化した、地方政府の財政難を取りあげる。現下の地方財政の苦境は、「中央と地方の綱引き関係」という中国経済が抱えるもう一つの難問の存在も浮き彫りにしている。
第7章では、新興産業の代表としてEV産業を取りあげ、産業政策ならびに「殺到する経済」をキーワードに、その台頭の背景と要因を探る。政府の補助金と、「殺到する経済」とも評される旺盛な市場競争がもたらした強大な供給能力は、一方でなかなか拡大しない国内消費という需要サイドの課題をも浮き彫りにした。
最終章である第8章では、「供給能力が過剰で、消費需要が不足している」という中国経済の根本的な課題に注目し、本書で論じてきた新興産業の台頭という「光の部分」と、不動産不況がもたらした経済低迷という「影の部分」をつなげる議論を行う。
本書の執筆中、2024年11月5日に行われた米大統領選挙では、共和党候補のトランプが民主党候補のハリスに圧勝し、政権発足とともに大幅な関税の引き上げが行われるとの憶測を呼んでいる。このことは、高成長が続いた時代が終わりを告げ、将来像が不透明になっている中国経済の不確実性をますます高めるだろう。
しかし、たとえそうなったとしても、本書で論じた中国経済の構造は短期的には変化しないと見ている。「殺到する経済」という言葉で表現される、製造業における柔軟さと圧倒的なコスト削減能力という“強み”、その強い製造業の供給能力を吸収するだけの国内需要の広がりを欠きがちという最大の“弱み”は今後も継続していくだろう。
その意味では、本書は中国経済のピークアウトという時事的な関心に応えたものでありながら、より射程の長い議論として展開した。その課題をクリアできているかどうかは、読者の判断にゆだねたい。
「まえがき」より

ピークアウトする中国 「殺到する経済」と「合理的バブル」の限界
定価 1,210円(税込)
文藝春秋
» この書籍を購入する(Amazonへリンク
- date
- writer
- category