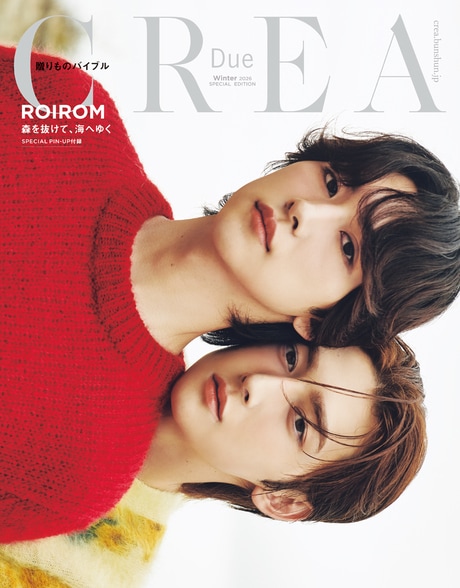なぜなら、これら二つの問題はいずれも「供給能力が過剰で、消費需要が不足しがちである」という中国経済の宿痾とも言うべき性質に起因しており、それが異なる形で顕在化したものにほかならないからだ。「光」と「影」は同じ問題から発しているのだ。
不動産価格の低下から生じた経済不振によってピークアウトを迎えた中国経済には、これまでにない、大きな不確実性が生じている。そのことが冒頭に述べた社会の閉塞感を生んでいるのも事実だ。しかし、影の部分が拡大しているからと言って、光の部分に全く目を向けなければ、やはり問題の本質を見誤るだろう。
中国経済は過去20年にわたり世界経済を牽引する存在であった。とりわけ日本経済にとって、中国は製造拠点としても市場としてもきわめて重要な存在であった。その中国がどのような岐路にさしかかっているのか、今何が起きているのか、そしてどのような未来へと向かうのかを知ることはきわめて重要だ。表面的なトピックではなく、複雑でわかりにくい話であっても、現在の混乱をもたらしている本質的な問題とは何かを、論理的な整合性をもって理解することは不可欠だ。それが、私たちが本書を執筆する上で何よりも重要視したことである。
本書の構成
以下、本書の構成を簡単に説明しよう。
本書前半の第1章から第4章では中国の不動産市場の危機を取りあげている。
まず、第1章では、中国不動産市場で何が起こっているのか、著者の一人である高口が行った現地取材を中心として現状を描いていく。
第2章では、コロナ禍以降の中国のマクロ経済政策を取りあげる。新型コロナウイルスの流行に伴う金融政策は、きわめて迅速かつ大胆だった一方、財政の拡大は限定的で、他国と比べても小規模だった。そのことはその後の不動産不況に直結する。
第3章では2010年代にブームを迎えた、都市開発と不動産リスクとの関係について取りあげる。当時の都市開発は先進地域の沿海部から遅れた内陸部に主要な舞台が移ったが、そのことがその後の不動産市場の歪みにつながっていく。
- date
- writer
- category