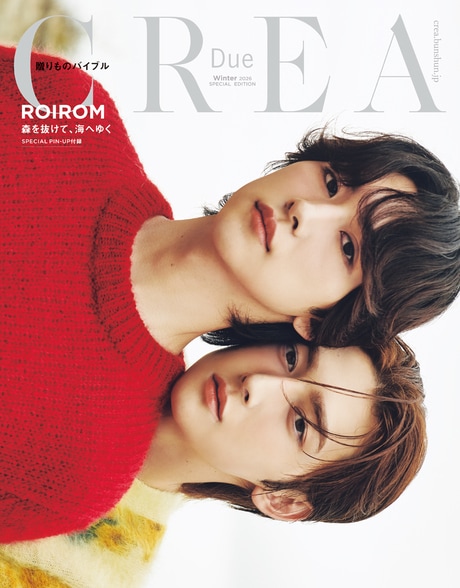裏返せば、2024年における中国経済の状況はそれほどまでに深刻だと言える。これまでにも多くの社会問題はあったものの、高成長を続ける経済が不満や閉塞感の拡大を押し止める防波堤となっていた。それが、中国経済の低迷、特に本書でも詳しく論じる不動産価格の低迷によって、いびつな形で顕在化してきている。無差別殺傷事件に象徴される社会の閉塞感は、とりあえずはこういった文脈で理解できるだろう。
不動産危機とEV急成長はコインの裏表
ただ、中国経済の理解は一筋縄ではいかない。マクロの経済状況にだけ注目すると悪化ばかりが目につくが、別の面に目を向けると一部の新興産業の快進撃という明るいニュースもある。特に電気自動車(EV)、太陽光パネル、リチウムイオン電池は「新三様(新三大輸出製品)」と呼ばれ、ヨーロッパをはじめとして世界の市場を席巻しつつある。脱炭素に不可欠な次世代の産業で、中国企業、特に大手EVメーカーのBYD(比亜迪股份有限公司)をはじめとするリーディングカンパニーは圧倒的なまでの競争力、先進国の企業がまともに戦っても太刀打ちできない実力を身につけた。欧米諸国は警戒を強め、関税の引き上げなどの対抗策を打ち出しているが、中国側はそんな批判はどこ吹く風といったおもむきで、新興国をはじめとした海外への製造拠点の移転を積極的に進めている。
マクロ経済の低迷、それに由来する社会全体の閉塞感と、それをものともしないような一部の民間企業の躍進が共存している。中国経済の現状は暗いのか、明るいのか。どこに目を向けるかで見える景色がまったく違うのが、現在の中国経済の本質であり、それだけにその実像は一般にはなかなか理解されない。
中国経済に関する書籍はしばしば、楽観論もしくは悲観論、どちらかに大きく偏りがちである。そうした中で本書の特徴は、不動産市場の低迷による需要の落ち込みと、EVをはじめとする新興産業の快進撃と生産能力過剰という二つの異なる問題を、中国経済が抱えている課題のいわばコインの裏と表としてとらえる点にある。
- date
- writer
- category