スパルタ教育の元祖
古代ギリシア史に関心を持たない人でも「スパルタ教育」という言葉を聞いたことはあるだろう。スポーツや受験、あるいは技術獲得のためにハードで、時には体罰を伴い互いに競争させて徹底的な指導のもと行われる教育だと、一般的に理解されている。ではなぜそうよぶのかを問われたならば、かつて学んだ世界史のおぼろげな記憶をたぐり寄せて、その昔スパルタという国でなされた教育に由来する、と答えられる人はいるかもしれないが、その時代や場所、その内容まで正確に知っていることは稀ではないか。
この「スパルタ教育」という言葉を生み出した、スパルタというコミュニティが本書のテーマとなる。スパルタはポリスとよばれた約千の独立した政治体が群立していた、今から二千年以上前の古代ギリシア世界において、アテナイ(本書では古代ギリシアのポリスをアテナイ、現代の都市名はアテネと表記する)とともに長期にわたり指導的な地位を占めたポリスである。なぜスパルタは強国として君臨することが可能であったのか、それを支えた社会とはいかなるもので、元祖「スパルタ教育」はなぜ必要であったのかを、本書ではさまざまなエピソードを交えて説明してみたい。
スパルタは、古代ギリシアを代表する哲学者プラトンが「その体制はまるで兵営におけるもののようだ」と述べたように、強健な兵士を生み出すために社会全体がポリスの厳格な統制下に置かれている、というイメージが同時代から強かった。このような社会に対して批判的な意見もあったが、第七章で述べるように、紀元前五世紀末以降、熱烈な支持者が後を絶たず、理想の社会として高い評価を受けた。そしてこれがその後、西洋世界では一貫したイメージとなり、現代まで賛美者を生み出している。その意味では「スパルタ」はある種のブランドと化したのである。
同じくプラトンが当時(前四世紀)の世界について、「平和とよぶものは名目に過ぎない」と述べており、戦争が常態であった世界において軍事的な優位は重要であった。それが教育や社会により軍事強国となったスパルタの高い評価につながっていたとも考えられる。そこで馴染みのない人も多いであろうから、まず特に軍事や国際関係の面を中心に、古代ギリシア世界におけるスパルタの歴史を簡単に説明してみよう。
ギリシア世界におけるスパルタ
西洋文明の源流と見なされてきた古代ギリシア世界は、今から二八〇〇年以上前の前九世紀にはエーゲ海を中核とする地域に姿を現し、最終的にローマの属州となる前二世紀後半まで活発な活動が知られる。この世界は強力な専制君主制が生まれず、数百から二、三千人の男性成人市民を構成員とするポリスが林立していた。ポリスは市民がその政策などを合議で決め、戦争の際には市民自らが武器を執って戦う社会であった。
これらのポリスのなかでスパルタ人たちは、山がちなギリシアでは珍しい肥沃な平野を擁するラコニア地方に居を構えた。前八世紀より周囲への拡大を始め、ラコニア地方全域を掌握すると、前七世紀末までには西隣の同じく肥沃なメッセニア地方を二度にわたる戦いで征服し、ギリシアのポリスでは群を抜いた領土を得ることになり、さらにその勢力は増大した。
前六世紀半ばにいわゆる「リュクルゴスの改革」と称される、一連の国制や社会の改革を断行して国内の安定を得ると、それまで劣勢であった北隣のテゲア、東で国境を接するアルゴスにも優位を得て、ペロポネソス半島の最大勢力となる。そして前六世紀の後半にはこの半島の多くのポリスと、ギリシア史上初めての攻守同盟であるペロポネソス同盟を結成して盟主となり、ギリシア世界以外にも広くその勢威が轟くこととなった。
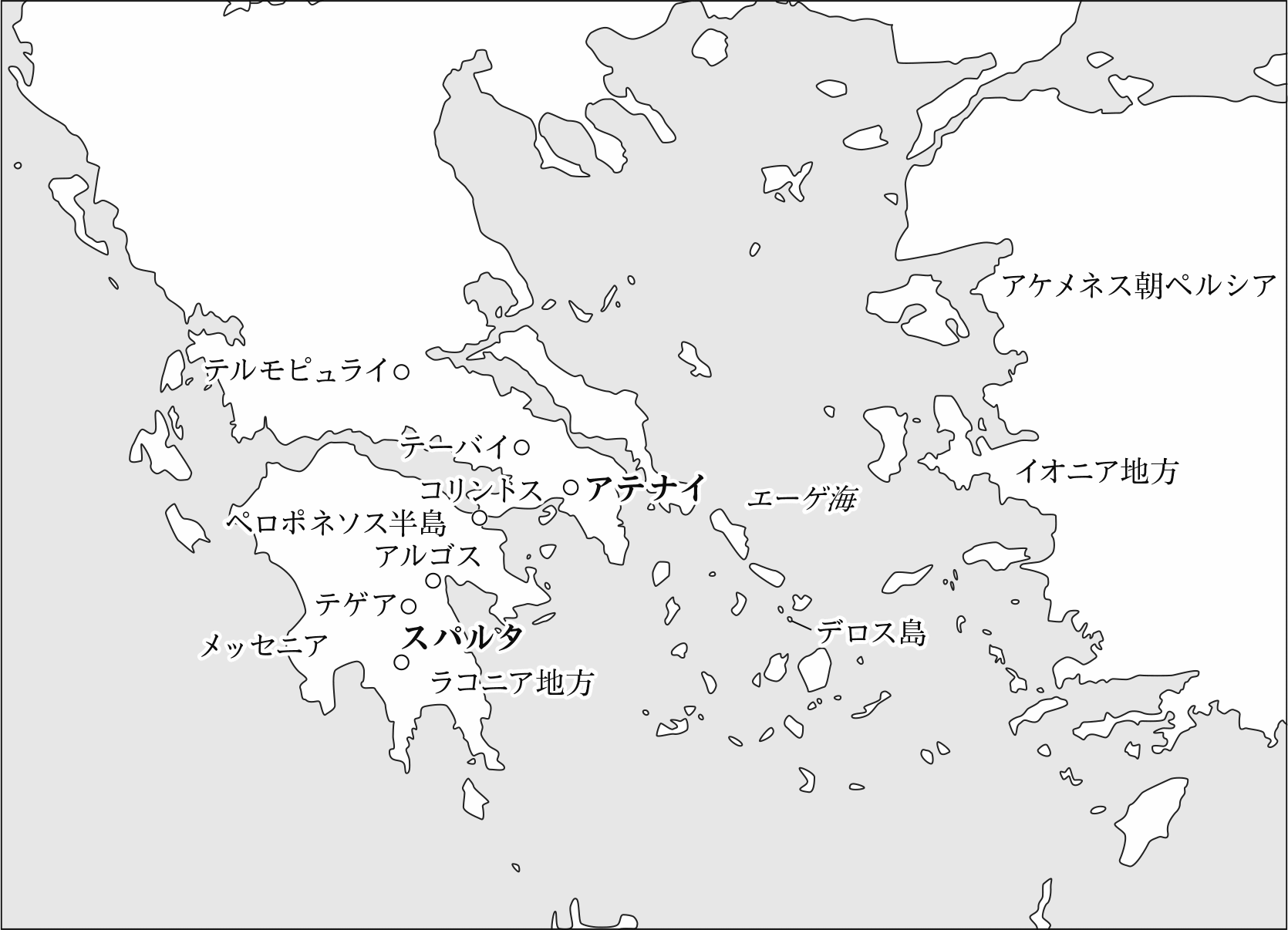
そしてその名を高めたのがペルシア戦争である。第一章で詳しく述べるが、前五世紀初めに、オリエント世界で大帝国を築いたアケメネス朝ペルシアがギリシアに侵攻した。一回目の戦いはアテナイが撃退したが、その数倍で来寇した二度目の戦いでは、スパルタがギリシア連合軍の総大将を務めてペルシアに対する勝利に大きく貢献した。
しかし戦後に同じく勝利に貢献したアテナイが、エーゲ海沿岸部や島嶼のポリスと海軍を主体とするデロス同盟を結成して、スパルタの強力な対抗勢力となった。そして前四三〇年代末にスパルタ率いるペロポネソス同盟とアテナイ率いるデロス同盟が、ペロポネソス戦争とよばれるギリシア全土を巻き込む全面戦争に突入した。スパルタは中断を挟みながら三〇年近く続いたこの戦争に勝利し、名実ともにギリシアの覇者の地位を得たのである。
さらに前四世紀に入ると、ペルシアの支援を受けたコリントス、テーバイやアテナイなどとのコリントス戦争に突入した。しかし最終的にペルシアと和解して、その王を後ろ盾として、ギリシアでの覇者の地位は維持した。その後も他のポリスとの抗争が絶えず、前三七一年に当時、勢力を拡大した仇敵のテーバイに大敗を喫して覇権を喪失すると、国力を支えていた肥沃なメッセニアも独立したため、かつての勢威を取り戻すことは困難になるが、その軍事強国の記憶はその後も絶えることはなかったのである。
軍事強国を支えた戦士教育
このようにスパルタは遅くとも前四世紀前半まで、ギリシア随一の軍事大国として君臨しており、その名声は外国にまで及んだ。その強さの理由として注目されたのが、産まれた時から(あるいは産む前から)始まる、屈強な兵士を社会が造り上げるシステム、すなわち「元祖」スパルタ教育なのである。往時の勢力を取り戻すことをめざして前三世紀に大胆な社会改革を実行した際も、その中心となったのが、かつての教育と生活態度の復活であった。ではその教育とはいかなるものであったのだろう。
詳細は第二章で述べるので、ここでは簡単にその特徴のみを説明しよう。注目すべき点は、他のポリスでは教育が個人的になされていたのに対して、スパルタでは公的な形で義務として実施されたことであろう。そして教育を受けることは市民資格を得るために必要とされた。さらに親は子どもの成長への関わりを制限された。出産後に新生児は将来、優れた兵士になるか、そのような子を産めるかについて年長者たちによる身体審査があり、それに通らないと山から崖下に棄てられたとの伝承すらある。
七歳になると本格的な公教育が始まり集団生活に入った。二〇歳で成人しても集団生活は続き、三〇歳になってようやくその生活から解放されたのであった。この間、厳しい肉体的な鍛錬などが競争を通して徹底された。この教育を統括する役人、その補助者も存在した。二〇歳になると優秀とされた者は、騎兵隊とよばれた王の親衛隊に選抜された。この部隊は二〇歳から三〇歳の若者三〇〇名で構成され、選抜は毎年、各年齢で改めてなされたので、競争は三〇歳まで続くことになる。
一方で二〇歳の時に六〇歳まで続くことになる、毎日の晩餐をともにする共同食事仲間への加入を果たす必要があった。入るためには一五から二〇名程度で構成されるそのメンバーによる審査があり、その際には教育での成果が重視された。これは現在の就職試験に近いものであった。なぜならこの共同食事への参加が市民資格要件であったからである。どこの共同食事仲間からも入会を拒否されて参加できないと市民として認められなかった。
ギリシア世界の軍隊は、市民が自ら武器を執って戦う民兵から構成され、彼らは普段、農業などの生業に勤しむアマチュアであった。しかしスパルタの場合、この長年にわたる苛酷な集団生活により、強健な肉体やしたたかさ、臨機応変な対応力、団結心、服従、愛国心、そして知性が培われていた。さらに市民は所有地で労働に従事する隷属農民から生産物を得られたので、生業に就くのを禁じられており、成人後も軍事教練などを日課とした戦闘の専門家集団だった。
ある伝えによれば成人後も定期的に身体検査があり、肌が白く肥満していると訓練を怠っていると見なされ、罰則として鞭打ちに遭ったという。このように幼少から徹底した訓練を受け、成人後も軍事訓練に明け暮れたプロの兵士から成るポリスゆえに、強国としての名を轟かしたと認識されてきたのである。
後世の評判
この教育についての風評はすでにペロポネソス戦争中にアテナイの指導者、ペリクレスにより戦没者追悼演説のなかで取り上げられ、その後もローマ期まで多く言及されている。仕上げの儀式には多くの観衆を集め、形を変えながらも存続したその儀式を、ローマ支配下のスパルタで目撃した人の記録もある。
スパルタ認識の後世への伝承は第七章で詳しく扱うが、近代に入ると西洋世界では軍事的な側面よりは、その社会の特徴とされた愛国心、集団への帰属意識、そして心身の鍛錬といった面に注目が集まるようになった。そのためハリー=ポッターの世界で描かれるように、教育においても座学だけではなく身体訓練をして行うチーム同士の対抗戦なども重視され、団結心や愛校心を育み規律を遵守することが奨励された。
例えばラグビー発祥の地であるイギリスのパブリック・スクール、ラグビー校の校長トーマス=アーノルドが推進した教育は、スパルタの心身とも厳格に鍛えるものと類似していることが指摘されている。さらにスパルタの熱心な賛美者であったナチス・ドイツにより設置された、アドルフ=ヒトラー・シューレ(シューレはドイツ語で学校の意)はその極端な事例であり、古代スパルタでなされた教育内容をモデルとするカリキュラムが多くを占めた。
ナチスの悪夢から第二次世界大戦後は表立って賛美する風潮は影を潜めたが、日本では「スパルタ教育」の言葉で表現される訓練が、軍隊などを中心に世界中で今もなお続いていることは否定できない。
日本における「スパルタ教育」
ところが意外なことに、英語のSpartan educationには「体罰を含む厳格な教育」という意味はない。単純にスパルタでなされる教育を指す言葉として使われているのである。では我々にとって馴染みのある「スパルタ教育」という語はいつから定着したのであろうか。
教育学者の鈴木円氏の研究によれば、日本ではスパルタは明治初期に認知され、今日的な意味でのスパルタ教育なる言葉は第二次世界大戦前から存在したが、この語が広まったのは一九六九年に出版された石原慎太郎氏の著書、『スパルタ教育』によるところが大きかったとのことである。
石原氏は父の権威が著しく低下したことを嘆き、戦前の体罰を容認する厳格な教育の復活を唱えて、この本は当時七〇万部のベストセラーとなった。しかしスパルタにおける教育を扱ったものではなく、スパルタへの言及もない。ところが教育学者たちからその内容への大きな反発を招いて、活発な議論が展開されたことから、スパルタとは関係なく広く我が国で「スパルタ教育」なる語が用いられるようになったという。
このように考えれば、我が国で「スパルタ教育」という語の普及に比べて、古代スパルタについての理解がほとんどないことは納得のいくものである。
見直しが進む「スパルタ像」
軍事強国を支えるものとして「教育」があり、スパルタはそれを受けてきた人々から成る社会だと見なされてきた。ところが近年のスパルタ研究では、そのような単純な見方への疑義が陸続と提出されるようになっている。これはポスト・モダニズム、オリエンタリズム、マルチカルチュラリズム(多文化主義)、言語論的転回など、世界認識の転換を促す動き(パラダイム・シフト)により引き起こされたと言えるであろう。
そこで教育の現実、その目的、そしてなぜスパルタがこのような体制を敷いて社会の形成に努めたのかについて、この新たな動きと連動して盛んに議論されるようになった。その動きの中心にあるのが、古代の人々が伝えるスパルタ像の見直しである。それを少し紹介して、これらの動向を踏まえたうえで本書の目的を説明しよう。
古代ギリシアに関する情報は、悲喜劇、歴史叙述、哲学、美術作品などを生み出し、民主主義の源流とされるアテナイについてのものが大半を占めることから、ギリシアのイメージを構成するものの大部分がアテナイを念頭においたものであった。
しかし近年、世界の歴史がヨーロッパの展開を基準に語られてきたと批判されるようになったことに刺激され、アテナイ=ギリシアとする古代ギリシア理解の再検討が叫ばれるようになると、スパルタはギリシア(=アテナイ)的スタンダードの対極として新たなギリシア像構築にとっての重要なケースとなる。
しかしスパルタに関する情報は、数は多いものの謎が多く、おまけに彼ら自身が書き残したものはほぼ皆無に近い状態である。それゆえ現実のスパルタ社会の内情を正確に伝える情報が少ないため、かつてある高名なイギリスの古代史研究者が、「スパルタに関する本は大きなクエスチョンマークのみを記した一頁の本となる」と述べたように、その実情解明は困難であると思われていた。加えていくら史料を精査しても、スパルタ自身のプロパガンダや執筆者自らの理想を、この社会に投影する傾向が多大に見られることが、近年とみに指摘されるようになっている。
そこで最近の研究は、文献史料の実証を中心とした伝統的な考察手法から離れて、文学理論、文化人類学や民俗学、あるいは社会学など他の学問分野の手法を援用して文献史料の読み直しを行う一方で、新たな手法を駆使した考古学の成果をもとにその社会の考察が進められている。このアプローチにより先入観を乗り越える可能性が開け、スパルタの現実を理解する動きが高まった。本書でもその成果を取り入れて、従来の認識を再検討する。
一方で教育により培われる愛国心、あるいは公的な部分を重視し、私生活に干渉するというスパルタ社会についての認識は、近代以降のナショナリズムなどの国民国家の枠組みでなされており、そこに当時の現実よりも近代以降の社会が投影されているのではないか、という批判も出ている。この批判に応えるためには西洋文明の伝統により生じ、広く流布している世界観、価値観などをまず取り去る必要があり、この作業を通じて逆に西洋的な近代国民国家のあり方を相対化する材料を提供しうるとも考えられる。
大きく分けてこの二つの動向が古代スパルタ史研究を推進する原動力となり、一九八〇年代以降、古代ギリシア史研究の分野で最も多く取り上げられているテーマの一つになっているが、我が国では広く一般の人々を対象にその動きは紹介されていない。
本書のめざすもの
そこで本書ではスパルタの現実とともに従来のイメージや評価を取り上げる方法により、当時のギリシア社会、さらには後世の西洋世界にまで視野を広げて、何が特異であり、なぜそのように考えられたのかを分析することで、ひるがえって我々が有する価値判断の基準を再認識してみたい。なぜならこれらの様相には現代の世界が抱える様々な問題を、改めて考えさせる要素を多く見ることができるからである。
例えばコミュニティに対する滅私奉公を強調し、軍事的な面に高い価値をおくと見なされてきたスパルタ人の価値観は、先の大戦におけるファシズム体制や現在でも存在する独裁体制を想起させるはずである。そのため近年その数が増えている、個人の自由を統制する強権体制の国について考えるヒントを提供するにちがいない。また民主主義の社会において、個人の幸福や希望のみが優先されることに懸念が示される現状との対比も興味深い。
さらに自分たちを「同等者(ホモイオイ)」とよび、格差のない平等な経済基盤を有することで市民団の団結を図ろうとしたスパルタは、結局この均衡が破れたことにより衰退へと至ったと認識されている。かつては一億総中流と言われながら、経済格差が問題とされ、低所得者層への注目が高まっている現代の日本社会にとって、一つのモデルケースを提供するのではないか。
スパルタにおける経済格差の拡大に女性が大きく関与したと考えられており、その物欲や性的奔放が当時から非難されてきた。これらの認識もジェンダー的な視点から再考が進められており、現代の女性のイメージとの対比も関心を喚起するのではないか。そして、衰退の要因の一つとして大きく取り上げられてきたのが市民数の減少であり、今日の日本において少子化による人口減少が社会問題となっていることを考慮するならば、この問題も看過できない。
「トゥキュディデスの罠」
スパルタはギリシア世界における大国としてアテナイとしのぎを削り、両者とも同盟国を率い、最終的には全面戦争に突入した。この時代の国際関係は、国際関係論的には弱肉強食の統制なき世界と見なされ、軍事力の維持はすべてのポリスにとって独立を維持するためには不可欠であった。
このあからさまなパワーポリティックスの世界で、覇権国にとって同盟国を敵側に奪われることは死活問題であり、それを阻止することが対外的な動きを決める重要な要因であった。アテナイ人トゥキュディデスは、現実主義の観点から自らが将軍として従軍したペロポネソス戦争について詳述しているが、そこでこの戦争は、スパルタがアテナイの台頭による覇権の揺らぎ、そしてアテナイ側への同盟国の離脱を恐れて開戦に踏み切ったと見なした。これを現代の国際関係論の研究者は「トゥキュディデスの罠」とよぶが、まさに中国の台頭に対するアメリカの動き、あるいはウクライナとロシアの関係を想起させるものである。このような国際状況を考慮して、スパルタが教育や生活において、強国を維持していくためにいかなる工夫をしたのかも考える必要があろう。
本書では以上のような現代社会を想起させる点を考慮して、日本ではほとんど紹介されていないスパルタとそれを取り巻く世界を説明する。そして現代の社会を改めて考え直すヒントを提供したいと考えている。さらに滅亡後、後世の人々にとって絶えることなく自分の社会の理想やアンチテーゼと見なされた、スパルタ社会のイメージの変遷は、現代にいたる西洋世界の展開を理解するために興味深い材料を提供するので触れてみよう。そして最後に改めてスパルタが現在の社会に提起することを取り上げる。
「はじめに スパルタ教育の元祖」より

スパルタ 古代ギリシアの神話と実像(文春新書 1469)
定価 1,375円(税込)
文藝春秋
» この書籍を購入する(Amazonへリンク)





























