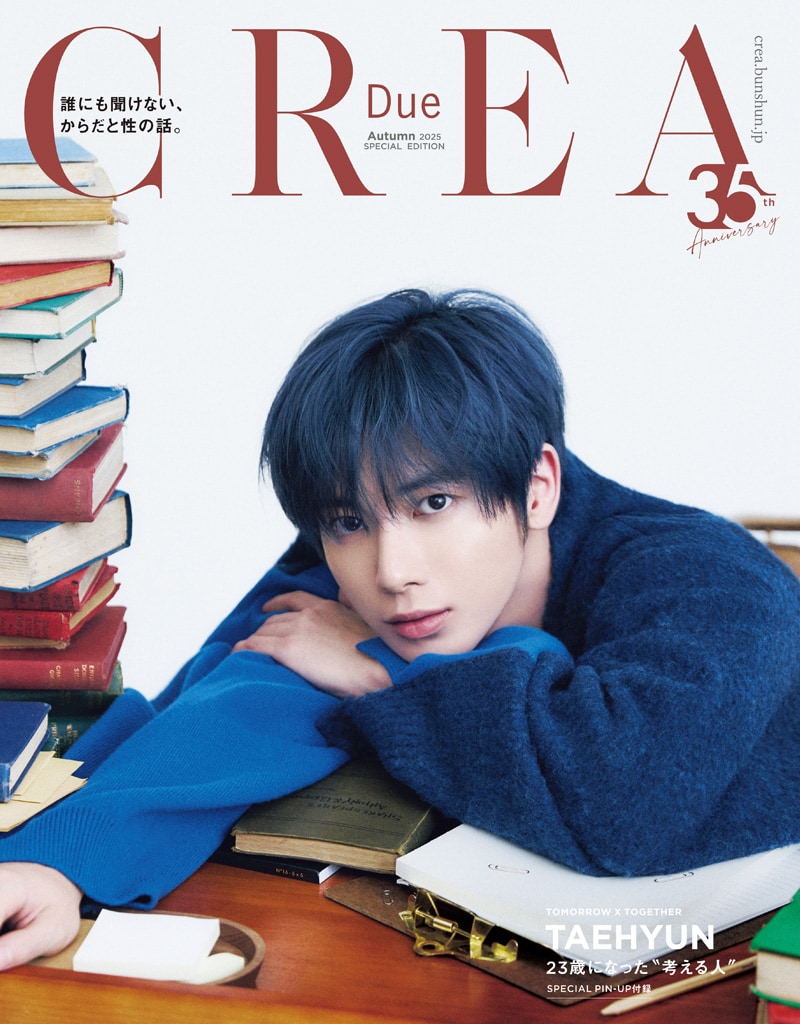ゆっくり休めばまた元の彼女に戻れるはず──きっと。
「そうなの? ごめんなさい、奈緒さん。でもね、わたしもずっと探していたのよ」
柔らかく紡がれたその返事に、奈緒は戸惑った。
「探していた……? 出口を?」
「いやね奈緒さん、違うわよ。魔物を探していたの」
「え?」
聞き間違いだと思った。あるいは、似た言葉の何かだと。まもの……まものって?
魔物を探していた?
「あやしの森に棲みついているという魔物よ。奈緒さんにも話したじゃない、忘れたの? わたし、その魔物を探していたの。お願いごとをするために」
「お、お願いごと?」
奈緒の困惑は大きくなる一方だ。雪乃はさっきから一体何を言っているのだろう。
ふふふ、と雪乃が笑う。いや──唇の両端を吊り上げて三日月のような形にし、冷え冷えとした光を放つ瞳を細めているそれを、「笑う」とは言わない。
嗤っている。
「両親と婚約者を食べてくださいって」
夢見る少女のように軽やかに願いを口にする雪乃に、奈緒は慄然とした。
「な……何を言っているの、雪乃さん」
これはいつもの雪乃ではない。しかし、雪乃本人であることは間違いない。彼女を無理にでも引っ張っていけばいいのか、それともできるだけ刺激しないほうがいいのか、奈緒には判断できなかった。
「ねえ、どうやって食べてもらうのがいいと思う? ばりばりと頭から噛み砕く? それとも腕を引き千切る? ああ、いいえ、まずは足からよね、逃げられてしまわないように。どれだけ血が噴き出るかしら。あんな人たちでも、その血は赤いのかしら。肉は美味しいのかしらね? 婚約者は硬そうだし、お母さまは萎びているし、お父さまはブヨブヨで脂身が多そうだわ」
ぞっとするようなことを楽しげに話し、あははは! と笑い声を上げる。喉を仰け反らせ、大きく口を開けて。
その顔に、淑やかで大人しい娘の面影はなかった。
「ゆ、雪乃さん、落ち着いて。聞いたわ、お父さまと何か諍いがあったのですってね。お家に帰って、もう一度ゆっくり話し合いをすれば……」
- date
- writer
- category