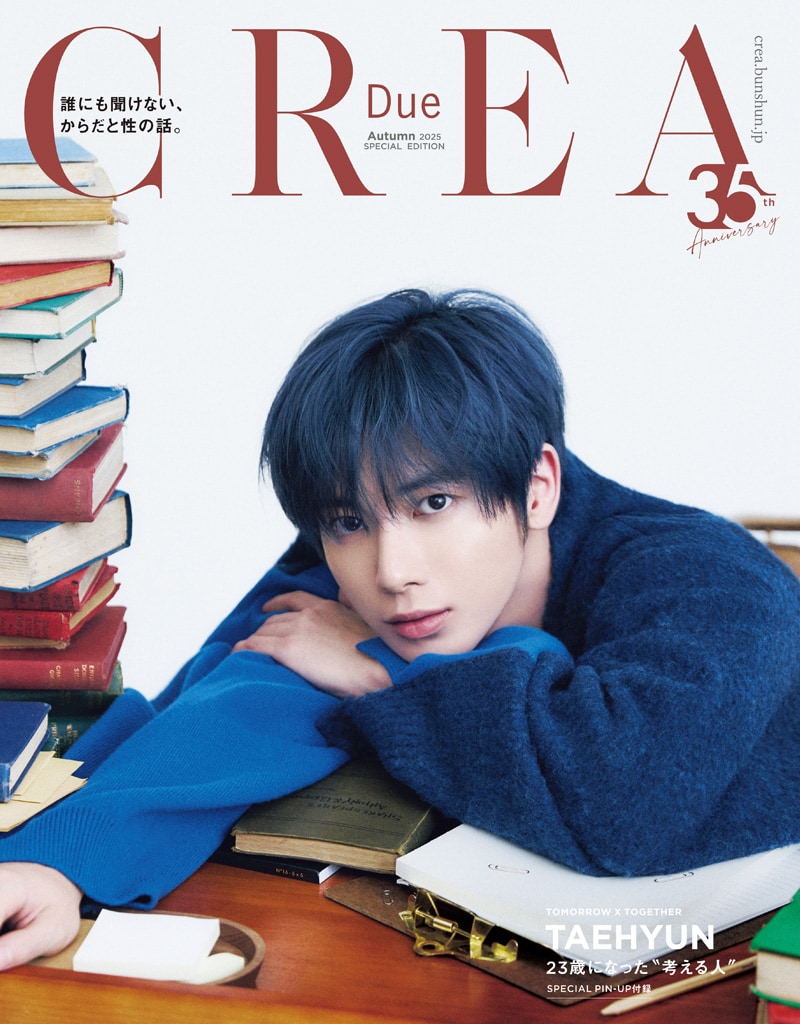「ゆ、雪乃……さ、ん……?」
疑問形になったのは、そこにいる娘の姿が、奈緒の頭の中の像と重ならなかったためだ。
薄暗い森の中で、雪乃は上から降り注ぐ金色の光を浴びて、きらきらと輝いているように見えた。
全身の輪郭がぼんやりと浮き上がり、まるで彼女自身が淡く発光しているかのようだ。それは神秘的な眺めではあるけれど、神々しく美しいというよりは、どこか不気味で、禍々しく恐ろしいもののように感じられた。
どれだけ歩き回ったのか、彼女は草履も履いていない。白かっただろう足袋は真っ黒に汚れ、着物の裾も泥と草の汁に染まっている。枝に引っかけたらしく袖が破れ、いつもきちんと整えられていた三つ編みは見る影もなく解けて乱れていた。
そんな痛々しい恰好なのに、雪乃は微笑んでいる。いや……たぶん、微笑んでいる、のだろう。こちらを向く彼女の顔には影が落ちて、はっきりとは見えない。
葉の間から漏れる夕日の輝きを全身にまとわせていてもなお、なぜか雪乃の顔だけは黒く塗られているかのようだった。
ぞくりとした。
誰そ彼──逢魔が時に出会う、あれは誰?
そこにいるのは、果たして人か、あるいは魔性のものか。
「まあ、奈緒さん」
雪乃は奈緒を認めて、優しげな声を出した。
耳で聞くだけなら、いつもの彼女の声と口調そのものだ。しかし奈緒はその事実にかえって背筋が寒くなった。そんな声、そんな言い方は、普通この状況下では決して出されるはずのないものだ。
奈緒は両手を組み、ぐっと強く握り合わせた。
「ゆ……雪乃さん」
怯えるウサギに対する時のように、そろりと小さく呼びかける。強引に唇を笑みの形にして、可能な限り普段と同じ顔を保つよう努力した。
「捜していたのよ。さあ、こんなところは早く出て、お家に帰りましょう。ご両親も心配なさっていたわ」
どう見ても、雪乃の状態は正常とは言い難い。何があったのか……いや、何もなくとも、雪乃のような娘にとって、外で夜を明かすなんて耐えられないくらいの恐怖と苦痛があったのだろうと想像できる。
- date
- writer
- category