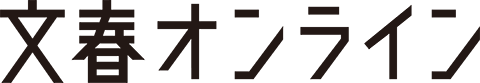書かざるを得なかった、女性が働くということ
――この小説では、当時の女性編集者たちが直面した困難や、働くことの葛藤が切実に描かれています。これは当初からテーマとして意識されていたのでしょうか。
大島:いえ、それはまったく思っていませんでした。でも、取材を進めていくうちに、どうしてもそこは書かなければならない、書かざるを得ない、という気持ちになっていきました。同じ少女漫画雑誌の編集部にいながら、漫画連載の担当をすることが叶わなかった、女性の編集者の方からうかがうお話は、本当に「当時はこんなふうだったの……!?」ということばかりで。
もちろん、男性編集者たちに決して悪意があったわけではなく、時代の流れの中では、ごく普通のこととして、女性が働く場所としてはむしろマシな方くらいの感覚だったと思います。その現実が、少女たちの夢を作る「少女漫画の編集部」で起きていたということが、すごく象徴的――これはもう、書かなければならないというより、ごく自然に「書くべきもの」としてそこにあったという感じでした。
――高校時代にデビューして瞬く間に売れっ子になった、美内すずえ先生に象徴されるように、少女が少女たちのために漫画を描きはじめた、まさに新しいメディアが生まれた時代ですよね。
大島:そうなんです。それまでは手塚治虫先生や赤塚不二夫先生のような男性漫画家が、少女漫画を描くことが多かったですし、純粋に少女が少女のために描きはじめたのは、作中にも出てくる漫画スクールがはじまった頃だと思います。この漫画スクールも小長井編集長が立ち上げたものです。

――なぜ漫画家ではなく、編集部を舞台に選んだのでしょうか。
大島:少年漫画雑誌が舞台になったものはありますが、なぜか少女漫画の編集部を舞台にした作品は意外にないんですよね。私自身、子どもの頃から雑誌の奥付を見て「どこの本だろう」と版元が気になるような子どもで、「どんな人が作っているんだろう」って、編集者の方が書いているコラムを読むのがすごく好きだったんです。長い間、誰か書いてくれないかなと思っていたけれど、誰も書いてくれないから、じゃあ自分で書こう、と。だから最初から、漫画家ではなく編集部を書きたいと思っていました。
――ご自身にとって最長の大作になったそうですが、書き終えてみていかがですか。
大島:もう、こんなに長いのを書くことは絶対にないです。疲れますから(笑)。ゲラのチェックも本当に大変で。連載が終わって単行本にする時、自分でかなり削ったつもりだったんです。体感では100枚くらい減らした気分でいたら、編集者さんに「23枚しか減ってないですよ」と言われて、衝撃を受けました。
最後の1行に至るまでの過程が長かったので、書き終えるまではとにかく健康でいなければ、とずっと思っていました。本当に、果てしない長い旅でしたが、最後の方は本当に楽しくて、なんだか、丸いものの中に入っていくような、不思議な集中を経験しました。これも初めての体験でしたね。今へと続いている「あの頃」の物語が、ぜひ多くの方に届けばと願っています。

うまれたての星
定価 2,750円(税込)
集英社
» この書籍を購入する(Amazonへリンク)