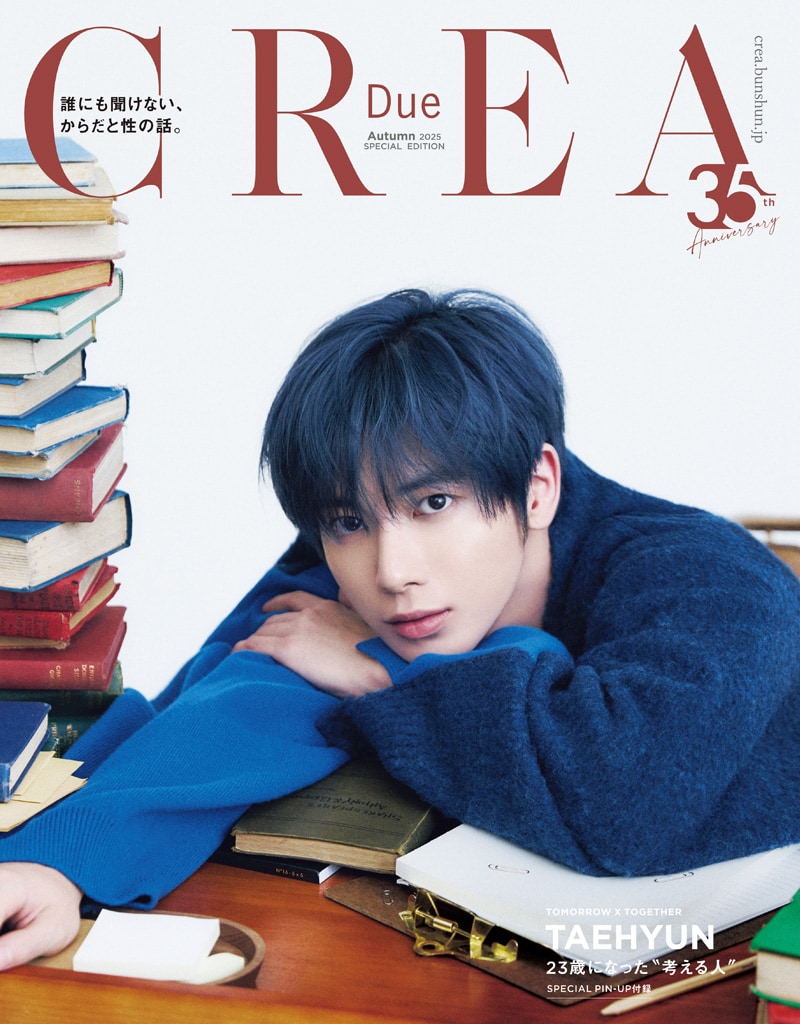暗がりの中、自分の前に立っているその相手は、果たして人なのか、あるいは魔性のものなのか判らないから──
それが黄昏、逢魔が時。
「だめだめ、そんなこと考えちゃ」
奈緒は慌てて頭を振った。きっと、雪乃から聞いた森についての噂を思い出してしまったためだろう。この新時代に、魑魅魍魎なんて馬鹿げている。
つい早足になってしまったが、それでも森の前を歩く奈緒の視線は地面に向いていた。こんなところに何もあるわけない。あるはずがない。お願いだから、何も見つかりませんように。
しかしその足が、ぴたりと止まった。
「ああ……」
唇から呻くような声が出た。眉が下がり、顔が歪む。
震える手で、落ちているものを拾い上げた。
白いリボン。間違いない、いつも雪乃が自分の髪を結わえていたものだ。
そのリボンは、森の入り口に立つ木の根元に落ちていた。おそらく張り出した小枝に引っかかったのだろう。
まるで、持ち主がそこに入ったことを教えるように。
躊躇したのは数分だ。奈緒は意を決して顔を上げ、唇を強く引き結ぶと、あやしの森に踏み入った。
森の中はさらに暗かった。夕日の黄金色の輝きも、この場所では半分が葉によって遮られてしまう。それらの間から漏れてくる光を頼りに、奈緒はおそるおそるといった調子で進んでいった。
自生しているのは大半がブナの木のようだが、それらの中にはずいぶん樹齢が古そうなものもあった。ずっと昔から、形を損なわず続いてきた森なのだろう。道などというものはないので、縦横無尽に生えている下草を踏み、ぼこぼこと露出している太い根を避けながら、少しずつそろそろと歩いていくしかない。伸びた枝に着物の袖が引っかかって、余計に難儀した。
祟りを怖れて誰も手が出せない──という雪乃の言葉を思い出し、ぶるりと身を震わせる。
奈緒だって本当は、怖くて怖くてたまらない。人を食べるという魔物の話もそうだが、もっと現実的な問題として、獣や虫に襲われたらどうしようという切実な恐怖もある。いくらしっかりしていようと、奈緒とて年頃の娘、ミミズもムカデも蛇も、見かけたら大音量の悲鳴を上げてしまうくらい大の苦手だ。
- date
- writer
- category