灯台にかけられた地元の意気ごみ

何しろ政府にしてみれば西洋船の多くがあるいは太平洋から横浜へ、あるいは上海から神戸へといったような航路を取る以上、やむを得ないことだった。灯台とはまず何よりも先に外国人のためのものだったのである。むろん日本海にも維新後すぐに建てられたものもないではないが、しかしそれはたとえば白州灯台(明治六年、福岡県)、角島灯台(明治九年、山口県)のように関門海峡の入口に設けられたので、純粋に日本海というよりも、むしろ瀬戸内のためという気配を濃厚に帯びている。
日本海沿岸の人々は、これには大いに自尊心を傷つけられたにちがいないのだ。これでははっきりと二流あつかいではないか。ましてや日本海は二流どころか、ついこのあいだの江戸時代まで日本の物流の大動脈だった。
そう、いわゆる西廻り航路である。北海道から日本海を西走して関門海峡から瀬戸内に入り、こんどは東行して大坂へ向かう。大坂には巨大な取引市場があって、ものに値段をつける機能があるので、天下のあらゆる物資はそこをめざした、ということは日本海を疾走した。
沿岸の港は、境にしろ浜田にしろ、灯台なんぞ建てずとも入船出船でにぎわったものだし、廻船問屋が立ちならんだものだ。ときには船乗りたちの陸遊びもあって、これがまた大きな利になったのである。
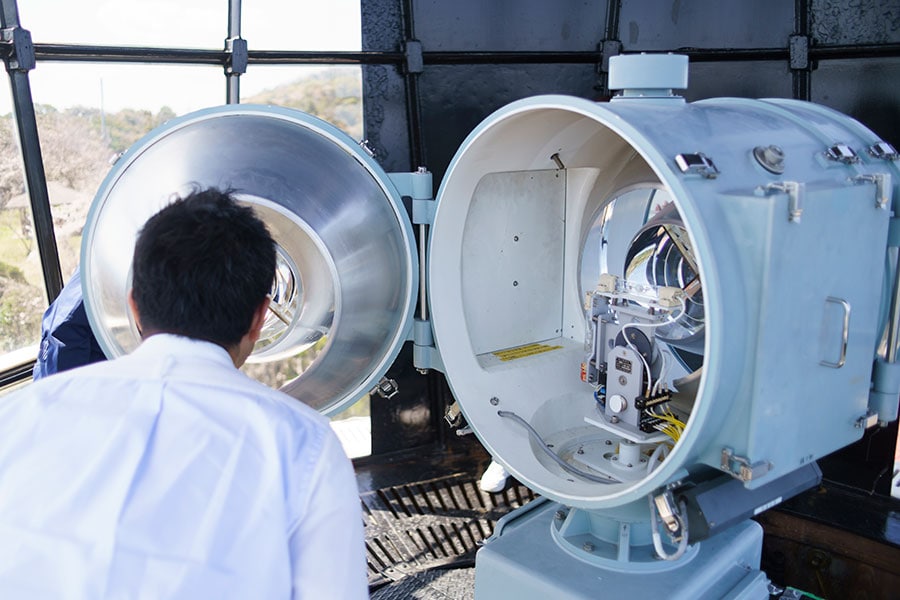
こういう過去の栄光を横に置いてみなければ、地元のこの灯台にかける意気ごみはわかりづらい。
転落からの復活。絶好の手がかり。灯台のために敷地を提供し、道路を整備し、三百人の作業員まで用意したのは「ようやく目を向けてもらえた」という可憐な感動の故であると同時に、おそらくは、この日本海という元来は第一流の海だったものを三十年ものあいだ放置しつづけた国家と国民に対する一種のあてつけでもあった。彼らは恩讐を跳躍台としたのである。




























