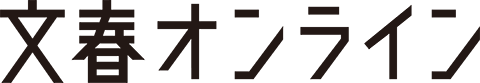「体が小刻みに痙攣し、息が止まった」「穏やかで美しい亡骸だった」住吉さんが目にした愛猫の“最期”
夜半ごろ。驚くことに、私たちのベッドに自力で跳びあがろうとした。もう力がなくて、どすんと落ちた。私はさとちゃんを抱き上げ、ベッドに乗せた。いよいよその時が近いことを感じ、涙が止まらない。他の3匹のネコ達も、いつも通り、ベッドに集まってきた。
ネコは死に場所を選ぶと聞いたことがあった。人目に付かない場所に隠れてしまうかもしれないと思っていた。しかし、さとちゃんはそのまま、私と夫と3匹のネコたちに囲まれ、ベッドの真ん中に居続けた。
苦しそうに息をしながらも、それぞれにまるでお別れの挨拶をするように、少しずつ顔の向きを変えながら横たわっていた。私たちの近くが一番安心だと思ってくれた証のようで、堪らなくさとちゃんが愛しかった。
「さとちゃん、これまで本当にありがとう。私を選んでくれてありがとう。一緒に暮らしてくれてありがとう」と話しかけながら、そっと撫で続けた。
時折うつらうつらしながら、数時間が経った。朝方ふと、私はなぜか「そろそろだ」と悟り、夫を起こした。家族みんなに囲まれ、私に撫でられながら、呼吸の頻度が少しずつ減っていく。そして、体が小刻みに痙攣し、息が止まった。さとちゃんは旅立った。
眠っているようにしか見えない、穏やかで美しい亡骸だった。こんな見送り方をさせてくれるなんて。やっぱり、さとちゃんは奇跡のようなネコだったのだ。
長女であり分身だった、さとちゃんが身をもって教えてくれたこと
倒れた当初、持って1週間と言われたところから、なんと8ヵ月と10日間もがんばってくれた。私の肉体は介護疲れでボロボロだったが、後悔はなかった。最後に濃密な時間を一緒に過ごせたことに幸せすら覚えていた。
さとちゃんは、絶対に奥に知的生命体がいると思わせる、人格を感じる目をしていた。見つめ合うだけで孤独が癒えるような、分かり合えるような、他の子にはない何かがあった。長女であり、私の分身であり、代わりはいない。言葉を交わせなくても、かけがえのない家族だった。未だに毎日、会いたくて仕方がない。
そんな子だから、私にたくさんの気づきをくれた。
介護は大変さが縦糸、でも、幸せが横糸だということ。
介護にも人生にも、型通りの正解はない。ただ、後悔がないように、やれることはすべてやったと思えることが肝心だということ。
そして、与えられた命の炎を燃やし切ることがいかに尊いかという、当たり前のようで難しいことを、身をもって教えてくれたのだ。