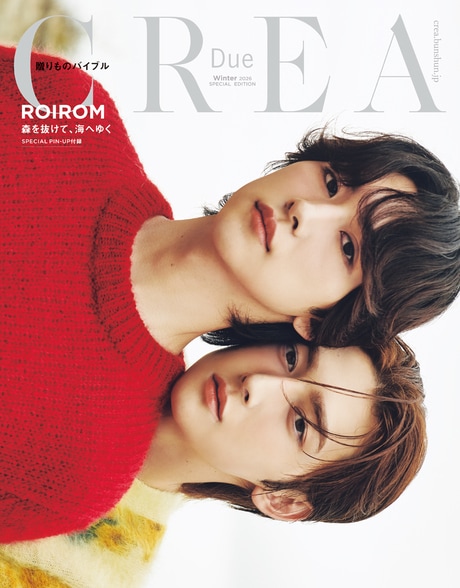「ほのぼの家族」が一転、ホラー一家に
第2週までは「貧しい中でもあたたかな絆で結ばれた家族」に見えていた松野家。ところが銀二郎を婿に迎えた第3週あたりから、その印象ががらりと反転する。トキは傳とタエの実子で、松野家に養女としてもらわれてきたことが判明するが、この事実が明るみになってから、松野家の面々のトキへの依存がだんだん浮き彫りになってくる。
「朝から朝まで」働く銀二郎に対してトキの母・フミ(池脇千鶴)が、特に良心の呵責なく「働き者だねえ」「本当助かるわ」と言ったシーンは、まさに怪談のひとくだりのようだった。それまで一人娘に愛情を注ぐ微笑ましい存在と思えていた祖父と両親が、ともすれば娘を束縛して自由意志を奪い、娘婿の誠意を搾取する「毒家族」にも見えてくる。誰にも悪気はないのだ。けれど、悪気なく誰かを縛っている。

体力気力ともに限界を迎えた銀二郎は東京へ出奔。トキも彼を追って上京する。銀二郎から「2人だけで東京で暮らしませんか」と請われたトキだったが、夫への思慕はありつつも、やはり「放っておくことはできない」と、松野の家族を選ぶのだった。このトキの決断が純粋な家族愛にも見えるし、「毒家族との共依存」を思わせなくもない。
作り手は、人間が包含する矛盾と歪さというグラデーションをなるべくありのまま描いて、その言動に善悪のジャッジを下す作劇をしない。これが『ばけばけ』の魅力であり、肝の据わり方と言える。
そうするより他に選択肢がなかった人がいる。そういう生き方しかできなかった人がいる。時代ごとの制約に縛られながらも、先達が一人ずつ、少しずつ「良き未来」を願いながら奮闘し続けた先に、今がある。こうした昔の人たちの選択や生き方を、「なかったもの」にしたり、現代人の価値観で一方的に「裁き」を与えるのは、傲慢ではないだろうか。明治を生きた「生身の人間」の姿が、観る者にそう問いかけてくる。
世界は二律背反でできている
「夕日がとても綺麗だね」の直後に「野垂れ死ぬかもしれないね」と歌う、ハンバート ハンバートによる主題歌「笑ったり転んだり」が奇しくもこのドラマの真髄を言い表している。その二者は併存し得るということだ。人も、物事も、世界も、二律背反の中にある。人間は愚かだけれど尊く、哀しくも可笑しい。この世はうらめしくも、すばらしい。怪談は怖くて寂しい。誰もが善と悪、裏と表の両面を持ち、そのどちらでもないグラデーションの中にある真実を、このドラマは映し出そうとしている。
第4週で、銀二郎と涙の別れを果たしたトキだったが、今週第5週ではいよいよヘブンとの出会いが待っている。まったく違う文化、異なるバックグラウンドを持つ2人がこれからいかにして理解しあい、心を通わせていくのだろうか。
「怪談」「時代に取り残された人たち」――。このドラマは「見えにくいもの」に目をこらしながら、トキとヘブン、そして彼女らを取り巻く社会を映し出し、「真の多様性とは何か」を探っていくのではないかという予感がする。観客に「正解を押し付ける」のではなく、闇の中から一緒に「探す」。『ばけばけ』はそんな朝ドラになるような気がしている。