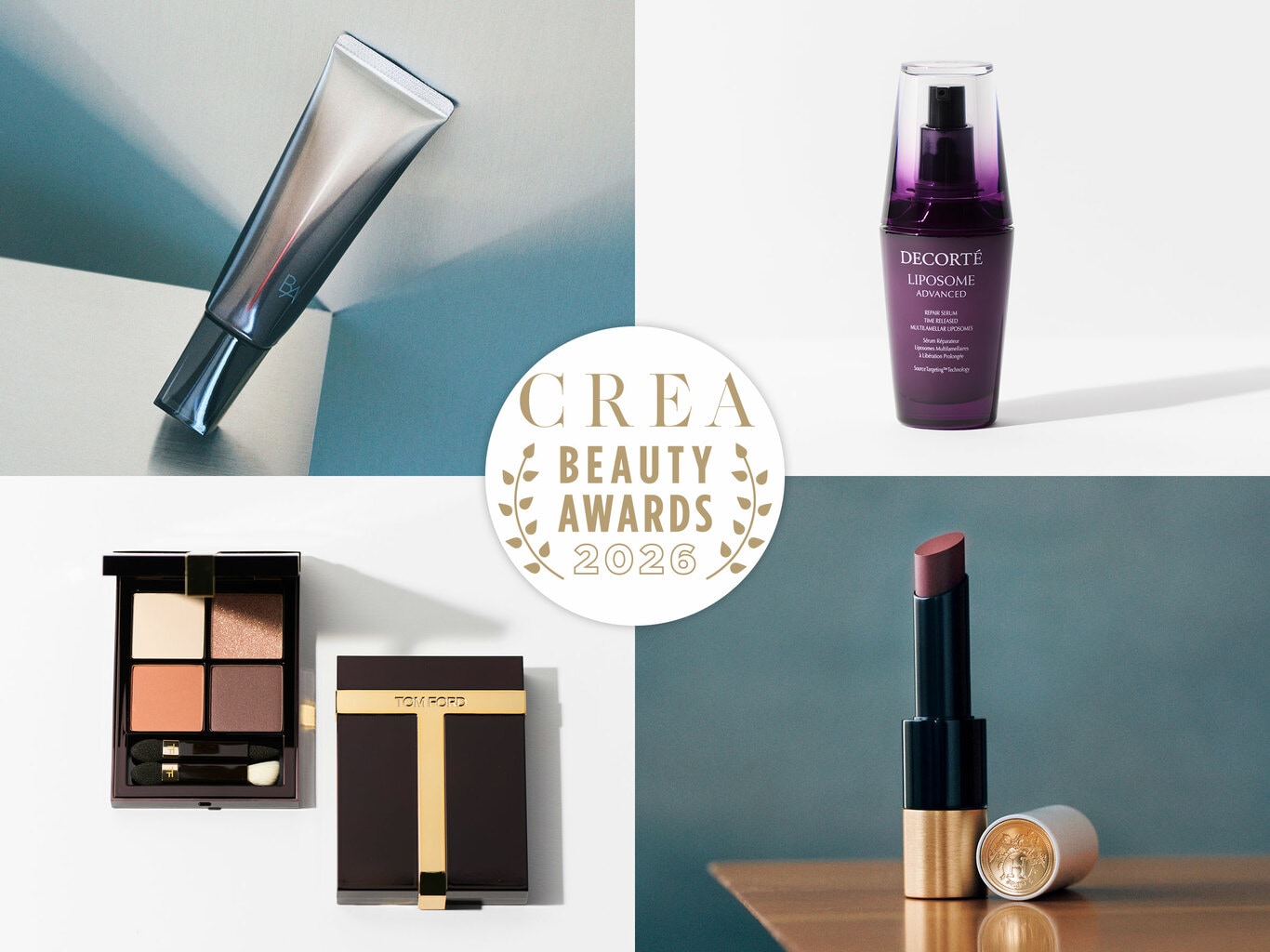編集部注目の書き手による単発エッセイ連載「DIARIES」。今回はオモコロのライター/ディレクターで初の単著『無職、川、ブックオフ』が話題のマンスーンさん。30歳までの無職生活を経て突如やってきた就職&結婚。加速していく「普通の人生」がしっくりこないのはなぜなのか?
目標がない。進むべき方向を指し示してくれるような。心の闇をそっと包み込んでくれるような。動かなくなった脚を一歩だけ進ませてくれるような。そんな目標がない。
理想もない。グチャグチャになって。靄。見えない。窓。開かない。夢。見れない。暑いのか寒いのか分からずに薄いTシャツと厚いダウンを重ねて中途半端。バランスを取るだけでは見出せないから。真ん中であり続けようとしてる。どっちつかずの最悪で最高。
~~~~
高校も大学も自分が入れるところという理由だけで選んだ。将来何がしたいのか分からず留年もして24歳で大学を卒業して無職になった。何もせずどこにも行けず、自分の地図にあったのは実家と土手とブックオフだけで、何がすり減っているのかも分からないから、すり減る感覚だけが部屋に充満していた。川底で少しずつ削られて丸くなっていく石のように生きていた。やりたいことも、やられたいことも思いつかず。どうにかなるのは、どうにかした人だけなのですね。
バイトもろくにしないまま、そんな無職生活を6年程して気がつけば30歳。気がつかなくても30歳。実家住まい。親に将来のことを聞かれても「タハハ……」なんて誤魔化せなくなっていたら急に就職が決まった。言葉の意味すら忘れるほどに遠くにあった就職。
全てが新鮮だった。例えば朝起きて満員電車に乗って会社に行くこと。スーツを着た人たちが作り上げる大きな流れに身を任せて車両に詰め込まれる。触ったら弾けてしまいそうなほど張り詰めた空気。線路と車輪が擦れる音。遅れを謝るアナウンス。顔の前にスマホを持ってきてTwitterを眺める。満員電車や電車の遅延に文句をツイートする人たちの気持ちが自分の中にも芽生えた。大きくて四角い箱にぎゅうぎゅうになって。みちっみちっ……という音が聞こえる。まるでひとつの肉になったみたい。しかしそれだけじゃなかった。嫌だけど少し安心もしていた。やっと社会の一部として認められた気がした。つらそうな顔をした人たちのなかで、僕もつらそうな顔をしてみる。同じ。同じだ。同じって楽だ。
帰りの電車は違う静けさ。車内には疲労と少しの自由が漂っている。つり革を握って目を閉じる。ちょっとだけ明日のことを考える。無職の頃にはなかった明日がある。それは時間としての明日ではない。自分が想像できる範囲にある光としての明日だ。真っ暗だった頭の中に明日も仕事をしている姿を思い浮かべる。目を開ける。全員がスマホを見ている。ちょっと変な顔したって誰も気にしないだろう。他人。だけれど他人じゃないみたい。同じ方向に高速で運ばれている人たちと一緒に。途中の駅でドアが開く。外の匂いが風とともに入ってくる。家には吹かない風。窓ガラスに映る自分は少しいい顔をしていた。
あとは電話対応にすごく緊張すること。最初は電話なんてできるだろうと思っていたのだが、いざ出てみると緊張してしまい、相手の会社名や名前がぜんぜん頭に入ってこなかった。もちろん聞き直すなんてことはできず、電話を繋ぐ担当者の同僚に「あ~なんかカタカナの感じの会社名です」みたいに曖昧に覚えた会社名を伝えていた。恥ずかしい。電話一つ取れない自分。それからどんどん電話が嫌になり、電話が鳴った瞬間、体を前のめりにしてパソコンのディスプレイを凝視して「今すごい集中してるので!」というオーラを出してなんとか電話に出ることから逃れていた。
それでも電話に出なければいけない時はあるので、自分なりの攻略法を編み出していった。まず電話している自分を俯瞰して、電話をしているのは自分ではなく、電話をしている別の自分を操作している他人だとイメージする。そうすることである程度落ち着くことができる。この方法は電話だけではなく、仕事上のいろいろな場面で使っていたと思う。例えば取引先の会社に行ってプレゼンをしなくてはいけない時も、一旦自分を架空のサラリーマンだと思い込んでから喋ることであまり緊張しなかった。どんなに失敗しても、その架空のサラリーマンのせいなので自分は傷つかなかった。よくないかもしれない。傷つかない方法ばかりうまくなっていくことが正しいのかは分からない。でもそのズルさも自分なのだと思っている。
文=マンスーン