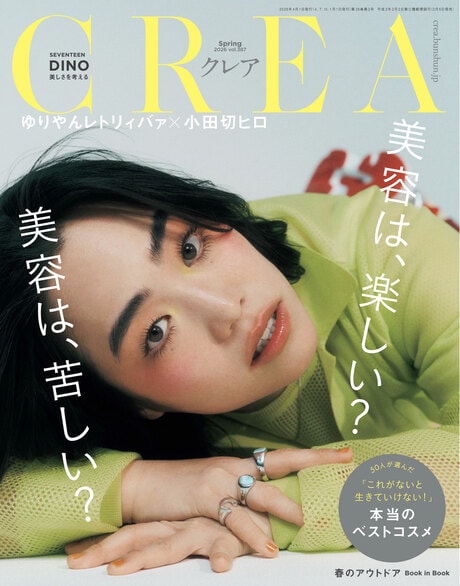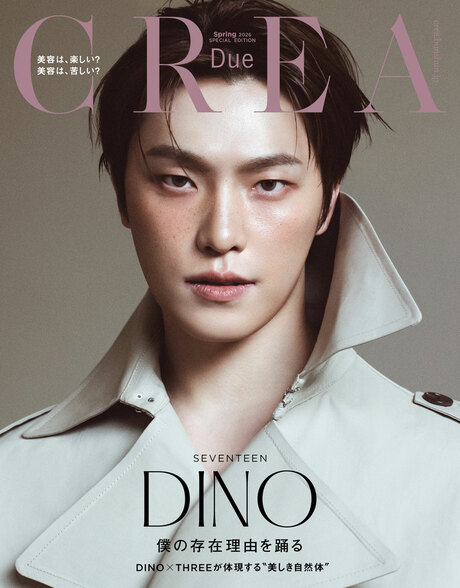NHKの朝ドラ「カムカムエヴリバディ」や土曜ドラマ「心の傷を癒すということ」、映画『港に灯がともる』を手がけた安達もじり監督と堀之内礼二郎プロデューサーがNHKを退職し、神戸を拠点にした映像プロジェクトに挑む。2人のものづくりの原点を聞いた。
≫「カムカム」安達もじりと堀之内礼二郎がNHKから独立 フリー映像監督と制作会社代表になって叶えたい夢は「関西を映像文化の拠点に」
テレビ、映画、配信…それぞれに“オプション”の良さがある

――神戸が舞台であればテレビドラマ、映画、いかなる形式の映像作品でも挑戦していきたいというお話でしたが、テレビドラマと映画のいちばん大きな違いはどんなことでしょうか。
安達もじり監督(以下、安達) 手法としてのいちばん大きな違いはやっぱり、音でしょうか。「聞かせる音を作る」のがテレビドラマ、「そこにある音を表現する」のが映画。テレビドラマだとまず絶対に台詞が聞こえないとダメで、台詞の隙間から聞こえる音をどう埋めていくか、というやり方なんですね。台詞以外にも「この音はどうしても聞いてほしい」という優先順位をつけて、それがはっきり聞こえるように編集していきます。
逆に、映画はどれだけ台詞の声が小さくても、大きな生活音をかぶせても、映画館の音響システムの中だと台詞は聞こえるんです。なので、何を表現すべく、どの音を立てていくかという選択が、テレビドラマと映画では全く違う気がします。
――媒体によってやり方は違うとは思うのですが、「わかりやすさ」と「奥深さ」のバランスについては、どうお考えですか?
安達 そこがいちばん難しいです(笑)。やっぱり最終段階の編集の作業が「観る人にどう伝わるか」に最もダイレクトに作用するので、そこはスタッフ間で徹底的に議論します。「説明はできても、気持ちが伝わらない」というのがいちばんうまくいっていない状態で、「説明してなくても、ちゃんと感情は伝わっている」ことを目指していつも粘って仕上げ作業をしている気がします。
堀之内礼二郎プロデューサー(以下、堀之内) プロデューサーとしては、編集室に入るということはないんですが、編集し終わった映像を見せてもらって、「何を思ったか」「どう感じたか」を言います。プロデューサーは最初の観客だと思っているので、「ここが伝わりにくかった」「ここ、誤解してしまうかも」みたいなことを伝えて、あとはそれをどう解決するか、監督に任せるというスタンスですね。僕の場合は。
――昨今、「わかりやすさ」の線引きがどんどん難しくなっていると感じます。特に朝ドラなどでは、「理解できないもの」が叩かれる風潮にあったりして。メディアも一度「駄作」の烙印を押したら最後、本来の作品批評から大きく外れたところで叩いて、一部視聴者の過激なクレームを煽るという流れができあがってしまっている。こうした時代にあって、制作側と視聴者のコミュニケーションの取り方についてはどうお考えでしょうか。
堀之内 ウェブのしくみとして、ビュー稼ぎのために偏った方向性の記事ばかりを出すという流れは確かにありますよね。ウェブ記事にしてもSNSの投稿にしても、一部ではありますが、あまりにも「重箱の隅つつき」で、真っ当な批判になっていないなと感じるものもあります。
昔は「マス」というものが存在し得たんですよね。たとえば「30代女性が好きなものはこれだから、ここを狙えば当たる」というように、マーケティングでヒットドラマを作ることもできた。でも今は多様化が進んで、多様すぎて「何を狙えばいいのかわからない」みたいな状態になってきている。すごく難しい時代だなと、僕も感じます。「当てに行こう」というのがもう無理になってきている。当てに行けば行ったで、作為が見えますしね。
でも、そうであれば、自分がこの世の中を生きてきて、感じとって、得たもの、自分の中にある「思い」を灯に作っていくしかないのかなと。昔から変わらない「大事なもの」を灯にして、届けたい相手の顔を思い浮かべながら自分たちが納得いくもの作りをしていけば、きっといつか届く。そう信じています。
安達 「どうやったら人に届くのか」というのは、永遠の課題ですね。私もその都度その都度、10年前もそういうことで悩んでいた気がしますし、これからも悩み続けるんだと思います。時代ごとの文化やメディアのあり方によって伝え方も変わっいきますし、人と人が話をしたって、届く言葉と届かない言葉がある。この1年ほどで自分が経験させてもらったことで言うと、『港に灯がともる』の舞台挨拶で、観にきてくださる方々と触れあって、「ちゃんと顔を見て届けていきたいな」と強く思いました。
今はテレビ、映画、配信といろんなプラットフォームがありますが、それぞれについた「オプション」の良さがあると思っていて。テレビは、自分で選ばなくてもお茶の間で観られるというオプションがついている。映画は、劇場という空間で多くの人と一緒に決まった時間観るという体験のオプションがついている。配信は、好きな時に好きな場所で観ることができるオプションがついている。それぞれのオプションの良さを活かす作り方をしていけたらいいのかな、と思っています。
文・撮影=佐野華英