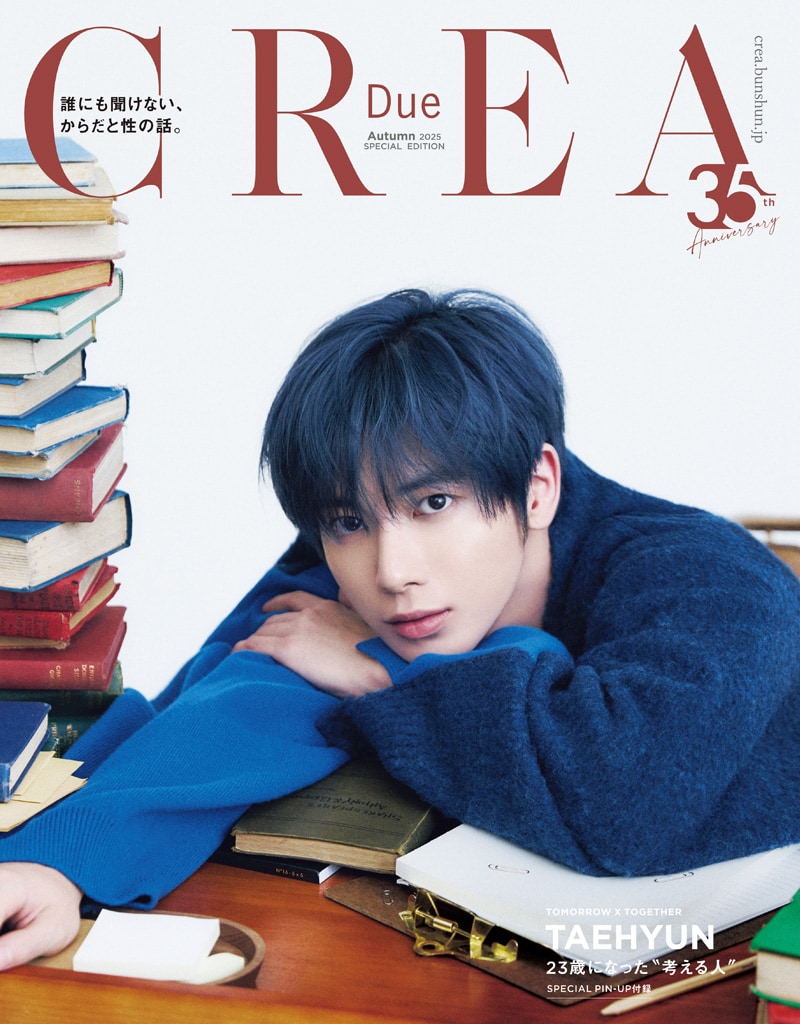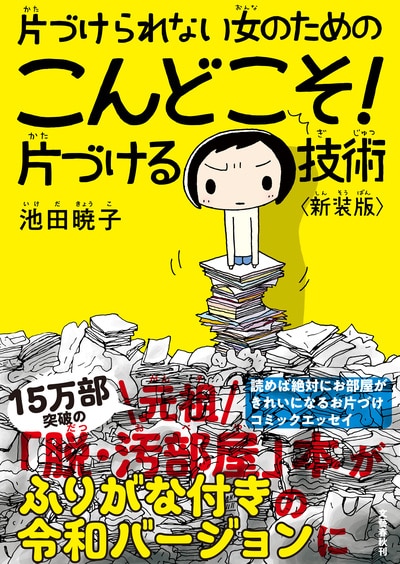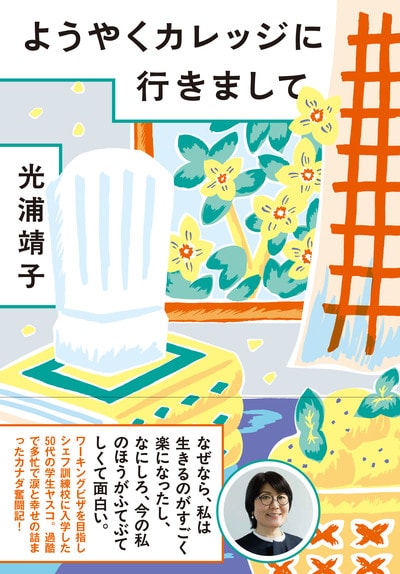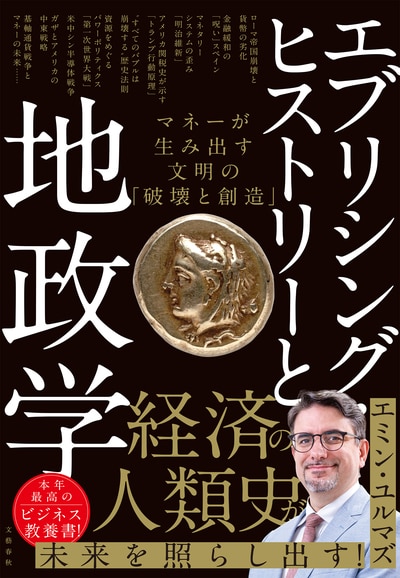『石井桃子集』の功績はとりわけ、彼女の業績のなかでもっと言及されていいはずの小説『迷子の天使』を第三巻に収録したことと、第七巻でエッセイをまとめて読めるようにしたことだと思う。
第七巻は一九五一年から半世紀近くにわたって書いてきた文章六一篇を収録し、書き下ろし一篇を加えたものだった。本書第二章はここから六篇を選んでいる。
石井桃子の多面的な活動のひとつとして、児童書にかんする施設や運動体の運営がある。白林少年館、家庭文庫研究会、かつら文庫、東京子ども図書館などである。こういった活動のなかから中川李枝子文・大村(山脇)百合子画の『いやいやえん』も登場した。「生きているということ」は、自ら設立した東京子ども図書館の《おしらせ》二〇号(一九七九年一月)に掲載したもの。
石井桃子の創作でもっとも有名な『ノンちゃん雲に乗る』は戦後に登場した「戦時下文学」である。そのあたりの事情は「自作再見『ノンちゃん雲に乗る』」で回想されている。《朝日新聞》一九九一年九月二二日に掲載された。
石井桃子は戦後、児童文学研究者としてたびたび英語圏を訪れた。移動すること、人と出会うことについてどう考えていたか、「ひとり旅」(角川書店《俳句》一九七六年一月)と「ヘレン=T」(《びわの実学校》一九八四年五月)で彼女は少しだけ教えてくれている。
「太宰さん」(岩波書店《文庫》一九五七年六月)と「井伏さんとドリトル先生」(筑摩書房『井伏鱒二全集』第一二巻月報、一九九八年一一月)は、このふたりの小説家との交流を回想したもの。石井桃子と太宰治の縁については、井伏鱒二の随筆「をんなごころ」にも違う角度から書かれている。
犬養道子の回想記『花々と星々と』『ある歴史の娘』に、若いころの石井桃子が登場する。祖父・犬養毅が菊池寛を介して蔵書整理のために雇った、日本女子大出の海老茶袴(えびちゃばかま)の女性だ。「クマのプーさん」シリーズ日本語訳のきっかけは、西園寺公一(きんかず)が『プー横丁にたった家』の原書を幼い道子の弟・康彦にクリスマスプレゼントとして贈ったのを、石井桃子が道子たちに訳して聞かせていたことだったという。
- date
- writer
- staff
- 文=千野帽子(エッセイスト)
- category