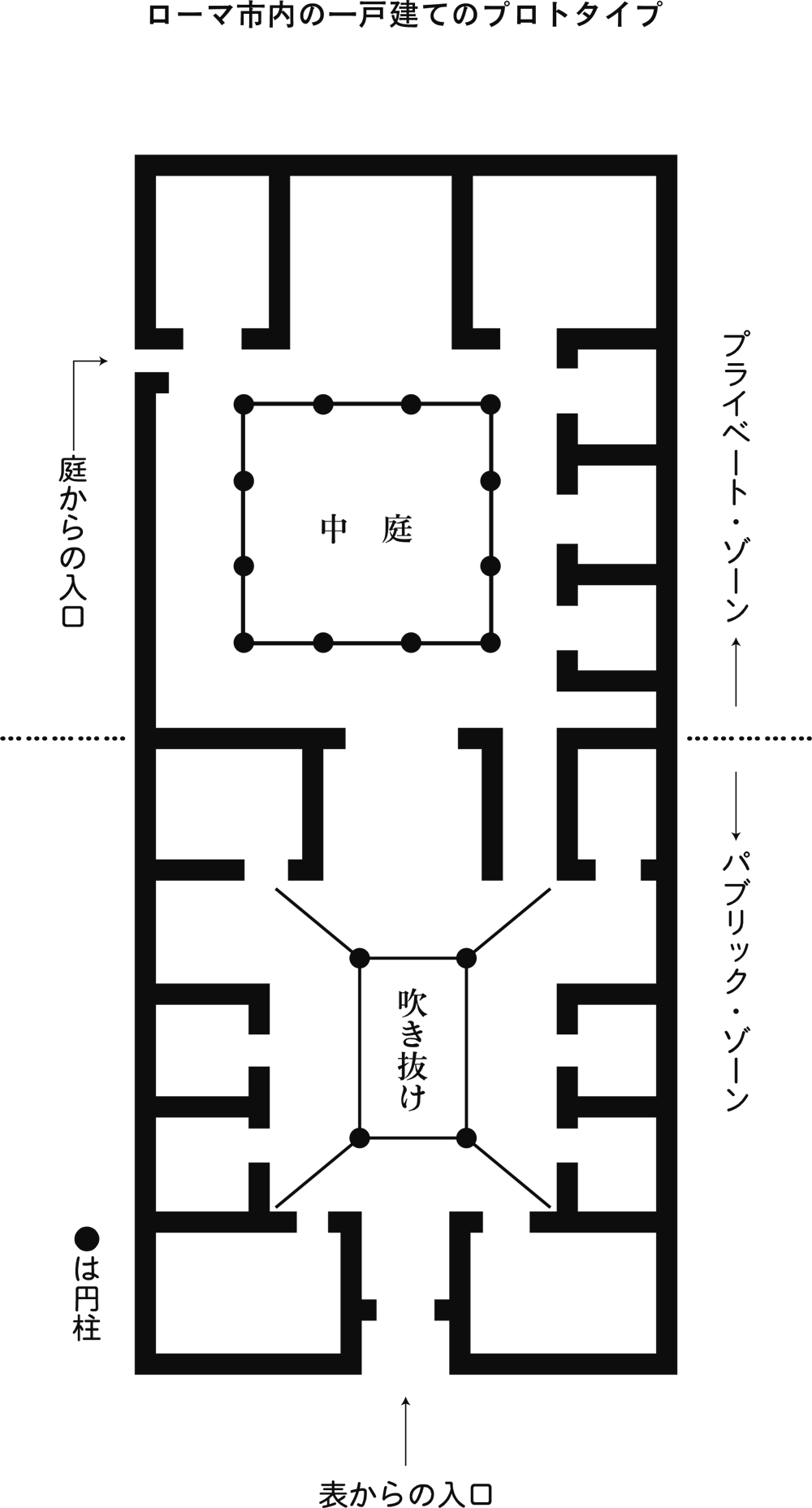
読者に(初刊行から二十年余りが過ぎた二〇二三年になって、改訂版を出す気になった理由について)
五十年以上も作家業をつづけてきて痛感しているのは、学者と作家の本質的なちがいは何か、ということである。
ちがいの第一は、人間という存在への好奇心の強弱。
第二は、何が書かれているか、と、それらがどう書かれているか、に投入される関心の強弱。作家が命を削るのは、どう書くか、のほうなのである。
二十年以上も昔に出版した『ローマ人への20の質問』は、何が書かれているか、に関してならば、改めるべきことは一つもないし、つけ加えることもない。しかし、どう書かれているか、になると、作者である私には不満は無くもない。
なぜなら、あれを書いた当時の私は、十五年を費やして書くと決めた『ローマ人の物語』の執筆の真最中(全十五巻のうち第九巻を準備中)で、年に一巻ずつ刊行するという読者への約束を果すのに全力を集中していた日々の連続。他の仕事までする余裕などはなかった時期である。それが、気の合った編集者の誘いに乗ってしまった結果出来たのが『ローマ人への20の質問』。何をとりあげたか、には自信はある。しかし、その一つ一つをどう書いたか、となると、少々なおざりにしたという想いは、その後もずっと抱いていたのだった。
改訂版は、その辺りを改めただけである。だから、何が書かれているか、にしか関心がない人は、何もわざわざ改訂版を買い求めることはない。なにしろ、改訂版を出したいと思った理由の最たるものは、死んだ後に恥ずかしい作品を残したくない、につきるのだから。
*
真夏のローマの午後くらい、人通りも少なく静かな時間もない。家人たちも暑さを避けて郊外の山荘に行っていて、家に残っている人がいたとしても、公務があって首都を留守にできない男くらい。
その日も、典型的なローマの夏の午後だった。そのローマの一つの家の扉を押した私は、「サルベ、入ってもいいですか」と言ったはよいが、そこで立ち止まってしまう。その私の眼の中に、中庭をめぐる円柱の一つに背をもたせた姿で立っている、一人の男が入ってきた。
年の頃は、四十代半ばというところか。これより始まる「対話」というか「インタビュー」は、古代のローマに迷いこんでしまった現代に生きる私と、暇をもてあましていたらしいそのローマ人との間で交わされた、正直で率直な対話の一部始終である。
<読者に より>




























