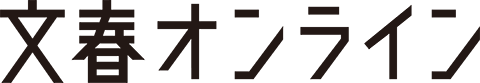いかに戦争の記憶を次世代に継承していけるのか
最近は原作者のイシグロ自身も、過去に人類が起こした大きな過ちを次の世代に伝えていくことの使命感といったものを、折に触れて語っている。このたびの変更は、エグゼクティブ・プロデューサーとして映画のクレジットにその名を連ねる、彼の意向が反映されているのかもしれない。
年齢を重ね今や大御所となったイシグロが、自らの社会的責務を自覚するようになったということか。戦後80年が経過し、実際にその災厄を経験した人の数も急速に減少している状況のなか、いかに戦争の記憶を次世代に継承していけるのかということが、昨今あらためて課題となっている。その意味では、今回の変更は時宜に適ったものと考えられる。

しかし実は長崎生まれのイシグロは、この長編デビュー作発表前後に自分の母親から聞いた話をもとに、原爆の悲惨さをかなり克明に記した「長崎から逃れて」という作品を書いている。結局その原稿が日の目を見ることはなく、今はテキサス大学の書庫に収蔵されているのだが、今回の映画での母から娘への記憶の継承という原作からの変更点は、イシグロ自身の実体験を反映したものと捉えることもできるだろう。
私は昨年、イシグロの生地であり、この小説と映画のおもな舞台となっている長崎を訪れ、関連する場所をへとへとになるまでくまなく歩いた。原作はけっして現実の長崎を正確に反映しているわけではなく、あくまでも作者イシグロの記憶と想像の「ナガサキ」なのだが、それでもその体験は、私にとってこの作品をよりリアルに感じさせるものであったし、今回の映画化によって、さらに鮮烈に悦子の物語が記憶に刻まれた。
またこのたび戦争や原爆、その記憶を語り継ぐといったことをより明示的に表現した製作者側の意図を思うとき、この作品に関わる私自身の様々な経験が、より重みを帯びてきたように感じる。人の話を聞いて、錯覚しないまでも、それを自分のことのように受け止めるのも、ときには必要なのだろう。(文中敬称略)
- date
- writer
- staff
- 文=荘中孝之
- category