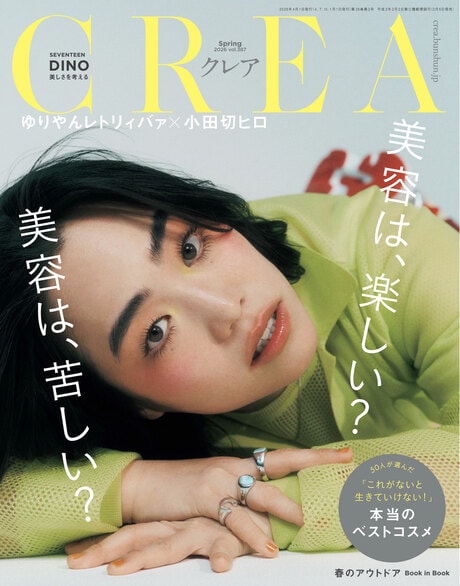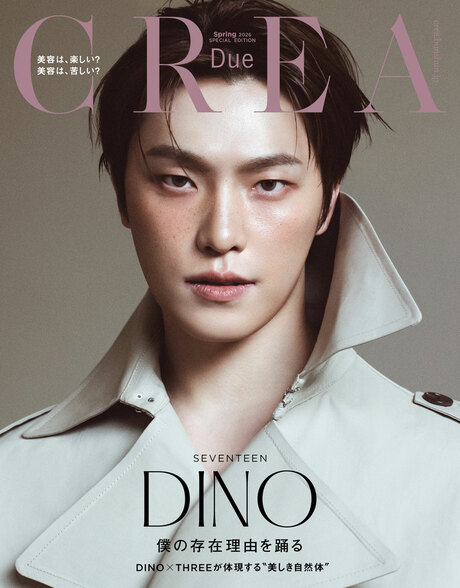「西の西陣、東の桐生」と称されるほど、古くから繊維産業が栄え、織物の産地として知られる群馬県桐生市。なかでも、桐生天満宮を起点にした本町通りは、のこぎり屋根の工場や蔵など地域産業を支えてきた建造物が今なお残り、風情ある町並みを形成しています。
そんな本町通り周辺は飲食店や土産店などが点在し、山歩きの後の観光にもおすすめのエリア。今回は、鳴神山でハイキングを楽しんだのち、モデルの吉岡更紗(さらさ)さんとともに出かけた町散策の様子をご紹介します。
» もっちり食感がクセになる。桐生に来たら味わいたい、名物ひもかわうどん
» 路地裏で目を引く個性派スポット。刺しゅう屋×ボタニカルショップ「TENBOU(十坊)」とは?
もっちり食感がクセになる。桐生に来たら味わいたい、名物ひもかわうどん


鳴神山ハイキングで適度に体を動かしたら、いい具合に腹ぺこに。登山口からまず向かったのは、本町にのれんを掲げる1887年創業の老舗うどん店、藤屋本店です。うどんやそば、丼ものなどがそろうメニューのなかでも、藤屋本店のイチオシはひもかわうどん。幅広の麺と強いコシが特徴のうどんで、桐生では古くから郷土料理として親しまれています。


桐生を訪れるのも、ひもかわうどんを食すのも今回が初めてだという吉岡さんは、ひもかわうどんとミニ天丼のセットをオーダー。いざ運ばれてきたひもかわうどんを前に、彼女の第一声は「こんなに太いんですね!」。一般的なうどんとは大きく異なる幅広麺に驚きつつも、わくわくしている様子が伝わってきました。

まずはひもかもうどんを1本口へ。「うん、おいしい! 食感がもっちもちで、すごく食べ応えがありますね。少しほうとう(山梨の郷土料理)に似ているのかな。太いけれど、つるんとしているから見た目よりずっと食べやすい。桐生に来た人にぜひ食べてみてほしいですね」
名店店主が語る、桐生の女性を支えたひもかわうどんの歴史

吉岡さんも大満足のひもかわうどんですが、由来は東海地方の郷土料理。愛知県刈谷市に伝わる平打ち麺の芋川うどんが群馬にわたり、その過程で“いもかわ”が訛って“ひもかわ”と呼ばれるようになったのだそう。名物グルメの歴史を、藤屋本店 六代目店主の藤掛将之さんが教えてくれました。
「ひもかわうどんの麺は幅広ですが、厚みが普通のうどんより薄く、茹で時間が短くて済むのが特徴です。かつては、冬の煮込み料理として親しまれていたと聞いています。
桐生は古くから繊維産業が盛んで、機屋(はたや)が多く、産業がら女性労働者も多かったようです。機屋(はたや)に従事する女性たちは仕事を終えれば、家に帰って夕食の支度をしなければならない。そんな忙しない生活の中で、さっと茹でて煮込みうどんを作ったり、味噌汁の具材にできるひもかわは、働くお母さんたちに重宝されたそうです。
群馬には『かかあ天下とからっ風』という言葉があるのですが、労働も家事もこなして一家を支える女性の強さと、群馬特有の赤城おろし(赤城山から吹き下ろす冬の強風)を表しています。ひもかわが今では通年、広く親しまれるようになった背景には、桐生の女性の暮らしや繊維産業の発展があるんです」
おいしさは桐生随一と評判。藤屋本店流ひもかわうどんのこだわり

幼少期から、五代目である父親が働く姿を間近で見てきた藤掛さんいわく、店を継ぐことはごく自然な流れだったそう。大学を卒業したのち、東京都内の日本料理店での修行を経て六代目に。以来、うどん作りに励んできた藤掛さんに、藤屋本店のひもかわの魅力を聞いてみました。
「うどんの生地作りはとても繊細で、その日の気温や湿度によって水や塩の加減を変えなければならない。機械で生地を製造することも可能でしょうが、手作業のほうが細かな調整ができるんです。使用する小麦のバランスにもこだわりがあり、群馬県産の小麦を軸に数種をブレンドしています。また、麺は作り置きをせず、日ごとに店で打つ自慢の自家製麺。桐生にいらっしゃることがあれば、ぜひうちのひもかわうどんを召し上がってもらいたいですね」
鳴神山の山頂で出会った地元のハイカーに、昼食はひもかわうどんを食べようと思っていますと伝えると、「それなら藤屋本店がおすすめだよ。あそこのひもかわがいちばんおいしい」と教えてくれました。創業から130年以上、地域の人からも観光客からも愛され続ける藤屋本店。桐生を訪れる際は、ぜひ足を運ぶことをおすすめします。
藤屋本店
群馬県桐生市本町1-6-35
https://fujiya-honten.net/index.html