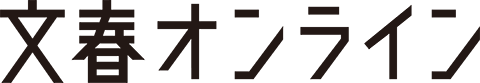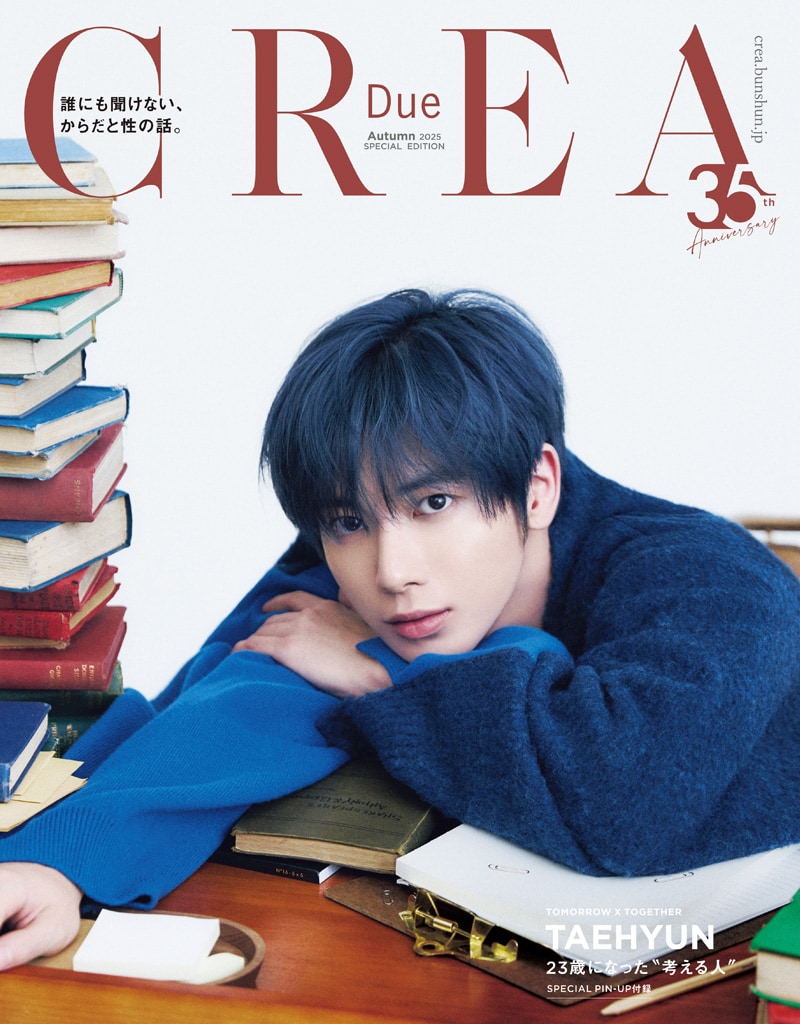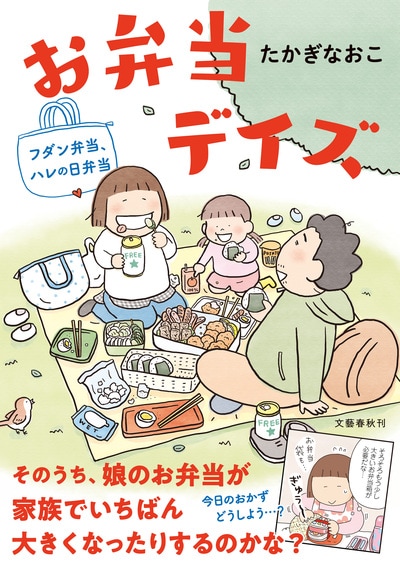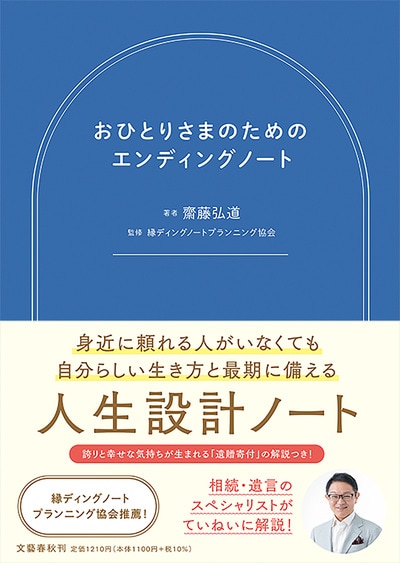「時代の中で精一杯生きる」と「一生懸命生きているつもりが時代に流されている」
例えば映画監督の伊丹万作は「戦争責任者の問題」の中で「だまされたものの罪は、ただ単にだまされたという事実そのものの中にあるのではなく、あんなにも造作なくだまされるほど批判力を失い、思考力を失い、信念を失い、家畜的な盲従に自己の一切をゆだねるようになつてしまつていた国民全体の文化的無気力、無自覚、無反省、無責任などが悪の本体なのである」と記した。これもまた「時代の中で精一杯生きる」ことの一断面である。表層的に「時代の中で精一杯生きる」を肯定してしまうと、この陥穽に足をとられてしまう。これはハンナ・アーレントが『エルサレムのアイヒマン』(みすず書房)で指摘した、「命令に従っただけ」と非人道的行為を行ってしまう「凡庸な悪」の問題にも通じる。
「時代の中で精一杯生きる」ということと「一生懸命生きているつもりが時代に流されている」の間にはどのような境界線があるのか。

『風立ちぬ』では「時代」という枠組みと、二郎の“芸術家”としての「業」を強調したことで、その境界線が見えなくなっている。『パトレイバー2』がリアリストであることを強調して、その先にある政治性に触れなかったように、『風立ちぬ』もまた作品の主題が強調されることで、別の側面が見えなくなっている。映画としてはそれでよいが、現代に生きて時代を作っている各個人が時代から逃れえないという形で、自分を免罪してしまうロジックと紙一重であることは、意識する必要がある。
この「当時を生きた人間を、現在の価値観に照らし合わせて“正しく”描いていいかどうか」という問題は『この世界の片隅に』の内容にも関わってくる。
◇
後編では、本書より映画『この世界の片隅に』(2016年)についての評論を紹介。あるシーンのセリフが原作小説から大きく変更された理由とは?
〈「じゃけえ、暴力にも屈せんとならんのかね」 映画『この世界の片隅に』で原作から変わったセリフが示す“深い意味”《9年ぶり再上映で話題に》〉へ続く

アニメと戦争
定価 2,200円(税込)
日本評論社
» この書籍を購入する(Amazonへリンク)
- date
- writer
- staff
- 文=藤津亮太
- category