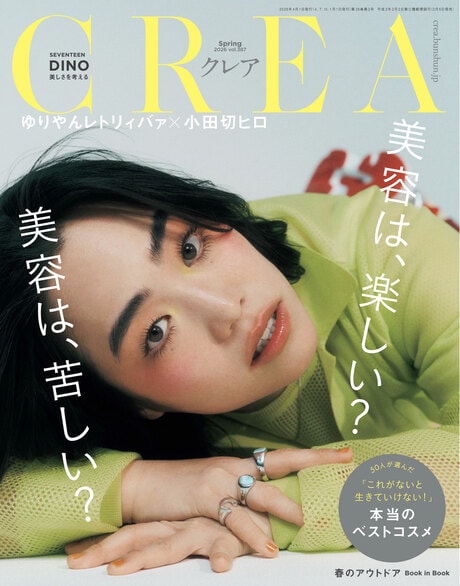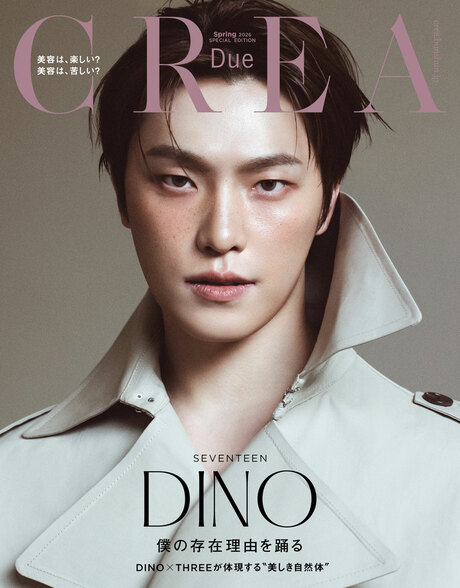中学や高校で習った数学を思い出してみてください。最初は数から始まり、次に図形や空間を扱い、さらには関数やベクトル、数列や確率まで詰め込まれていましたよね。もっと踏み込んでいくと、「数理論理学」といって、数学の理論を展開する際の論理の基礎を学ぶ分野もあります。また、最近はプログラミング言語もかなり数学チックになってきている。このように数学は、多種多様な領域の学問がごっちゃに入り乱れて異種格闘技戦を繰り広げている、まさに“バトル・ロワイアル”の舞台となっているのです。
これは、ほかの学問には類を見ない多様性ですね。物理学もけっこう領域が広い学問ではありますが、宇宙とか物体とか、何かしらの「物」についての学問ですという説明の軸がある。生物学だったら、生命現象の謎に迫っていく学問。化学だったら、物質を構成している仕組みにメスを入れていく学問。宇宙科学だったら、地球の外に広がっている宇宙空間について探究する学問だと説明できますよね。そのなかで数学だけが、何についての学問なのか、バシッと一言で説明できる軸がないのです。
どうしてそんなことになってしまったんですか!?
やっぱり怒ってますよね?
私は、これは歴史的な偶然が生み出した結果なんじゃないかと思っています。例えば、江戸時代にペリーの黒船が来航し、幕府は長らく続けていた鎖国を解いて開国へと向かいましたよね。でも黒船来航は宇宙の必然だったのかと言えば、そうではない。黒船が日本を訪れなかった歴史だってあり得たわけです。それと同じように、数学史においてもひょんな出来事が積み重なっていき、今の数学が作り上げられたのではないでしょうか。
数学も最初は単純に、「数」についての学問だったのかもしれません。それが、時間が経つにつれて別の要素がどんどん加わっていった。
例えば、度量衡について考えてみましょう。古代の人間が家を建てたり農地を区切ったりするとき、最初は長さを1、2、3……と単位で数えるような、安直なものの測り方しかしていなかったと思うんです。でもそうしているうちに、たとえ「数」でバシッと書けなくても、「量」を考えるのは大事なんだということに気がついた。そこから平面図形の面積、立体の体積なども、数学の分野に加わったのでしょう。