そこから覗く中身に、私と次郎丸くんは顔を上げて目を合わせた。次郎丸くんはADバッグからカッターナイフを取り出して段ボールを素早く――それでいて慎重かつ丁寧に――解体した。
段ボールが展開され、敷き布団のようにその中身の下敷きになった。
あおむけになったその腹にしっかりと人の命に届きうるサイズの刃が刺さり、赤黒い液体がジャケットを染めている。そこまではいい。問題は、その目が白目を剝いていることと、その顔が生きている人間のものとは思えないほどに冷たいこと。
箱に入っていたのは勇崎恭吾の死体だった。
二度目の絶叫がスタジオに響いた。サスペンスによくある「きゃー」的な甲高い悲鳴ではなく、音で言うと「うおお」の三音をベースにした可愛げのかけらもない私の悲鳴。
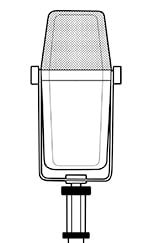
スタジオから前室まで届く「うおお――」という悲鳴。おれのピンマイクを調整してくれていた音声さんが、怪訝そうに首をかしげた。
「何かあったんですかね」緊張をほぐすために声をかけた。
「どうせまた幸良Pが何かドジってるんじゃないっすかね」
おそらくおれより十歳近く年下であろう音声さんは、タメ口との境界線上くらいのゆるい敬語でそう返してくれた。それだけ仁礼左馬というタレントに対して親しみを持ってくれているということだろう――おれの思考は常にポジティブに流れるよう重力を操作してある。
「幸良さん、そんなドジなんですか」打ち合わせしてるときはそんな感じなかったけど。
「ディレクター時代に、番組の最後に出すプレゼント応募用のQRコードを間違えて、なぜか国税庁がe-Taxの利便性を案内してるページに飛ぶやつにしちゃって、いわゆる陰謀論的な界隈の人たちが“国がメディアを操って納税額を増やそうとしてる!”みたいなことを投稿しまくるっていう炎上を起こしたことがあるらしいっす」
- date
- writer
- category



























