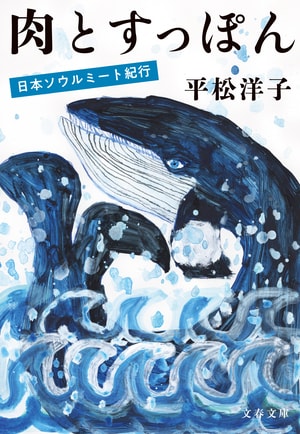
私は毎年北極探検にかよっているので、肉食と聞くとどうしてもイヌイットの食事のことが頭にうかぶ。
私の根拠地はグリーンランドのシオラパルクという、四十人ほどのイヌイットが暮らす世界最北の集落である。この村にかよいはじめたのは二〇一四年冬からだが、その食文化にはやはり強烈なインパクトがあった。
農業ができない北極の地で暮らすイヌイットは、いうまでもなく動物の肉だけをたよりに生きてきた正真正銘の狩猟民だ。ビタミンを摂取するため生肉や生肝臓をこのみ、ときにはドラキュラのように血そのものを旨そうに舐めたりもする。
当然珍味には事欠かない。たとえば狩りの難しい冬(北極の冬は太陽の昇らない暗黒の極夜だ)を乗りきるため、小型の渡り鳥を海豹(アザラシ)の皮のなかで発酵させるキビヤはその代表格だ。強烈な発酵臭をはなつ生肉を口を血まみれにしながら内臓まで食べるため、見た目はおぞましいが、慣れると脂ののった生肉はクリームチーズのようにまろやかで忘れられない。日本に帰国して一番恋しくなるのがこのキビヤだ。キビヤ好きが昂じて、私はかならず日本にもどる前に鳥を捕獲し、海豹の皮袋につめ、次シーズンのキビヤを作ってから帰国するようになった。
海象(セイウチ)の胃袋のなかにたまった未消化の二枚貝も絶品だが、こちらは村人にとってもごちそうなのでなかなか分けてくれない。海豹の目玉は狩りの途中での水分補給のための食材で、鯨の皮はマッタといってビタミンが豊富なごちそうだ。鯨、海豹、海象といった主食のほか、狼、白熊、狐、馴鹿(トナカイ)、麝香牛と何でもござれ、食べない動物は犬ぐらいだ。いまもボートや犬橇で周辺の猟場をまわり、海獣類を狩猟して暮らす彼らこそ、地球上でもっとも徹底した肉食主義者といってさしつかえないだろう。
ただ私にとって強烈だったのは肉食そのものというより、肉食にともなう村の風景だった。
彼らは毎日のように猟に出て海豹や海象や鯨を仕留め、それを村の砂浜に引っ張ってきて解体する。海象や鯨のような大物ともなると、村の女子供が総出でまわりをとりかこみ、熱い息を吐き、甲高い歓声をあげながら、血まみれの解体作業を興奮の眼差しでみつめる。解体がおわり、ブロック状の塊に切り分けられた肉は、そのまま各自の貯蔵庫や自宅にむかう。肉塊のなかにはその日の夕食のテーブルにのって村人の胃袋におさまるものもあれば、天井に吊るされ、さらに細かく切断されて飢えた犬のもとにはこばれるものもある。要するにここでは、動物の死が人間(と犬)の生に転換する全プロセスが、目の前でむき出しになっている。生と死の循環がおもむろに可視化されているのだ。
文=角幡 唯介(探検家・作家)



























