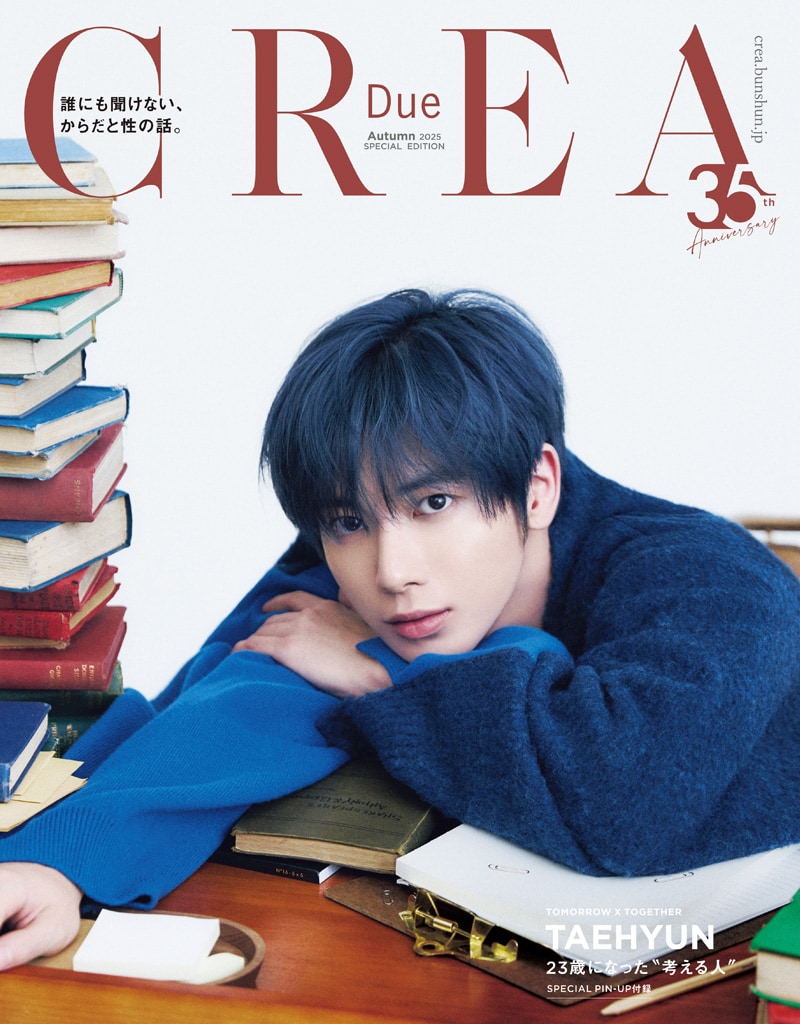また松山市は、俳人の正岡子規が育ち、文豪の夏目漱石が明治二十八(一八九五)年に英語教師として赴任した、文学とゆかりの深い町でもある。「われの星 燃えておるなり 星月夜」(高浜虚子)、「遊ぶ子の ひとり帰るや 秋のくれ」(正岡子規)、「いつまでも 忘れじ秋の この旅を」(柳原極堂)などの俳句や、松山赴任時の体験を元にした漱石の小説『坊っちゃん』が、物語に盛り込まれている。〈あ……雛歩は、自分のいまの状況と思い合わせ、その句に心が添うのを感じた〉、〈いま雛歩は、さぎのやでの数日を経験して、坊っちゃんにとって、あのお婆さんが、「帰る場所」だったんだ、と思い至った〉。ずっと前に亡くなった俳人や小説家の孤独と、雛歩の孤独が、「言葉」を通して共振する。雛歩は人と出会い、町を歩き、言葉に触れて、自分の経験と感覚で孤独を受け止める。〈自分が失われることが、ずっと怖かった。でも……包み込まれたぬくもりの中で溶けてゆくことは、決して自分がなくなってしまうことじゃない。包んでくれる相手と、一つになること。一緒に笑い、一緒に泣いて、守り合える、助け合えるということ……〉。雛歩はなぜ、さぎのやに来ることになったのか。一つひとつ丁寧に紡がれたエピソードを通して、読者の腑に落ちてくる。
そしてもうひとつ、十五歳の雛歩が生きている「今」の社会状況を、ありありと描きだしているところも、本書の魅力だと思う。
天童荒太さんは、三十年以上にわたり「この時代」と向き合って物語を創りつづけてきた小説家だ。一九九三年に文芸記者になった私(青木)は、同年の第六回日本推理サスペンス大賞の受賞者会見で初めて天童さんを見て、とても印象に残っている。都会的なミステリー作家と思ったが、それからの作家活動を見ると、天童さんが向き合っていたのは、人間という生き物が織りなす世界そのものだったのかもしれない。本書に登場する、さぎのやで生まれ育った飛朗とこまきが、一人前の弁護士や看護師になるよりも、もっと高いところに目標を据えているように。そして本書の物語は、とある遍路宿と、日本の地方都市を舞台にしながら、「今」の世界を広く捉えている。雛歩ら人間を生きづらくさせている事柄や閉塞感へのカウンターとなるべく、もっと広く、高いところへと眼差しを伸ばしていると思う。〈ただし……人間は、ほかの生き物より知恵はあるものの、欲もそのぶん深うございます。他人よりもっと楽な暮らしを、もっと多くの富を、と欲にかられれば、いとも簡単に正しき道を踏み外すでしょう〉。だから人間社会よりも広く高い空に向かって、のびのびと羽を広げる。内外の悲劇を見聞きしながら、それでも人間を信頼して、世界と向き合って描きだした物語を投げかける。
- date
- writer
- staff
- 文=青木 千恵(書評家)
- category