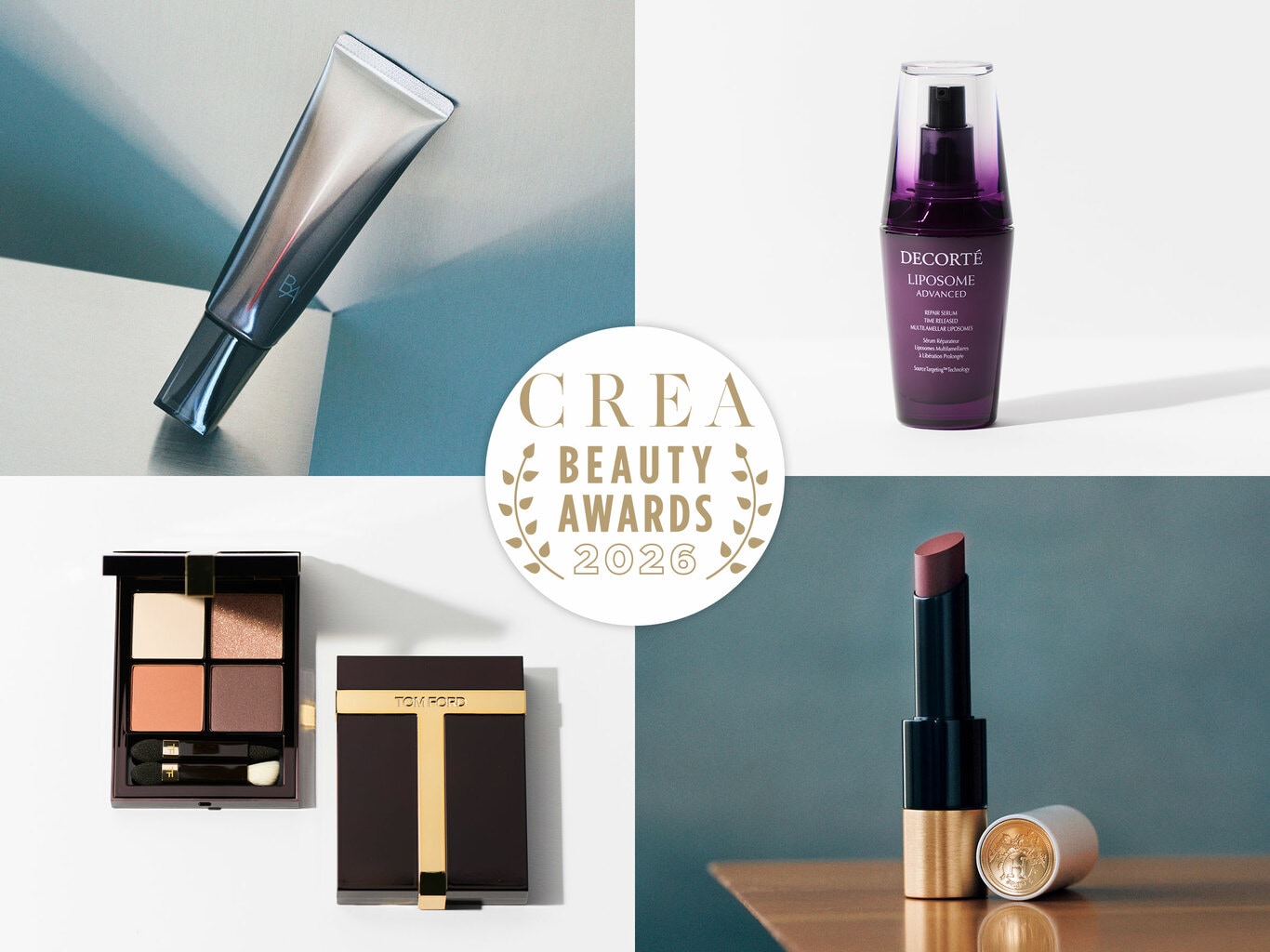「だって好きなんだもん」で終わらない音楽評論
近田 日本において、洋楽を伝える情報環境が激変するのは、やはり、ビートルズの登場以降になるんですか。
湯川 はい。情報に時差がなくなったのは、1964年の東京オリンピック以降のことですから。そして、60年代は、ビートルズの写真を載せた「ミュージック・ライフ」がどんどん右肩上がりに部数を伸ばしていきました。来日公演を行った1966年には、30万部とか40万部とかに達していたんじゃないでしょうか。
近田 星加ルミ子さんが編集長を務めていた、当時の「ミュージック・ライフ」の勢いはすごかったですもんね。

湯川 あの頃までは、洋楽のファンは圧倒的に女性が多かったんですよ。けれど、ビートルズが来日公演の翌年に発表したアルバム『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』あたりから風向きが変わって、批評性を求める男性のリスナーが読むような雑誌が登場するようになった。その象徴が1969年に創刊された「ニューミュージック・マガジン」でした。
近田 現在の「ミュージック・マガジン」ですね。やはり音楽評論家の中村とうようさんが中心になってスタートしました。
湯川 「だって好きなんだもん」っていうだけでは終わらない批評的なスタンスは、やっぱり時代のニーズに合っていたと思いますね。それ以前から、ボブ・ディランのような存在があったし、私も、エルヴィスを好む一方で、ジョニ・ミッチェルみたいな音楽も愛聴していましたから。
近田 1972年には、また毛色の違う「ロッキング・オン」が登場します。渋谷陽一たちが創刊したあの雑誌は当初、読者からの投稿が中心だった。
湯川 渋谷さんは、残念ながら昨年亡くなってしまいましたね。
近田 同い年で古くからの友達だった渋谷の死には、結構なショックを受けました。あいつ、アーティスト個人に対する興味は強いけど、音楽そのものについてはあんまり書かない。その点、作品至上主義の僕とは発想が違うから、よく喧嘩もしましたけどね。「お前のやってることは、アイドルが何食ってるのかとかに興味を持ってるようなもんで、女性週刊誌と一緒じゃないか」みたいにね(笑)。
湯川 私、渋谷さんにこんな風に言われたことがあるんですよ。「湯川さんはすごいミーハーだけど、ちゃんと評論もしているところがいい」って。あれは、すごくうれしかったですね。確かに、私はミーハーだけれど、その中に真面目な評論を交えてきたつもりでしたから。
近田 そのバランス感覚が秀逸なんですよね。