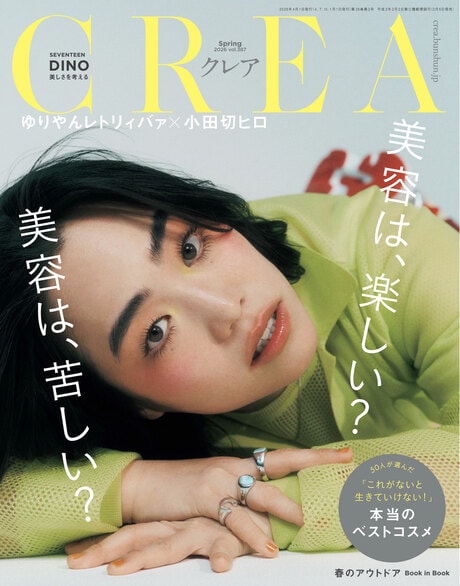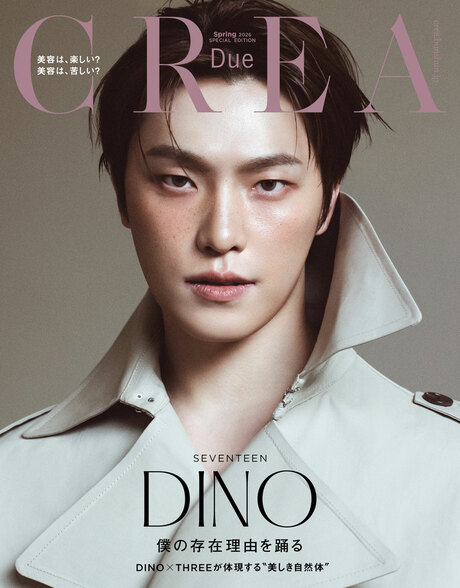言葉からイメージを広げるために

――大橋さんは文字の動かし方ではどんな部分にこだわりましたか。
大橋 CMやリリックビデオなど、文字が動く映像はたくさんありますが、言葉の意味や響きに合わせて文字を動かしているわけではなくて、音楽のリズムやメロディーが物差しになっていることがほとんどです。でも今回は映像を先につくっていったこともあって、文字を動かして言葉に運動性をもたせるって、どういうことなんだろうと、普段考えなかったようなことにも思いを巡らせました。
たとえば、予告編にもなっている冒頭の「望遠鏡の詩」は、あくまで僕の解釈ですが、亡くなった人への思いを感じさせる詩で、「骨」や「灰」という言葉が出てきます。その言葉を直接的に表現するというより、その言葉からイメージを広げたり、それぞれの体験を想起させられるような動かし方ができないか。そんなことを考えながらつくりました。
佐々木 そこまで考えていたなんて、さすが大橋君! とくに「望遠鏡の詩」は見ている人の心を掴む、重要なモーションだからね。
大橋 スターウォーズの導入みたいなね。「これはすごいのが始まったぞ!」と思ってもらえるものにしたかったから、あの部分だけで3週間かけました。かなり気合入ってます。
佐々木 やっぱりサイズ感かな。とくに僕は普段、書籍や大きくてもB1サイズくらいのポスターのデザインをしているから、大きい湾曲したスクリーンに映し出されたときにどう見えるか、その感覚がなかなか掴めなかったんです。
サンプルのテスト試写で、幅20mくらいのスクリーンに投映されたとき、思った以上に文字がデカくてスピードが速くて、これはマズいと。一気に不安になりました。
大橋 全然、目で追えなかったよね(笑)。
佐々木 読めないと意味がないので、スピードを落として、文字の級数を少しずつ下げていったり、フォントを調整したり。明朝体にすると、ここのはらいの部分がにじんじゃうけど、太い書体にするのは違うんだよな~みたいな作業を延々と繰り返して。それがけっこう大変でした。
その調整がある程度、いい感じになって、文字の見せ方や動かし方の方針が固まってきたところで、朗読は青柳いづみさん、音楽はNETWORKSさんにお願いすることに。僕としては、桃太郎みたいに仲間がだんだん増えていった感じで心強かったですね。

大橋 苦労というか難しかったのが、映像と音楽、どっちを先につくるかというところ。僕と佐々木さんとしては、プログラムのデザインや構成を進めるなかで、音楽が先にあったほうが絶対やりやすかったけど、NETWORKSさんは「いや、映像が先だよ」となって(笑)。
佐々木 そうだった。お互いヒントが欲しかったんだよね。結局、どうやって進めたんだっけ?
大橋 まず五藤光学研究所さん(※)に、詩に対してどの星座を映すといいか相談して、そこから星座の形と詩を組み合わせることで生まれる表現みたいなところを探っていった感じだったよ。
※光学式とデジタル式を融合した「ハイブリッド・プラネタリウム」など、先進的な映像技術を駆使して、プラネタリウムの制作や開発を手がける世界的メーカー。「詩のプラネタリウム」の制作協力や配給を行う。
佐々木 そうか、僕が全体の流れを考えて、大橋君が映像をつくって、それに音をつけていったんだった。
大橋 予告編だけ、つくっている途中で音源をもらって、あれがいわゆるデモ音源的な意味合いになったんだよね。
佐々木 たしかに。全体のプログラムのイメージとしても「望遠鏡の詩」を壮大に拡張していった感じだよね。青柳さんの朗読が骨組みとしてあって、それに合わせてリズムをつけていく部分もあったり、自然に寄り添う部分もあったり。文字と声と音楽がすごくいいマリアージュをしているというか。
ネタバレになっちゃうから、あんまり言えないけど、個人的に白鳥座のところがめっちゃ良くて好きなんです。いろいろ合わせる作業だけで5時間かけただけあって、とてもいい仕上がりになっています。
中川 わたしも白鳥座の表現はすごく好きですし、思い描いていたものより遥かに素晴らしいプログラムになって、ただただ感激しています。
文=熊坂麻美 写真=志水 隆