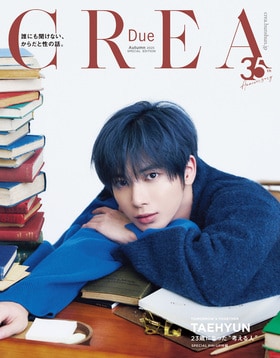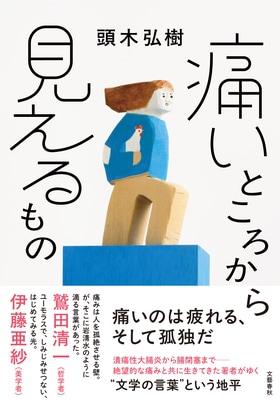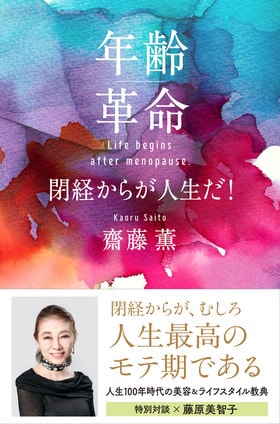ひらりさ ありがとうございます。別媒体でこの本の刊行にあわせて、『ロンドンならすぐに恋人ができると思っていた』の著者である鈴木綾さんと往復書簡の連載をしているのですが、綾さんもこの本に「友情の失敗」を書いたことを面白がってくれていました。〈「友達破局」の描写はポップカルチャーで御法度に等しい。だからこそ、「友達」と別れることになると、私たちは正しい言葉を持っていないし、心の準備が全くできてない。そもそもそれを友人と「破局」あるいは「別れ」と言ってもいいのか、私たちはためらう。〉と書いてくれて、確かにそうかもと思いました。
ジェンダーやセクシュアリティをめぐる自分自身の葛藤を書くうえで、「友達破局」レベルの泥沼になった友人関係を振り返り、その関係性のなかの、典型的な「友達」にも「恋人」にも定まらないあいまいさを私なりに言葉にしてみたらどうなるか、というのは意識したことかもしれないです。

キャッチーな言葉でラベリングすることの功罪
――明確な言葉で可視化される問題もあれば、ラベリングが反発を招くこともありますよね。「女」を取り巻くラベルを見つめ直す作業を通して、何かハッとしたことはありますか?
ひらりさ ネーミングが効いて問題が可視化されている例は本当にたくさんあります。特にフェミニズムは、これまで意識にものぼらなかった性差別を、言葉にすることで発展してきた歴史がある。セクシャルハラスメントだってそうですし、ここ最近だと、MeToo運動やマンスプレイニング、ギャラリーストーカーなど、挙げればいろいろなものがあると思います。
ただ最近は、「キャッチーな言葉でラベリングすることの功罪」もあるなと思っていて。『それでも女をやっていく』ウェブ連載時に最も反響があったのは、出身校である東京大学のことを「『ほとんど男子校』な世界」と書いた初回でした。このときは、反発もすごく多かったんです。2023年の私が読み返すと、「中高一貫男子校出身」をステレオタイプ化しすぎている点に反省はたしかにあった。やはり私自身がラベリングをしながら書いていることに起因する反発もあったのだろうと。「女」以外のラベル……ジェンダーやセクシュアリティを決めつける物言いから、毒親、メンヘラといったタームまで、とにかく断定的な物言いには気をつけて書いたんですけど、難しいですね。
2023.03.28(火)
文=ひらりさ、佐野亜裕美
撮影=平松市聖/文藝春秋