生きるために働かなければいけないという強迫観念が少女を追い詰めた

本作を手がけたチョン・ジュリ監督は、ソヒのたどる悲劇を生々しく描きながらも、ここでもうひとりの主人公を登場させ、別の視点から彼女の足取りを追い直す。もうひとりの主人公とは、ソヒの死の真相を調べに来た女性刑事ユジン(ペ・ドゥナ)のこと。
ペ・ドゥナが演じるユジンは、調査を進めるうち、コールセンターでの労働搾取とパワーハラスメントの実態を知り、怒りをつのらせていく。会社も、高校も、そして実習制度を管轄する教育庁もソヒの死に責任を持とうとせず、誰もが保身と無関心を貫くばかり。何よりつらいのは、ソヒの両親や友人たちもまた、彼女の声を聞く余裕がなかったこと。それぞれに社会のなかで疲弊し、ソヒの声にならない悲鳴を聞いてあげられなかった。

だから刑事のユジンは、そしてこの映画の監督であるチョン・ジュリは、なぜ誰も彼女を救えなかったのかと私たちに問いかける。仕事とはこんなものであっていいはずがない。これから社会に出ていく少女たちを、ソヒのような目にあわせてはいけない。何より、ソヒを救えなかったのは私たち大人全員の責任だ。その怒りの声を、私たちはどう受け止めるべきなのか。若者たちを取り巻く社会の現状を見つめるのが、この映画の一番の目的だ。
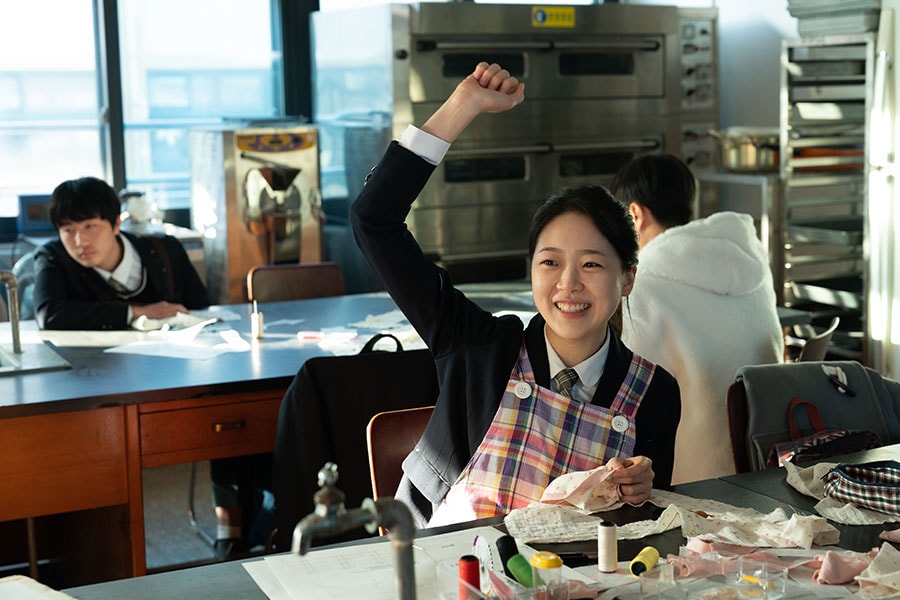
それは、チョン・ジュリ監督の前作であり、同じくペ・ドゥナが主演した『私の少女』(2014)に通じる主題でもある。『私の少女』でも、ぺ・ドゥナは、ある悲惨な家庭環境に置かれた10代の少女を救う女性刑事として登場する。彼女は迷わず少女に手を差し伸べるが、やがて、それが職務としての行為なのか、私情が絡んだ行動なのかと逡巡する。だが最後には、理由などどちらでもいい、という結論に至る。大人は子供を守らなければいけない。それが大人としての職務であり、人としての義務なのだから。
たしかに多くの人は、働かなければ生きてはいけない。でも「働く」とは、これほど過酷なものでしかないのか。金を稼ぐため、ひたすら何かに耐えながら自分を酷使するだけではなく、もう少し自由に、「働く」ことへの希望を見つけることはできないのだろうか。
文=月永理絵




























