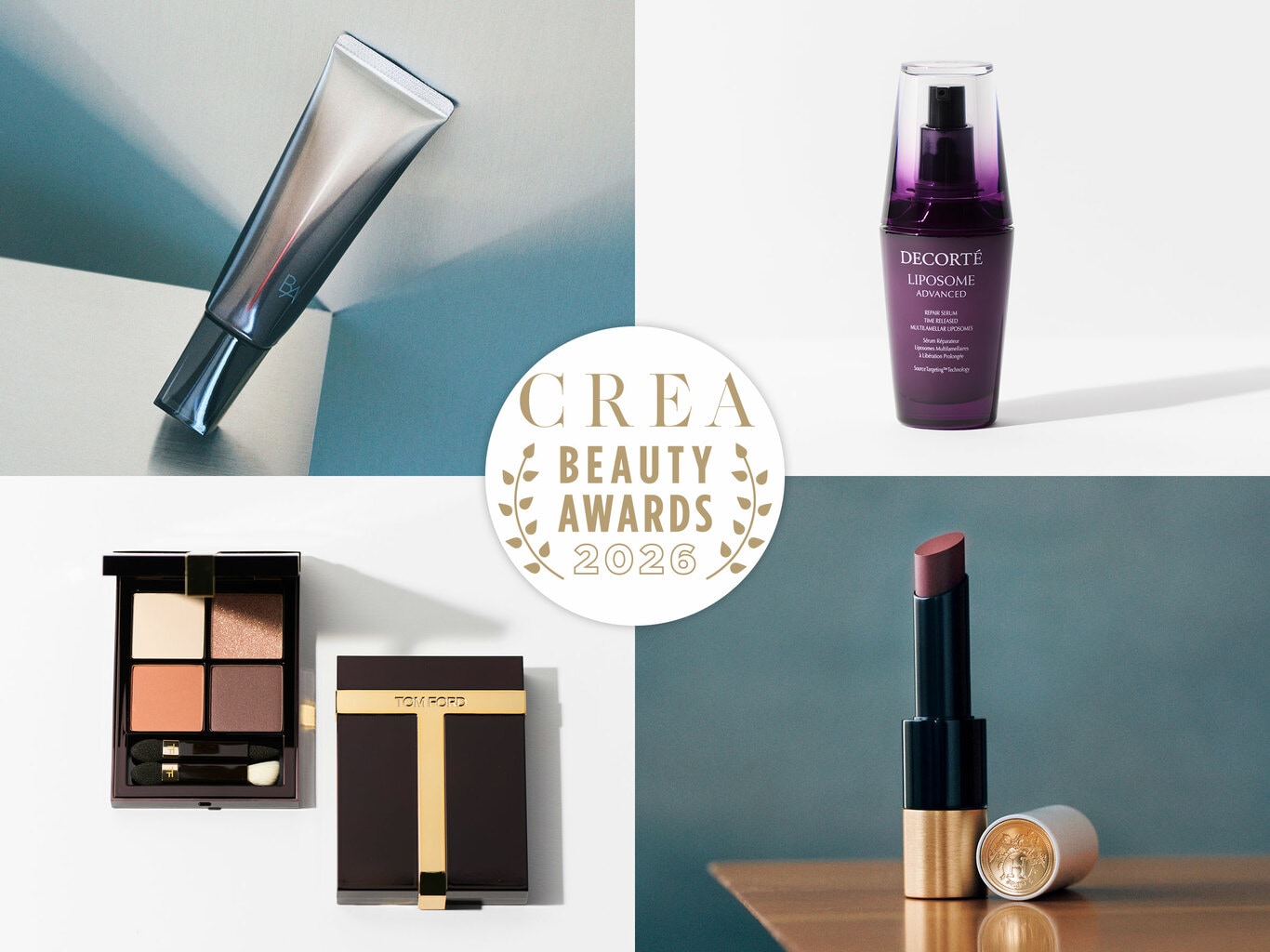コロナに関しての記述がないわけではない。話題としては、当然扱われている。掲載号と照らし合わせてみると、二〇二〇年五月二十二日発売の六月号が「散歩道入門 コロナで大躍進を遂げた運動」でコロナの初出。「コロナ禍」という言葉がメディアで使われ始めたのが二〇二〇年二月から三月あたりらしいので、辻褄はあっている。
エッセイ界(というものが存在するのであればの話ですが)の末席を率先して汚すタイプの欲深い私なら、災いの足音が聞こえていたであろう四月二十二日発売の五月号で、我先にとコロナに触れていたと思う。一方、東海林先生のエッセイは「令和の“チン”疑惑 電子レンジと安倍内閣」である。もはや超然としている。いや、こっちも大事なことなので、世間に背を向けスカしているわけではないのだろうけれども。
コロナについての記述があるにもかかわらず、私がプレ・コロナとポスト・コロナの境目に気づけなかったのは、先述の通り、東海林先生が飄然と暮らし続けていたから。つまり、東海林先生の生活を描く態度がブレなかったからだ。どれほどのことが起こっても、一定の距離を保ち世間を眺める筆致には美学がある。社会の諸問題から目を離さずに、しかし一定の距離を保ち続けるには胆力が必要で、簡単なことではない。私なんか、時代のムードに合わせてコロッと文体を変えた。
戦争経験者は強いな、と思う。東海林先生は昭和十二年生まれで、私の父親は昭和十三年生まれ。どちらも戦中派の最後と言えよう。すえたご飯を食べた経験を持つ世代。
世代で十把一絡げに語ることが忌諱されがちな昨今だが、日本が過去に経験した最悪の禍を生き抜いてきた人のへこたれなさは、良くも悪くもすさまじい。良い例が東海林先生。悪い例を知りたかったら、昭和十二年生まれの内閣総理大臣経験者を検索してみることをおすすめする。いや、三人いるな。私が言いたいのはオリンピックのほうです。
第二次世界大戦を幼少期に経験した諸先輩のユーモアに助けられたことは、一度や二度ではない。困難が迫ってきたときほど、それを面白がる。やせ我慢の冷笑とは一線を画すものだ。その余裕はどこからくるのか、戦中派の末席を汚す我が父親に尋ねたら、価値観が一夜にしてひっくり返ったからかもしれないと言っていた。
文=ジェーン・スー(作詞家、コラムニスト、ラジオパーソナリティ)