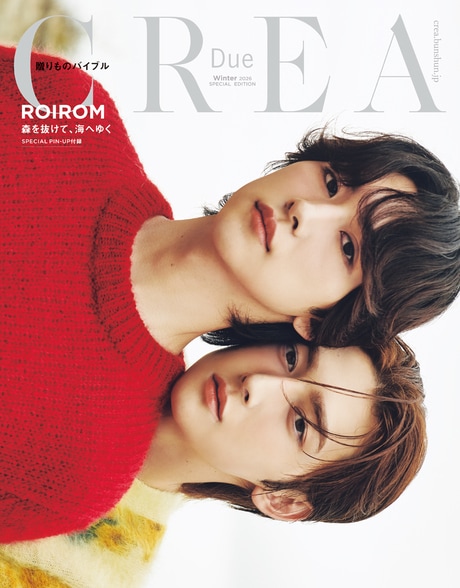脚本家を悩ませた最大の難事
筆が乗った背景には、『国宝』は現代劇の装いを取りつつも、ひと昔前の題材を扱った作品だからだと話す。
「この物語は昭和39年から始まりますが、昭和中期の話は現代劇ではなく、もはや時代劇なんです。そういう意味では自由に書き進められました」
映画では、歌舞伎舞踊が魅力的に描かれる。中学生の喜久雄が長崎の料亭で舞う『積恋雪関扉』、目に鮮やかな『二人藤娘』、そして可憐な『二人道成寺』。喜久雄は渡辺謙演じる花井半二郎の後ろ盾を得て出世を遂げていくが、舞踊がその中心に描かれる。
「それでも歌舞伎演目についての説明や解説を入れられないのは不安がありました。ただ、李監督は台詞で説明するのではなく、お芝居の説得力で見せたいという考えでした」
説明を省く以上の難事が、吉沢亮と横浜流星という俳優ふたりが挑んだ歌舞伎舞踊を、映像として成立させなければならないことだった。幼いころから舞踊の研鑽を積んだ歌舞伎役者とはワケが違う。
しかし、製作陣の思いをふたりの役者が昇華させた。奥寺さんは想像していたよりも、歌舞伎のシーンがたっぷりあったことに驚いたという。
「『こんなに観せてもらって、いいのかしら?』と思うくらい、贅沢に感じました。それを成立させたのは、監督、撮影、俳優のチームワークです」

奥寺さんには他の企みもあった。舞台から見える風景を脚本に入れることである。
「舞台の向こう側が見たいと思っていました。実際に映画を観て、『役者さんからは、こう見えているんだな』ということがわかって目が離せませんでした」
映画では舞台上でカメラが躍動する。まるで、観客が舞台に紛れ込んでしまったかのように。特に『二人道成寺』の大詰めでは、花子が恋に破れ、執念が蛇体となって「鐘入り」するが、映画ではこの鐘の裏でどんなことが起きているのかが描かれる。これは歌舞伎を観慣れたファンにとっても新鮮な映像だ。
物語が凝縮された『曾根崎心中』
そして物語の展開上、重要な意味を持つのが『曾根崎心中』だ。原作での上演シーンは一度だけだが、映画では二度。一度目は俊介の父・半二郎が事故に遭い、お初の代役に実子の俊介ではなく喜久雄を指名したことで、人間関係に決定的な亀裂が入る。そして二度目は、俊介がお初を演じ、喜久雄が徳兵衛に回る。
「劇中の役と、喜久雄、俊介の心情が絡み合っていくところ、このあたりは脚本では書き込みきれないんです。あそこまで物語に引き込まれたのは、おふたりの演技によって、役者の人生が芝居に投影されていたからだと思います」
『曾根崎心中』は100分ほどの演目だが、映画では物語が凝縮されている。
「現代の人が歌舞伎を観ると、どうしてこんなことで心中しなきゃいけないの? と疑問を抱くかもしれません。ダイジェスト的に話が展開する映画では、監督の演出力によって演目が魅力的になったと思います」
映画『国宝』のおかげで、歌舞伎の『曾根崎心中』の上演を望む声が増えた。それほどインパクトがあったのだ。
そして映画のオリジナリティを強く感じるのは“国宝”となった喜久雄が最後に演じるのが『鷺娘』であることだ。
- date
- writer
- staff
- 文=生島 淳
- category