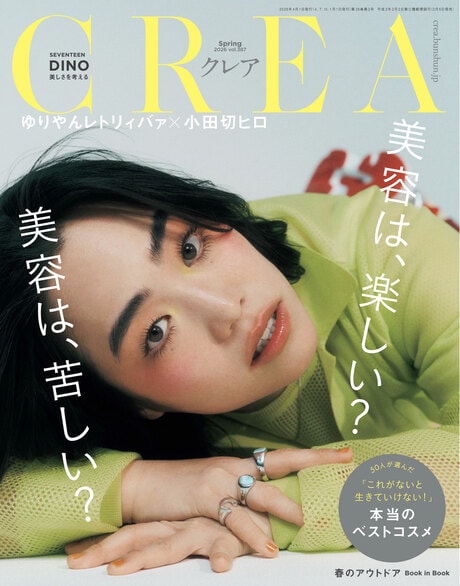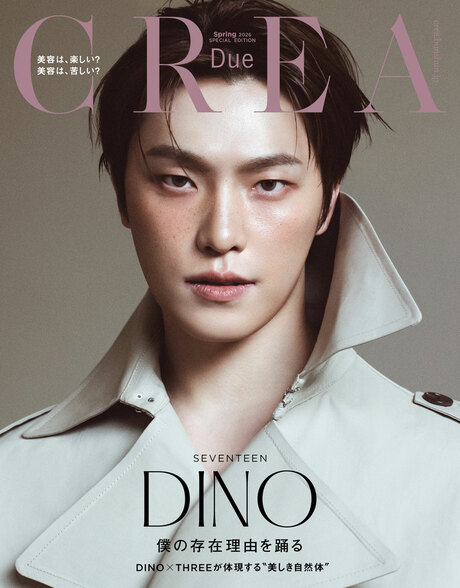坂東玉三郎が演じる六条御息所と、市川染五郎が演じる光源氏。二人の出会いが生む舞台上の化学反応は、まさに『源氏物語』の世界そのものだった。歌舞伎という表現が、世代や年齢差を超えて、光源氏と六条御息所という永遠の恋人たちを現世に甦らせる。その奇跡の舞台が、今度はスクリーンに登場する。
昨年10月、歌舞伎座で上演された『源氏物語 六条御息所の巻』がシネマ歌舞伎として映画館に蘇り、観客は息をのむ美と情念を間近に体感できるようになった。玉三郎さんには、作品への思い、そして共演した染五郎さんへの言葉を聞いた。
“嫉妬”という感情の象徴ともいえる役

——『源氏物語』に登場する紫の上や葵の上などいろいろなヒロインの中から、六条御息所を選んだ理由をお聞かせください。
かつて『源氏物語』の現代語訳を手がけられた円地文子先生とお話しした時に、「六条御息所が一番物語になりやすい」とおっしゃっていたのを覚えています。
確かに「空蝉」だと光源氏が女性のもとを訪ねてもいなかったので物語になりませんし、第十帖の「賢木」の野宮神社へ行く場面を入れることも考えたのですが、葵上が取り憑いて殺されてしまうので、そこで幕切れになってしまうとお客様がいい気持ちがしないと思いました。
六条御息所は“嫉妬”という感情の象徴ともいえる役ですが、それが芝居として成立しやすいのだと思います。しかし“嫉妬心”という感情は誰しもが心の奥に秘めているもの。
あの時代の女性は六条御息所だけでなく誰しも、“私のところに来てくれない”という思いを抱いていたのではないでしょうか。それを代表した存在でもありますし、舞台上で表現することで、お客様の琴線にも触れ、どこかで浄化されるような体験になればと思いました。

——『源氏物語』を歌舞伎として舞台に甦らせることには、どのような魅力があるとお感じですか? また、これまでの上演史の中で心に残っている出来事があれば教えてください。
『源氏物語』を歌舞伎化するのは、とても難しいことです。だからなかなか成功していませんが、過去で一番ヒットしたのは十一世團十郎(当時、九代目市川海老蔵)さんが舟橋聖一脚色の『源氏物語』で光源氏を演じた時(1951年3月歌舞伎座)だと思います。
まだ『源氏物語』が舞台で描かれていない時代に、十一世がその美しさで観客を魅了し、それがきっかけで歌舞伎が復活したのだと思います。
——六条御息所をどのような人物として捉えていますか? 演じるうえで、これまでに経験されたお役の視点などが投入されているのでしょうか。
私は地唄舞『葵の上』を踊った経験があることから、六条御息所はその延長線上にあるので、すっと入っていけました。
実のところ六条御息所は代々生き霊になる血筋だそうですが、彼女は自分が怨霊になっていることを知らない。その自覚がないんです。(葵の上を憑り殺してしまうことは)許されることではありませんが、気づいていないことが許されるところなのではないでしょうか。
私が六条御息所を体現すると、女方として演じてきた桜姫や『四谷怪談』のお岩とか、自分が経験してきたものが出てくるのかもしれないですね。