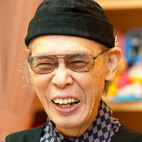放送中のNHK連続テレビ小説「あんぱん」は、アンパンマンの生みの親やなせたかしさんと、妻の暢(のぶ)さんをモデルにした物語です。ドラマをきっかけに、改めてやなせさんの作品を見返しているという方も多いのではないでしょうか。
やなせさんのもとで働き、晩年まで親交があったノンフィクション作家の梯久美子さんが書き下ろした『やなせたかしの生涯 アンパンマンとぼく』より、誰もが知る名曲「てのひらを太陽に」が生まれた背景をお届けします。
心はこんなに落ちこんでいるのに……

苦しむ嵩(たかし)に追い打ちをかけるように、漫画の世界に決定的な変化がおとずれる。手塚治虫の登場によって、漫画界の地図が大きく塗りかえられたのだ。
一九四七(昭和二十二)年に大阪の出版社から描き下ろし長編『新宝島』を刊行した手塚は、当時から天才の呼び声が高かったが、一九五〇年代に入ると「ジャングル大帝」「リボンの騎士」などを雑誌に長期連載し、絶大な人気を得る。
大阪から上京した手塚が住んだ椎名町(しいなまち)(現在の豊島区南長崎)のトキワ荘というアパートには、あとに続く新しい才能が集まり、漫画の世界は長編漫画が主流になる。昔ながらの四コマ漫画を描いていた嵩の居場所はますますなくなっていった。
そんなある日のこと、嵩はいつものように深夜まで起きていた。仕事はとっくに終わっていたが、机に向かっていないと、自分は世の中から必要とされていないという思いに押しつぶされそうになるのだ。
嵩はふと、机のそばにあった懐中電灯を手にとってスイッチを入れ、光にてのひらをかざしてみた。すると、指と指のあいだが光に透けて、きれいな赤色に見えた。
「何だろうこの色は……ああそうか、血の色が透けて見えているんだ」
心はこんなに落ち込んでいるのに、からだには赤い血がいきいきと流れている。生きているということの、たしかな証拠がそこにあった。
この夜、一篇の詩が生まれた。
ぼくらは みんな生きている
生きているから 歌うんだ
ぼくらは みんな生きている
生きているから かなしいんだ
てのひらを太陽に すかしてみれば
まっかに流れる ぼくの血しお
てのひらを透かしてみたのは懐中電灯だったが、「ここは太陽のほうが詩らしくなるな」と考えて太陽にした。詩はこう続く。
みみずだって おけらだって
あめんぼうだって
みんなみんな 生きているんだ
ともだちなんだ
このとき独立からすでに八年がたち、嵩は四十二歳になっていた。
みみずも、おけらも、あめんぼうも、人から注目されることはない。でも、それぞれの場所で、自分の命を生きている。光の当たることのない小さな生きものたちが、自分に似ているように思えた。
- date
- writer
- staff
- 文=梯 久美子
- category