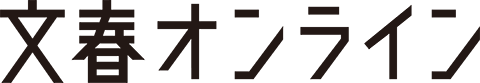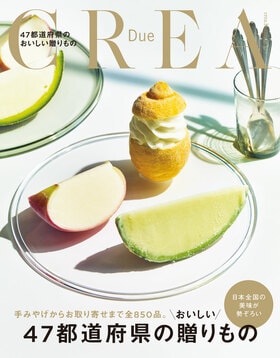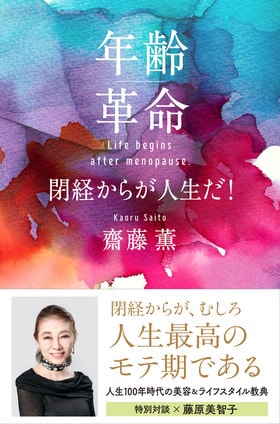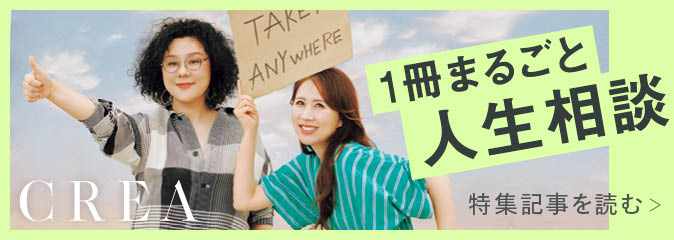最近は史実との相違の指摘し合いが盛んである。ドラマをきっかけに知識を得られること自体は悪くないのだが、本来、期待されたのは、史実と違う描写の是非ではなく、深い議論を交わすことだ。おそらく寅子だったら、なぜ史実を変えたのか、その理由を追求し、異なる意見をもつ人と話し合っていくだろう。知識とは議論するうえでの材料に過ぎない。
『虎に翼』には、よく学ぶこと、気になったことはとことん議論することの喜びがある。リーガルものとは、本来のSNSのよき使い方のできる格好の題材だったのである。これまでの朝ドラは主人公がとんとん拍子に結果を手に入れ、そこまでの過程が省略されていると感じることをよく指摘されてきた。リーガルものは結論を導く過程が醍醐味。つまり、待ちに待ったドラマなのである。その点も新しさだ。
夫に見下され、笑って受け流してきた「梅子」の姿
知的な議論を好む層、語る言葉を持つ女性たちがいっせいに、『虎に翼』を支持している。優秀で、もしかしたら世の中を変えられたかもしれない人たちが前例や偏見によって、可能性を得られず、口のなかを切るほど口惜しい気持ちを抱えていたのかもしれない。

例えば、寅子の学友の梅子(平岩紙)のように、学びたい意欲があり、実際優秀なのに、夫に見下され、それを笑って受け流し、折り合いをつけてきた人がいる。その人たちが正当に評価され、平等に土俵に上がり、才能を発揮することで、あとに続く人をも励まし、引っ張っていけるのではないか。『虎に翼』はまずそこからはじめようという決意が感じられる。
離婚を考えている梅子は、現時点では法律で親権が妻には認められていないが、「いまはだめでも糸口を必ず見つけてみせる」と決意を語る。主題歌の歌詞に「100年先」とあるように、未来のために、いま、ほんの小さな穴を開けていく。いまいる仲間との連帯のみならず、過去から(三淵さんという先例)のバトンを受取り未来へ渡す、時間の流れのなかでの連帯をも描こうとしているのも『虎に翼』の新しさだ。

30代の女性作家・吉田恵里香の起用によって、これまで昭和の歴史もリスペクトしながら、いまの若者が見ても楽しめるように現代的な価値観で描こうと試行錯誤を繰り返してきた朝ドラがようやく勘所を見つけた第一歩のようにも感じている。エンタメ連ドラから、社会問題を題材にしたドラマまで、長いものから短いものまで、原作ものからオリジナルまで手掛けてきた作家の懐の深さが、寅子の懐の深さと重なって見える。
2024.05.13(月)
文=木俣 冬