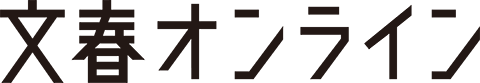秩父党の中心だった畠山重忠が消え、義信以来、武蔵国に影響力を保持してきた平賀氏のトップである朝雅が消えたことで、武蔵国は空白地帯になったのです。義時はそこに弟の時房を守護として送り込みました。
義時はそれまでの「江間」から「北条」に名乗りを変えます。『吾妻鏡』は、ここに北条氏の歴史は始まったと書き、義時を北条家の初代と位置付けます。
『吾妻鏡』編纂者たちの苦労
今日の目で見て興味深いのは、畠山重忠の乱から、時政失脚までを記した『吾妻鏡』の編纂者たちの苦労です。
この時代、子殺しは正当化できても、親殺しはとうてい容認できないことでした。義時の行った時政の追放劇は、政治的には限りなく親殺しに近い。当時の感覚からすると、これは北条氏の恥になるのです。
『吾妻鏡』は、鎌倉武士を率いるリーダーとして北条氏を讃える歴史書です。そこで義時を初代とし、時政を非道な陰謀を企てる完全な悪者として切り捨てようということになったのだと考えられます。
そのためにも、時政が殺した畠山重忠は、武士の鑑であり関東を代表する武士でなければなりません。そして、彼を陥れた時政がいかに狡猾な人物であるか、最後まで重忠を助けようとした義時がいかに素晴らしい武士であるか、と対比させて、時政の追放は鎌倉武士としてやむを得ないことであったというストーリーを仕立てていったのです。
いまさら遺児に出てこられても困ると考えたのでは
それでは、義時が畠山重忠を殺したことを後悔していたかといえば、怪しい限りです。畠山重忠の乱から8年後の建暦3(1213)年、亡き畠山重忠の末っ子の大夫阿闍梨重慶が日光のお寺で匿われていたことがわかります。
この重慶が兵を集めて謀反を企てているというので、義時はすぐに兵を差し向けて殺してしまうのです。本当に重忠のことを後悔していたのなら、他にやりようがあったでしょう。謀反といっても「牢人を集めて、祈禱をしていた」程度の容疑でしたが、それに対し実朝が「重忠は無実の罪で殺されてしまった。その息子に謀反の容疑があっても、鎌倉に連れてきて、申し開きをさせてからでも良かったのではないか」と使者を通して伝えたところ、重慶の首を持ってきた長沼宗政が「そんなことを言われるのでは、今後、誰が忠節を致しましょうか。これは将軍家(実朝)の御過失です」と逆ギレした、と『吾妻鏡』は書いています。実朝の言うのももっともですが、義時らからすると、もう畠山領はみんなで山分けしてしまったし、いまさら遺児に出てこられても困ると考えたのでしょう。
2022.12.31(土)
文=本郷和人