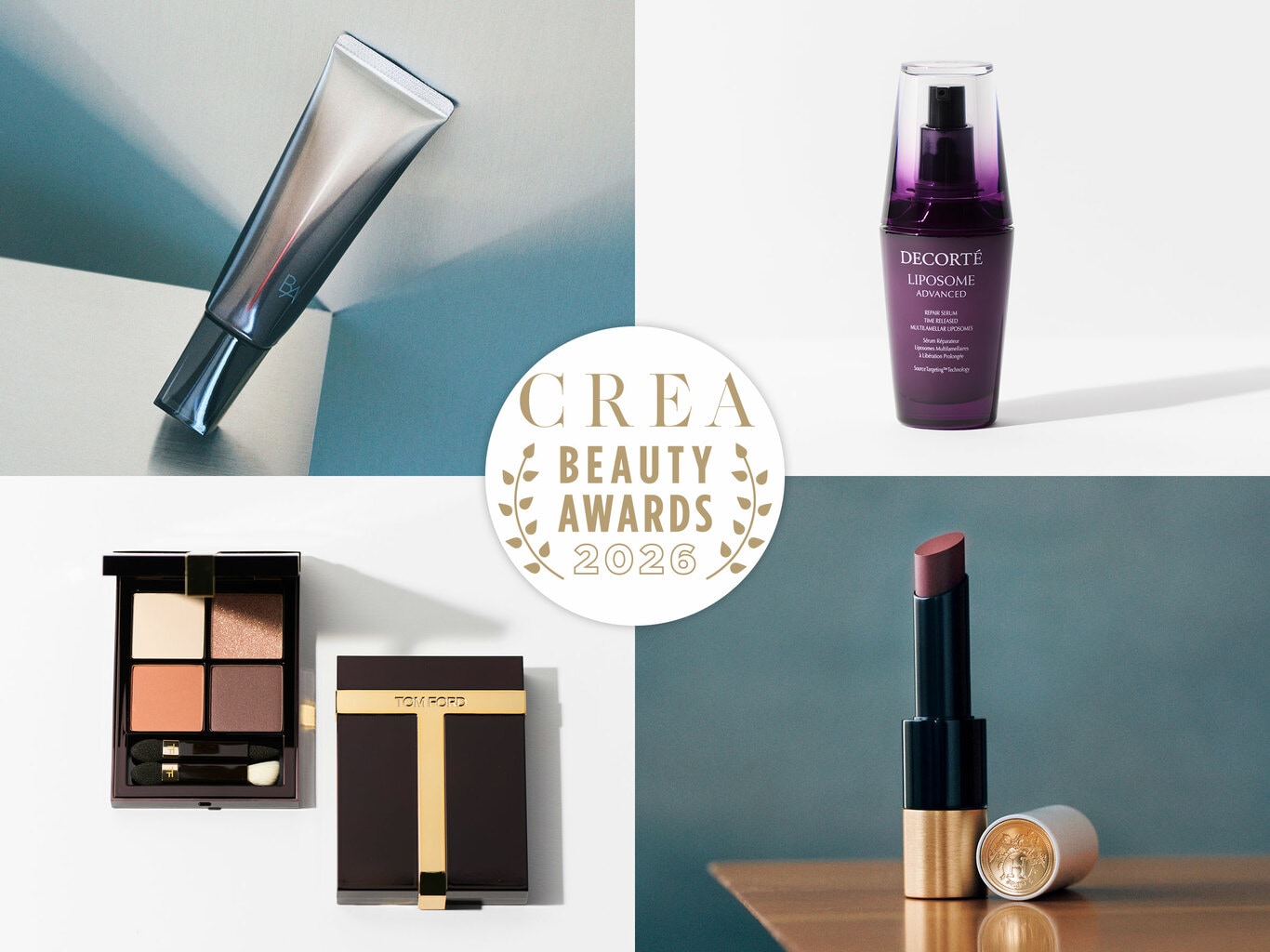子どもの頃のわくわくを蘇らせる音楽フィルム
◆オープンカテゴリー:アグスティナ・サン・マルティン×リン=マニュエル・ミランダ

あらゆるカテゴリーを含むオープンカテゴリーのメントーは、リン=マニュエル・ミランダだ。トニー賞を受賞したミュージカル『ハミルトン』と『イン・ザ・ハイツ』の制作者であり、ディズニーの長編アニメ『モアナと伝説の海』、『ミラベルと魔法だらけの家』でも楽曲を手がけたことで有名だ。きっと誰しもが彼の音楽を聴いたことがあるだろう。
役者としても『ハミルトン』では主演を演じたが、実際の彼自身もまるでステージの上であるかのようにリズミカルな口調で話し、話しながらも椅子から跳び上がりそうにエネルギッシュだ。
そんな彼がプロトジェとして選んだのは、アルゼンチン出身の映画監督アグスティナ・サン・マルティン。当初から、さまざまな人種のアーティストに門戸を広げ、チャンスを作ろうと決意していたという。
「多様な作家がいればいるほど、より多様なストーリーが生まれ、結果としてより良い映画が生まれるのです」
2020年3月、ミランダは初の長編映画、作曲家のジョナサン・ラーソンの生涯を描いたミュージカル映画『チック、チック…ブーン!』に取りかかっていた時期だったが、新型コロナウイルスが猛威をふるって、撮影が中断。その後、安全規定に沿いながら秋になって完成させた。
残念ながらサン・マルティンはミランダの撮影現場には立ち会えなかったが、オンラインで撮影を見学することができた。
「アグスティナには、『あなたは私より多くの映画を作ってきている』と言ったんです。結果として、私が初めて映画を監督する過程で、彼女は貴重な相談相手になってくれました」とミランダはふり返る。

ミランダは、サン・マルティンの最初の印象を「詩的な感性の人」だといい、一方サン・マルティンは「彼は常にエネルギッシュな人」といい、二人は最初から話がつきなかったと話す。ミランダがサン・マルティンに貢献したのは、おもに思考プロセスをサポートしたことだという。
「ただ質問をするだけです。たとえば『自分の中でどのようなイメージを持っているのか?』 『伝えたいことは何か?』。 外部の立場で見て、伝えられることは、目標への到達度です」
一方、サン・マルティンにとっては、今回のプロセスを経て、インディペンデント映画を離れ、より物語性のある映画を作りたいと思うようになったという。
「映画作りでは資金繰りが大変なのです。そのため、ヨーロッパのインディペンデント映画祭で賞を取ることを目指して作っていると、賞に向けてシリアスな作品を作りがちでした」
彼女のこれまでの作品は実際にシリアスなものだった。カンヌ映画祭で受賞した短編映画『モンスター・ゴッド(Monster God)』や、初の長編作品『トゥ・キル・ザ・ビースト(To Kill the Beast)』など、画面は意図的に暗く、ミステリアスで難解な作風だった。
「でも今回ロレックスのプログラムで映画を撮れることになって、そうした心配がなく、好きなものを撮ることができました。それで自分にとって、映画がどんなにわくわくするものか、子どもの頃に『ジュラシック・パーク』を見て椅子から跳び上がりそうになったのを思い出したんです」
「それこそが大事なこと」とミランダがうなずく。「10歳の時の自分でも、16歳の時の自分でもいい。その時の自分がわくわくしていたことに、まっすぐ向かうのが、創作では大事なのです」

そして今回製作され、ワールドプレミア上映された作品が、『チャイルドフッド・エコーズ(Childhood echoes)』だ。日本語でいえば「子ども時代からの残響」といった意味だろう。これはドキュメンタリーと幻影がユニークにハイブリッドとなった作品だ。冒頭から夢幻的な雰囲気で、モノクロの夜空に浮かぶ顔が、音楽の思い出を語り始める。
「あなたにとってのお気に入りの曲はなに?」と友だちや見知らぬ人、そしてリン=マニュエル・ミランダに行ったインタビューから始まり、曲から呼び起こされる思い出について尋ねていく。映像は、浮かぶ雲に投影され、オリジナルのスコアと組み合わされ、音楽体験について考察していく。
人が子どもの頃から大好きな音楽と、それにまつわるイメージを、ドキュメンタリーともミュージカルとも違う手法で描いてみせたのが斬新だ。
サン・マルティンは現在、ある大きな映画のプロジェクトに関わっているという。「新しい道に進むにあたり、ミランダと話せたのはすばらしい経験でした」と話す。
彼女がここから巣立ち、今後さらに映画界で活躍するのは間違いない。
文=黒部エリ