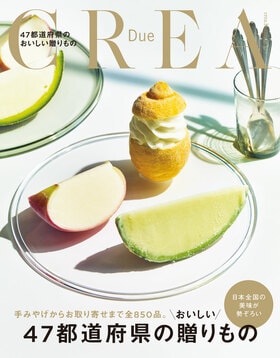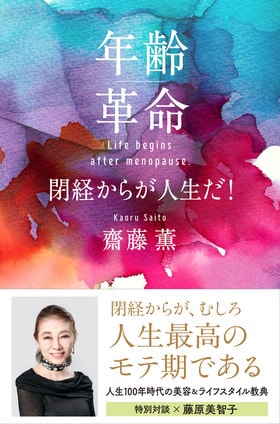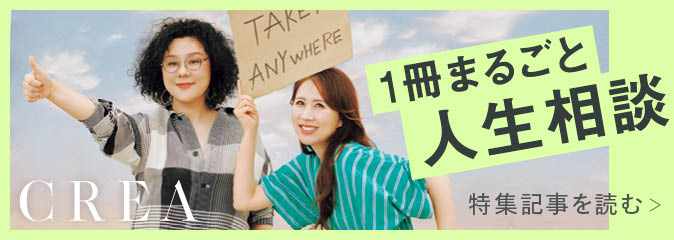後免町は江戸時代に人工河川の開削で拓かれ、舟運で発展した。明治維新後も鉄道が交差する交通の要衝となり、寛さんはまちの将来性を見越して医院を開いたようだ。
母が再婚したことも知る由もなく……
やなせさんは弟を追いかけるようにして寛さんに引き取られた。母が再婚することになったからだ。ただ、弟のように養子ではなかった。
通っていた小学校も2年生の1学期に高知市立第三尋常小学校(現在のはりまや橋小学校)から、後免野田尋常小学校に転校した(当時は旧後免町と旧野田村の組合立)。1926(大正15)年のことだ。
高知県の県紙『高知新聞』にやなせさんが寄稿した連載『人生なんて夢だけど』に当時の事情を説明した部分がある。
母は伯父としばらく話し合った後、ぼくに「嵩(たかし、ぼくの本名)はしばらくここで暮らすのよ。病気があるから伯父さんに治してもらいなさい」と言ったのです。ぼくはすごく素直な子どもだったから「はい」と答えました。そして書生部屋のようになっていた部屋で柳瀬家の末弟である中学三年生の正周叔父と暮らすことになります。
埃っぽい道を白いパラソルを回しながら母が遠ざかっていった時にも、別に涙は出ませんでした。母が再婚したことは知る由もなく、いつの間にか伯父の寛と伯母のキミをお父さん、お母さんと呼ぶようになり、旧制の県立城東中学校(現・追手前高校)を卒業するまで、後免町で表面的には平和で安定した歳月が過ぎていきます。
「しばらく」そこで暮らしても、母は迎えに来なかった。やなせさんは18歳までの約10年間、伯父夫妻宅の医院で育つことになる。こうして後免町はやなせさんの実質的な故郷になっていく。
人間関係を整理しておくと、やなせさんの父は三兄弟だった。長兄が後免町で柳瀬医院を開いた寛さん、次が亡くなったやなせさんの父清さん、末弟がやなせさんと一緒に書生部屋で過ごした正周さん。

やなせさんの弟の千尋さんは、父の兄・寛夫妻の養子として奥の部屋で寝た。
やなせさん自身は「子ども心にも伯父夫婦に世話になっているという負い目があり、『お父さん』と呼んではいても甘えることもなく、何かをねだることもなかったのです」と連載に記している。「年がら年中泣いてばかりでした。なぜあんなに悲しかったのか、よく解りません」とも書いた。
2025.07.14(月)
文=葉上太郎