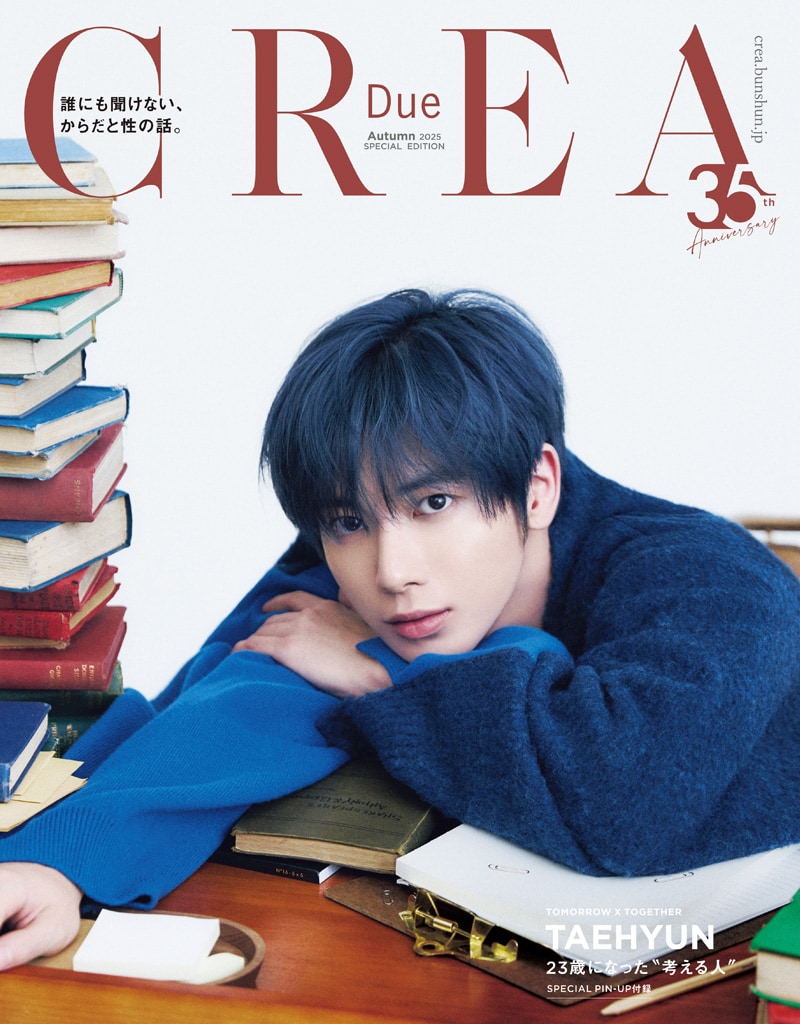やがて大学院を休学したJさんは研究者になることをあきらめ、臨床の道に進むことにし、私の勤務していた大学病院の精神科に入局した。Jさんは飾り気のない朴訥な人柄だったし、知識の量は豊富だったが、対人関係に大きな難があった。たとえば、受け持ち患者と面接しているとき、Jさんは微に入り細に入り情報を得ようとして、質問魔になってしまうのである。患者を問い詰めて、泣かせてしまったこともあった。
もちろん、治療の際にそういった詳細な情報収集が必要な場合もあるが、たいていは相手の様子を気遣いながら、面接をすすめていくものである。相手の表情や言葉のニュアンス、あるいは沈黙などにも注意しながら、どの程度まで聞いてもいいものか推し量りながら会話を続けていくのが通常である。これは日常のコミュニケーションでも同様である。だが、Jさんにはそういった「さじ加減」ができなかった。
それでも何年か研鑽を重ねる中で、彼にも普通のコミュニケーションがどういうものか次第に理解できてきたようで、最近は苦労しながらも地方の公立病院の医師として仕事を継続している。
発達障害の人たちの驚異的な「底力」
ただし本書で描きたかったのは、こういった高学歴、高機能の人たちの挫折のプロセスだけではない。彼らの「復活」と「再生」の物語である。この点には個人的にもたびたび驚かされることがあった。多くの精神疾患において、症状が回復したとしても、病前のレベルにまでもどらないことが多い。うつ病を例にあげると、会社や公的機関のトップエリートだった人でも、いったんうつ病を発症すると、かなり回復した場合でも、病前の80~90%程度の力しか発揮できないことが多い。
彼らは瞬間的に100%かそれ以上の能力を見せるかもしれないが、それは短時間しか持続できない。比喩的な表現になるが、蓄えていたエネルギーがすぐに枯渇してしまうからだ。そこで無理を重ねると、再発を繰り返すことになる。
- date
- writer
- category