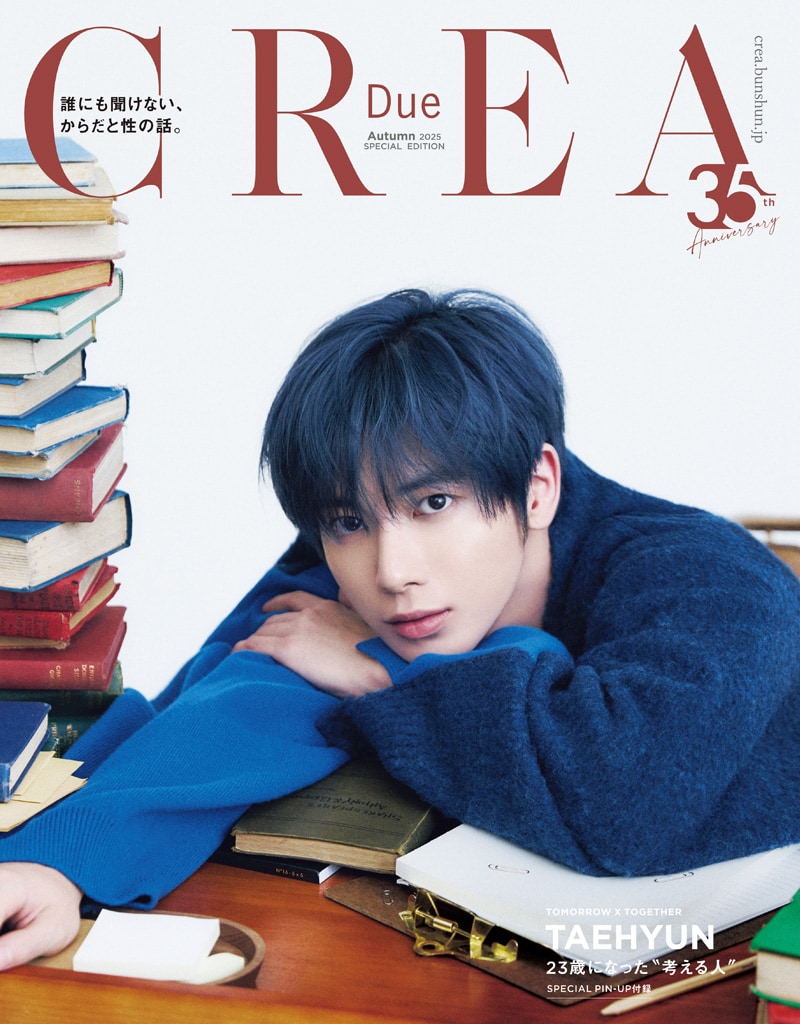高学歴、高機能の人には、難易度の高い「課題」や「業務」が割り振られやすい。これも、「脱落」の原因になる。高い能力を持っていても、発達障害の特性を持つ個人は、興味を持つ事柄と持てない事柄に対するモチベーションがまったく異なるためである。
さらに、彼らは人々を「管理」する立場になることが多い。学校ではリーダーとなることが期待され、会社では、管理職となって昇進していくことが要求される。けれども発達障害の特性を持つ人たちは、こういった調整が不得手である。「相手の気持ちを考えながら」とか「他の人たちはどう反応するだろうか」などと予想を立てながら、状況に応じて対応を修正していくことは、もっとも苦手にしているのである。
勉強や業務の能力は十分であったとしても、ここで「挫折」が始まりやすい。
正確なデータは存在していないが、高学歴の人の発達障害の比率は明らかに高いものがある。以前、東京大学の保健管理センターが東大生を対象に発達障害の比率を調査したことがあったが、結果が高率過ぎたため、公表されなかった。また、高学歴、高機能の人に対する要求は過大になりやすく、不適応が生じやすい。
ある高学歴医師の挫折
挫折と再生ということで、思い浮かぶ人がいる。全国的に有名な中高一貫の進学校に在学していたJさん(男性)である。彼の成績は常に学年でトップ3を譲らなかった。特に数学の成績は、際立っていた。さらに、大学入試の全国模試においても、何度もトップの成績をとっていた。彼は希望どおりに国立大学の医学部に合格し、順調に人生を歩んでいくように見えた。
異変が起きたのは医学部を卒業して大学院の基礎系に入学したときのことである。
大学院の指導教官は、彼に何も教えてくれなかった。細かい点をいろいろ聞いても、自分で考えろと突き放された。周囲の大学院生は研究室に溶け込み、研究の計画も順調な様子だった。それなのに自分だけが何をしていいかわからないまま、時間だけが過ぎ、大学院に行けない日が続いた。Jさんは、自分で目標を設定することができなかったのである。人生の中で、初めての「失敗」だった。
- date
- writer
- category