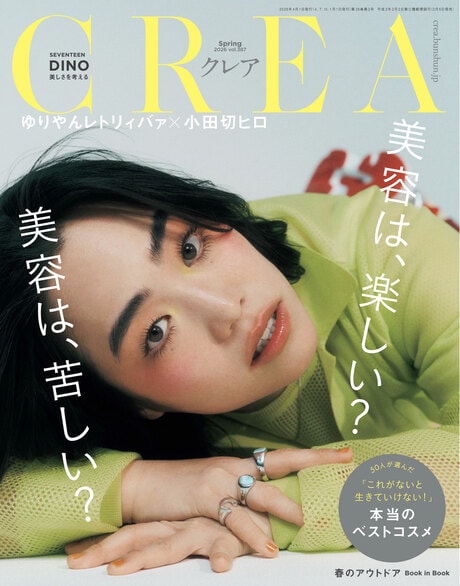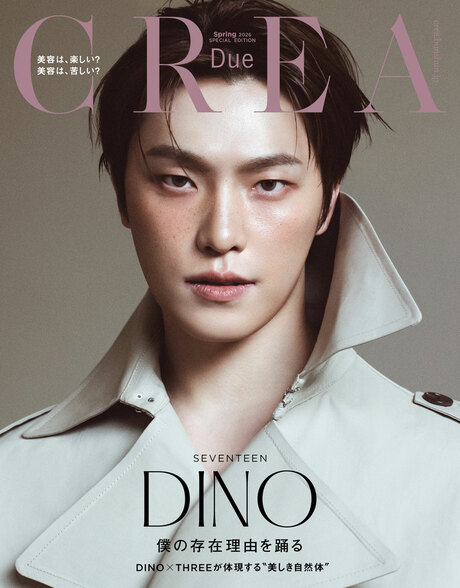「同時代」から「歴史」への転換点
本書が刊行される二〇二五年は、「戦後八十年」「昭和百年」という節目にあたる。これは単なる数字の節目ではなく、「同時代」から「歴史」への転換点に、私たち日本人が立ち会うということを意味している。
「同時代」から「歴史」へ──。それは具体的にはどういうことなのか。
第一に、さまざまな戦争や事件を同時代の出来事として体験してきた人々の「感情」や「情念」が消滅し、それらの出来事が「歴史」のなかに位置づけられるということである。私たちは日々の体験を、皮膚感覚と感情によって生々しく記憶している。しかし、それらを体験した世代がいなくなれば、歴史的事実だけが残ることになる。
第二に、その歴史的事実は、当事者の思惑を超えて後世に理解されるということである。たとえば太平洋戦争には、欧米列強による近代帝国主義を終わらせたという側面もある。言うまでもないが、それによって戦前の日本軍部を美化するわけではない。また、戦争を主導した昭和初期の陸軍エリートたちは、そこまで考えて連合国相手の戦争を始めたわけでもない。だが、結果的に列強の植民地支配が終わり、米ソ超大国による冷戦構造という新しい世界史の時代が始まったのである。
第三に、私たちは「孫の世代」と対話する必要があることだ。同時代の記憶は、容易に風化してしまう。その結果、後の世代がとんでもない過ちをおかすこともありうる。
たとえば江戸時代まで、武士には武士道の美学があった。明治以降も、日露戦争で活躍した乃木希典の世代ぐらいまでは、その精神がたしかに息づいていた。しかし、近代的な軍人教育を受けた世代が主流になると、大きな断絶が起こる。主としてドイツから「戦術」を学ぶことに集中し、その背景にある「戦略」あるいは「軍事哲学」はないがしろにされた。軍内の人事や幹部選抜システムは、ペーパーテストによる成績一辺倒であった。
その結果、昭和初期の軍部エリートたちは近代的効率主義だけを追求する、人間性を忘れたモンスターのような存在に肥大してしまった。天皇という存在を極度に抽象化し、「天皇のためにクーデターを起こす」という、倒錯した論理をもつに至ったのである。