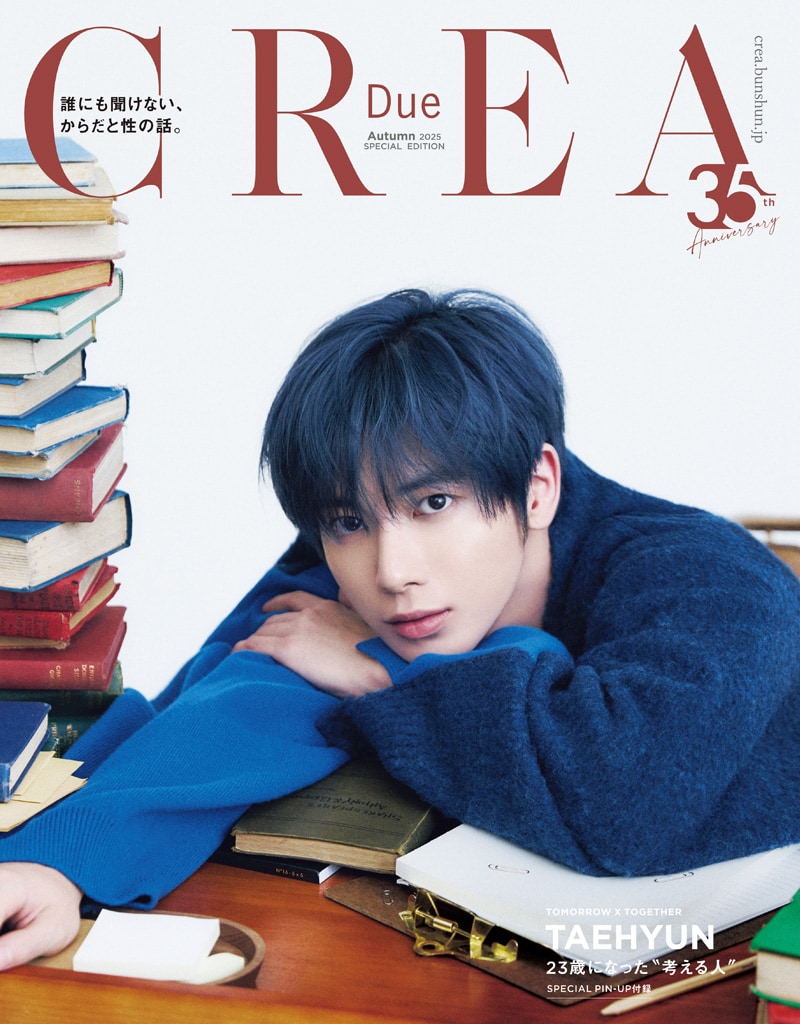私がこの小説を読んでいるときに思い出したのは、二十世紀前半にアメリカに移住したアイルランド系やイタリア系移民が受けた差別や、紀元前からあるユダヤ人の迫害についてだ。ユダヤ系の人には金融業、医師、弁護士、科学者が多いのだが、それは古代のヨーロッパでユダヤ人の就業が禁じられていた職種が多かったからだという説を読んだことがある。また、アメリカのニューヨークやボストンでは、アイルランド系移民の警察官が圧倒的に多い。これも、アイルランド系移民が初期に受けた職業差別が少なからず影響している。二十世紀の日本での在日韓国・朝鮮人によるパチンコ店経営は、これらに似ているところがある。
アメリカは、先住民以外はすべて「移民」とその子孫だ。何世代か遡れば、必ず移民としてのこうした苦労ばなしに行きあたるはずだ。こうしたアメリカ人のDNAに刻み込まれた記憶が、小説への共感を生むのだろう。
日本統治下の韓国での日本人による現地人への虐めや、日本人による在日コリアンへの差別、そして単語こそ出てこないが「慰安婦」のリクルート、日本で在日コリアンが受ける差別など、日本人にとっては居心地が悪い部分もある。
けれども、これは日本人を糾弾する小説ではない。
ニューズウィーク日本版のコラムのための取材で、作者のミン・ジン・リーさんは「私の夫は日本人とのハーフで、私の息子は民族的には四分の一が日本人だ。現代の日本人には、日本の過去についての責任はない。私たちにできるのは、過去を知り、現在を誠実に生きることだけだ」と語ってくれた。
そういったリーさんの日本人への愛情は、この小説に登場する善良な日本人や在日コリアンの言葉からも感じ取ることができる。
むろん、良いことばかりではない。この小説に出てくる在日コリアンの一世、二世、三世が日本や日本人に対して抱く複雑な心理は、白人男性と結婚してアメリカで暮らす私にはとてもよくわかる。裕福で政治的に保守的な夫の家族は、悪気なく差別的な発言をするのだが、日米の血が混じったわが娘のほうが、私よりも過敏なところがある。それは、差別を覚悟で移住した一世の私と、祖国を自分で選ぶことができなかった二世の違いなのかもしれない。『パチンコ』を読んだ後で、娘とそんなことを話し合った。
- date
- writer
- staff
- 文=渡辺 由佳里(エッセイスト/洋書レビューアー)
- category