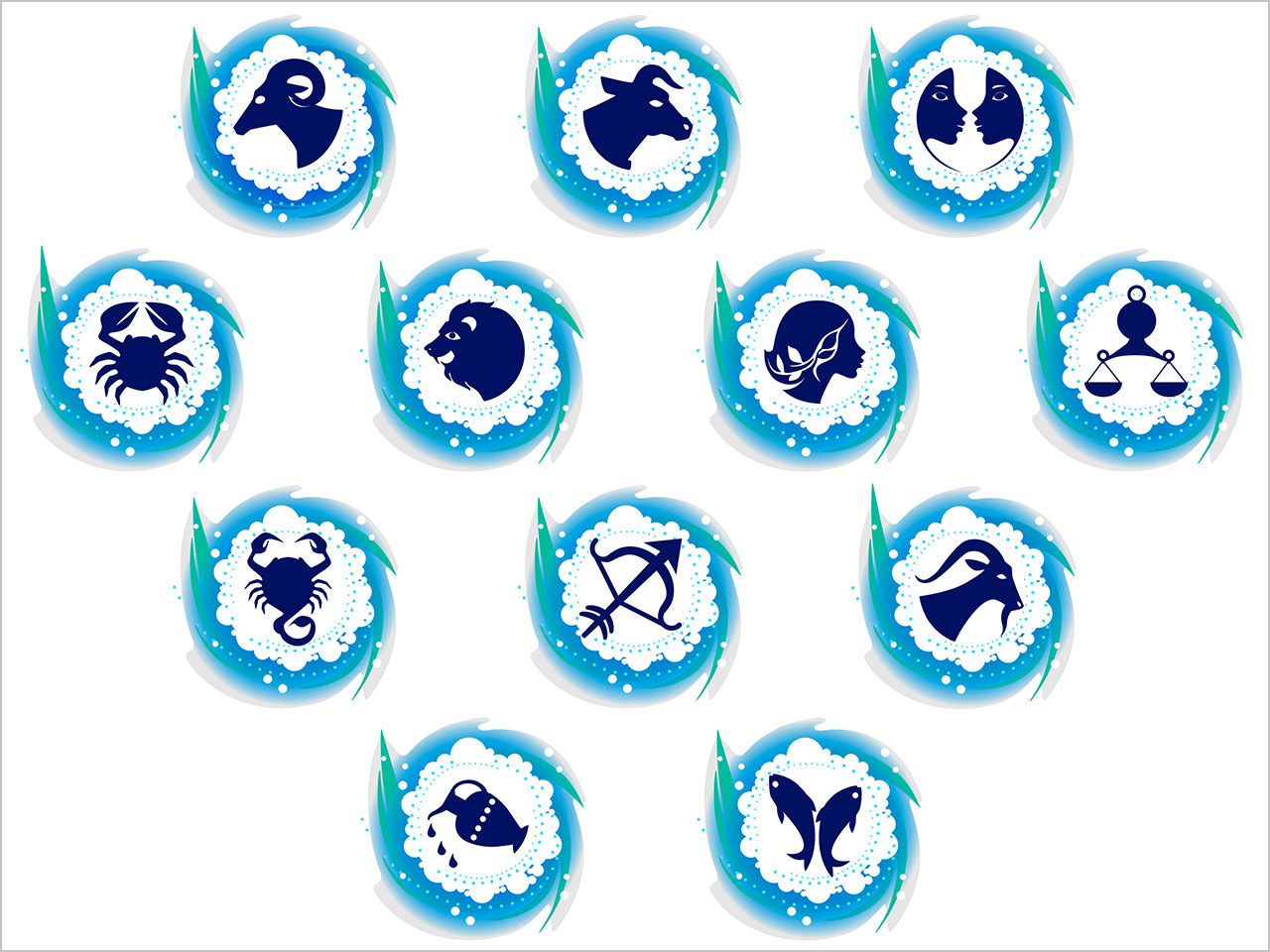ところが『裏切りの日日』は、当時まだ世間で警察小説なるもの、まして公安警察になじみがなかったせいか、話題にもならずに初版で絶版、という憂き目を見た。作者の意気込みに反して、この処女長編は二、三の好意的な書評を除き、ほとんど黙殺される結果に終わった。
その無念が報われたのは、同作で狂言回しを務めた特別監察官、津城(つき)俊輔を再登場させた、『百舌の叫ぶ夜』(一九八六年)を発表してからのことだ。そのときは、すでに初作から五年の月日が、経過していた。この作品も前作同様、公安の刑事を主人公にした警察小説に、トリッキーな叙述スタイルをからませた、さらなる自信作だった。ただ、この時期にしても世間的には、まだ本格的な警察小説の市場は、熟していなかった。
とはいえ『百舌の叫ぶ夜』は、『裏切りの日日』のときと打って変わって、読者の受け入れるところとなった。それどころか、シリーズ化されるまでにいたったのは、われながら予想外の出来事だった。
しかるに、そのシリーズがまだ続いているさなか、オール讀物から新たに警察小説を書いてほしい、という要請がきたのだ。この注文は、わたしにとってはむしろ意外な出来事で、少なからず面食らったものだった。百舌シリーズによって、警察小説ブームに先鞭をつけた一人、と自負していたわたしとしては、今さら別の警察小説を書いてほしい、という注文がくるとは、考えてもいなかったのだ。もしかすると百舌シリーズは、市場をにぎわす警察小説の一つとは、認められていなかったのではないか。
だとすると、ここでわたしが別の警察小説に手を染めれば、逆に現下のブームに乗ろうとしている、と見られる恐れがある。自意識過剰もいいところだが、常にだれも書いたことのない〈テーマ〉を取り上げ、異色の〈キャラクター〉を創出することを目標にしてきた身には、他作家の〈後追い〉だけはしたくない、という思いが強かった。
しかしプロの作家として、編集者の注文に応じられないというのも、情けないではないか。こうなったら、新たな警察小説を書くしかない。ただ書くからには、これまでだれも書いたことのない、読者の感情移入をこばむような悪徳刑事を、主役に据えよう。その主人公が、さんざん悪いことを繰り返したあげく、最後にみじめにくたばるのだ。
- date
- writer
- category