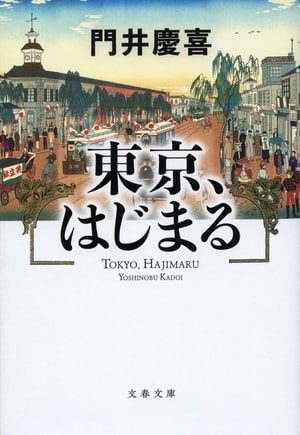
東京駅(東京駅丸ノ内本屋)が開業したのは、一九一四年のことだ。関東大震災による被害は免れたものの終戦間近の空襲により一部を焼失、本来は三階建てだったが、二階建てで修復されたまま長らく利用されてきた。しかし、二〇〇三年に駅舎が国の重要文化財に指定されたことを追い風に、JR東日本による「東京駅丸の内駅舎保存・復原工事」プロジェクトが本格始動。五年余りにわたる工事期間を経て、創建当時の姿を現したのは二〇一二年一〇月のことだった。
建築物はタイムマシンだとよく言われるが、まさにそれ。復元された南北のドーム天井とレリーフは、真新しいもののはずなのにどこか懐かしく、一〇〇年前を夢想せずにはいられないものだった。それ以上の衝撃は、外観からもたらされた。赤レンガの壁に嵌め込まれた白い大きな窓とストライプ、その配置と彩色のバランスは端的に美しい。残存していたオリジナルのレンガをできる限り活かしつつ、高度な技術によって再現された創建当時の赤色が──白は赤を際立たせるための色だ──見る者を魅了した。それと同時に、一つの疑問を生じさせたのではないかと思う。なぜ一〇〇年前にこの鮮烈なデザインが選ばれたのか?
その疑問に、このたび文庫化された『東京、はじまる』は一つの答えを差し出している。直木賞作家・門井慶喜の筆による本作は、東京駅をはじめ数々の有名建築物の設計を手がけた建築家・辰野金吾の一代記である。
物語は明治一六年の横浜、金吾が三年ぶりに日本の地を踏み締めた場面から始まる。金吾は官立の工部大学校造家学科の第一期首席となり、日本の建築界では初めて国費留学生として、師匠ジョサイア・コンドルの祖国イギリスに逗留していたのだ。もうすぐ三十路を迎えようとする金吾は、少し焦っている。出迎えに来てくれた大学以前からの親友・曾禰達蔵に「ぜひ東京にたくさん斬新な建物をつくってくれ」と声をかけられると、「ちがうなあ」「柄が、小さすぎる」と物申す。「そこは東京にじゃない。東京をとすべきじゃないか、曾禰君。ひとつひとつの物件など、しょせん長い道のりの一里塚。私はつまり、最後には、東京そのものを建築する」。だから、己は一刻も早く現場に立つ。「東京の街づくりは、すでに始まっている。私が一日休めば、その完成は一日おくれるんだ」。本作の方向性を決定付ける、名台詞だ。
文=吉田 大助(ライター)



























