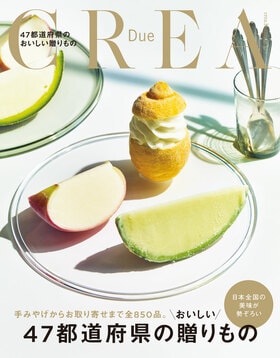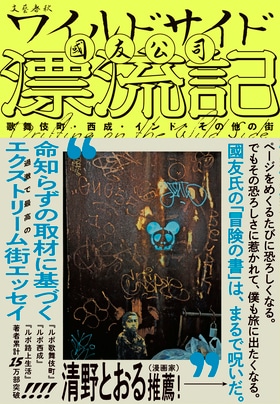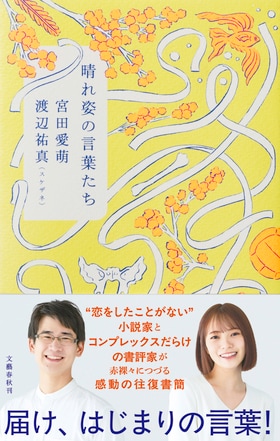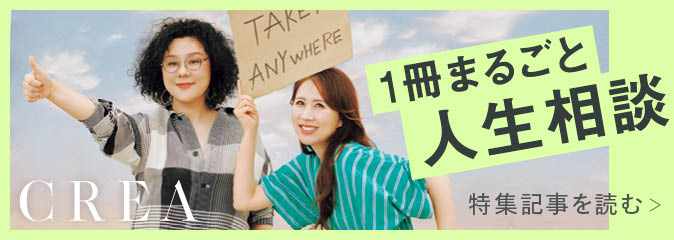見どころは「大きな岩、滝、そして七福神」
ガイドでは仁淀川の名前の由来、仁淀川の地形ができた理由、植物の話などを中心に伝える。「渓谷なのに植物?」と不思議に思う人がいるかもしれないが、二つ隣の佐川町は植物学の大家、牧野富太郎博士の故郷だ。牧野博士は中津川流域へ何度も植物採集に訪れた。中津渓谷を通るコミュニティバスの終点「上名野川」から少し奥に入った神社で「ヤマトグサ」を発見し、日本で初めて学術誌に発表した。このため、日本の近代植物分類学の発祥の地とされる。
井上さんは、中津渓谷の見どころは「大きな岩、滝、そして七福神」と言う。

「この辺はチャートと言って動物性プランクトンの死骸が深海で堆積した岩石でできています。チャートは大きく割れる性質があり、だからこんなに大きな岩がいっぱいあるんですよ」と説明する。
七福神は遊歩道から見える場所に石像が置かれていて、「竹下登内閣のふるさと創生1億円事業で設置されました」と教えてくれた。
雄大な自然と人為の石像は異質なように見える。が、意外に楽しそうに探しながら歩いている人が多かった。「心がきれいな人しか見えない」と言われるほど、見つけにくい石像もあるのだという。
地層の話が非常に面白かった
県庁で「コミバス旅」のPRを担当している西森大祐・観光政策課チーフは「5年ほど前、ガイドに同行したことがあり、地層の話が非常に面白かったのを覚えています」と話していた。
仁淀川水系は複数の地質帯を貫いて流れている。このため河川が浸食する岩の種類が多く、赤、緑、白、灰、黒といった五色の石が見られる。これらが太平洋に下って、桂浜(高知市)に打ち上げられる。
巨岩の中を歩いていると、異界に迷い込んだかのような気持ちになる。
「まるでダンジョンRPG(地下迷宮や洞窟で宝探し、戦闘をするロールプレイングゲーム)の世界のようだ」と言われることがあるのもうなずける。

2025.05.22(木)
文=葉上太郎