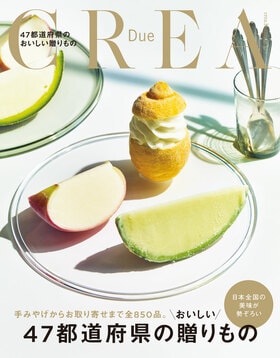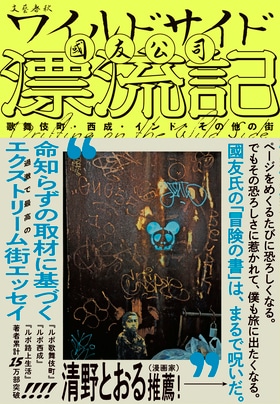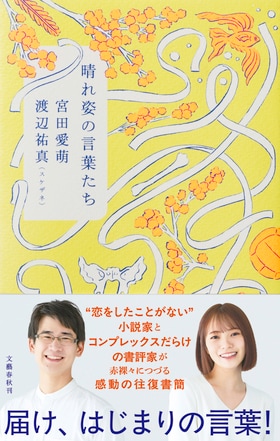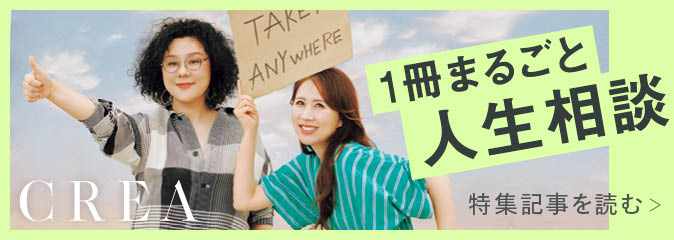モクズガニだ。ついに千代川でモクズガニを捕獲した!

全て手探りで調査しただけに嬉しさがこみ上げる。挟まれないようしっかり観察してみた。

爪の周りにふさふさした毛のようなものが見えるが、このはさみ脚に生えた毛が藻屑に見えることからモクズガニと呼ばれるそうだ。つまり、毛はモクズガニのアイデンティティみたいなもの。こすって簡単に取れるものでもなかった。
腹側にある三角形をした部位(ふんどし)が広く丸みを帯びていればメスで、細長い三角形ならオスだ。メスは卵(外子)を包み込むため広く発達している。
続けて残りの2つのカゴも見に行こう。期待たっぷりでカゴを引き上げると……残念ながらどちらも不在であった。今朝の収穫は一匹。しかし、カニの生息を確認できる大きな手掛かりとなった。
捜索範囲を拡大してモクズガニを狙う
モクズガニ調査は次のステージへ。
河口エリアには一つだけカゴを残し、捜索範囲を拡大することにした。あわせて釣具屋で大サイズのカニカゴを追加し、万全の態勢で挑む。

選んだポイントは河口から約20km上がった中流エリア。都市部から一変、山に囲まれた自然豊かな景観が広がる。

川幅も狭まり、砂利や玉石でできた川底は、当初思い浮かべていたモクズガニ採りのイメージそのもの。

しかし思いのほか水深が浅く、それでいて流速がある。これではカゴを仕掛けることができない……。そう判断して再び移動した。続いての候補は石積と消波ブロックで護岸された急流エリア。人工物の隙間に隠れたモクズガニを狙う。

夜になり隙間から出てきたモクズガニを大サイズの網におびき寄せて一網打尽にする作戦だ。消波ブロックの隙間はカニが移動しやすいほど流れが緩く、カゴも仕掛けやすい。

移動中に拾ったすでに絶命しているウグイとマイワシをカゴに仕込んで夜を待った。

20時ごろ急流エリアに戻ってカゴを引き上げると、信じられないことに一匹もカゴの中に入っていない。小サイズのカゴも付近に仕込んでおいたが、共に空振り。
しかし、カゴの真下から器用に中の魚を捕食するモクズガニが……! 手づかみで捕獲した。

一匹いればまだ潜んでいるはず。そう確信して、同ポイントのカゴはそのままにし、翌日の日の出前に再び引き上げることにした。
2025.04.07(月)
文=ぬこまた釣査団(大西)