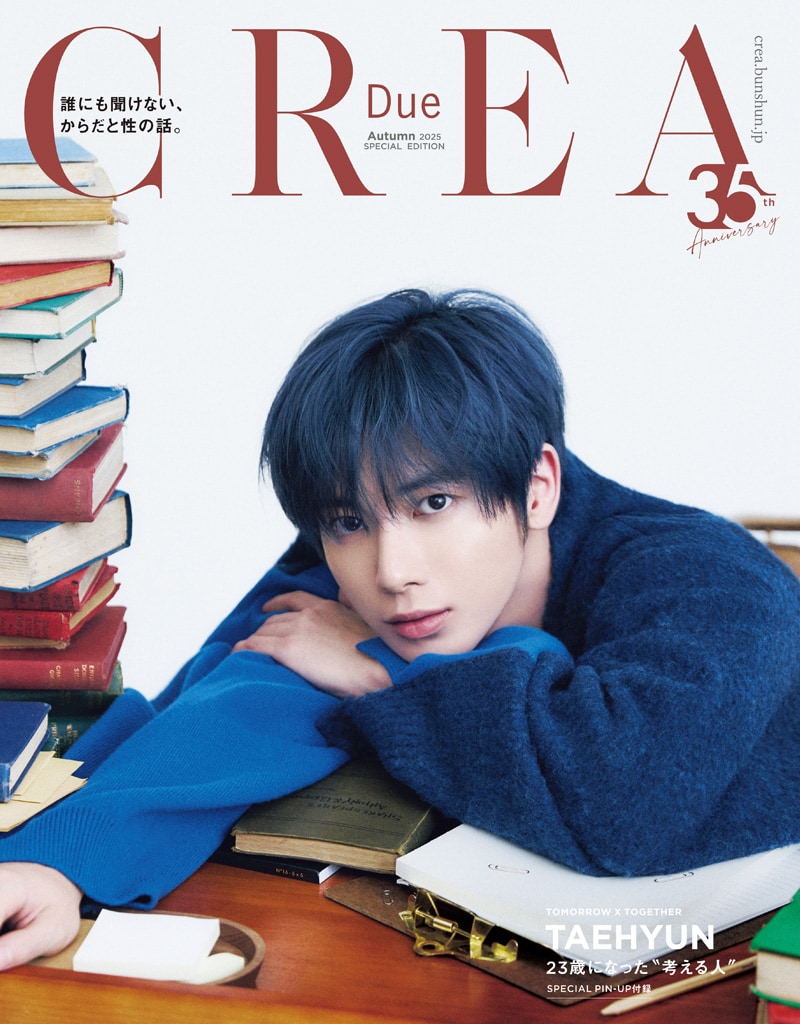その言葉に、カラスが「おっかない嫁だのう……」と羽をすぼめた。
雪乃は目を丸くして動きを止めている。驚きからか、表情から毒気が抜けていた。
──さっきまで空虚だったその瞳に、やがて、ぽつんとした明かりが灯った。
感情の失せた顔が、徐々に歪み始めていく。
頬が震え、眉が下がり、曲がった唇からは引き攣ったような呻き声が漏れた。
ひっ、と息を吸い込むとともに、みるみるうちにその目が透明な水膜に覆われる。
「……っ、なっ、奈緒、さん」
「ええ」
「わ──わたし、ほんとは、本当はね……他に、す、好きな人がいるの……」
「まあ、素敵。だったらなおさら、こんなところにいる場合じゃないわ。森を出て、すぐにでも会いに行かないと」
「お、親の言うことを、聞かなくても、いいのかしら。いっ、嫌だと、言ってもいい? わたしのこと、身勝手で恩知らずな、ひどい娘だと思う……?」
「誰だって、自ら進んで不幸になりたくないのは当然よ。ひどい娘だなんて思わない。この道は間違いだと思うなら、自分の意志で別の方向へ行けばいいのよ」
雪乃の目から、大粒の涙がこぼれて落ちる。
ぎゅうっと手を握りしめると、痛いほどの力で握り返された。
「わたし、わたしね、ずっと、誰かに話を聞いてほしかった……味方になってほしかった……て、手を取って、一人じゃないって、言ってほしかったの……!」
その時だ。
足元の雪乃の影から、にゅるんと飛び出すように別の黒い影が長く伸びた。
「分離した」
青年が短く言って、手にしていた刀を素早くその影に向かって振り下ろす。
ひゅ、と鋭く空気を切る音がした。
滑るように地面を這ってどこかへ逃げようとしていた影は、刀が自身に食い込んだ瞬間、縫いつけられたようにぴたっと動きを止めた。
ざわりと一度、不気味に揺れたのは最後の抵抗か。
闇色がすうっと薄まり、端のほうから少しずつ消えていく。まるで、床に撒いた墨汁を綺麗に拭い取るかのようだった。
- date
- writer
- category